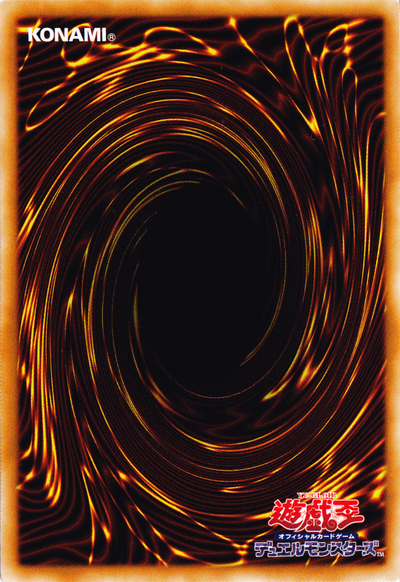漫画『
遊☆戯☆王』に登場するトレーディングカードゲーム(TCG)。
原作となる漫画での名称は「マジック・アンド・ウィザーズ」だが、
東映アニメ版等、一部の媒体では「デュエルモンスターズ」と呼称され、
NASによるアニメ第2作(と言うかリメイクアニメ)『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』以降はそちらに統一されている。
現実の日本においてもTCGの立ち位置を大きく引き上げた歴史に残る存在であり、
トレーディングカードゲームを「デュエル(決闘。
ヒューゴーの
勝利台詞の「ドゥエル」もこれの事)」
と称する事を広め、定着させたと言ってもいいだろう
(実はこの表現を最初に使ったのは、世界初のTCG『
マジック:ザ・ギャザリング』。
なのだが、現在は『デュエルモンスターズ』を発売しているコナミが商標登録をしているため MTG側は「ゲーム」と言い替える羽目になっている)。
転じて本TCGで対戦するユーザーを「決闘者(デュエリスト)」とも言う
(そもそもMTGの公式誌の名前が『The Duelist』(1999年廃刊)である。
なので中二病ではない
なお前述の理由により現在は「プレーンズウォーカー(世界を歩く者=自力で異世界転移が可能)」と呼んでいる(小説等では昔からこの肩書))。
原作におけるマジック・アンド・ウィザーズ(デュエルモンスターズ)
ゲーム企業「インダストリアル・イリュージョン」が発売しているTCGで、
名誉会長である
ペガサス・J・クロフォードによって作り出された。
彼がかつて恋人と死別した後、現実逃避するように訪れたエジプトで鑑賞した、
古代エジプトの「名も無きファラオ」と魔術師達が魔物を使役する壁画をヒントにデザインしたカードだが、
実はこの壁画の光景は史実であり、千年アイテムの使い手達と彼らが使役する魔物を記した物で、
ペガサスは自覚無しにこの古代の精霊や魔物達……そしていずれ蘇る名も無きファラオの記憶を取り戻すのに必要な、
生前のファラオが使役した三幻神「オシリスの天空竜」「オベリスクの巨神兵」「
ラーの翼神竜」を現代に甦らせる使命を与えられていたという。
古代魔術師達は
心の底に潜む深層心理の精霊を実体化させて使役できるが、
千年アイテムの使い手達は例外的に他者の精霊や魔物を石板に封じ込めて使役することが可能で、
それが作中の現代のカードゲームの起源となったのである。
しかしながら石板が全ての始まりという事でもなく、世界は1枚のカードから始まったという設定もあるので
「カード→石板→カード」という進化の道を辿っていることになる。
ゲームとしてのデュエルモンスターズ
東映版時代はバンダイの
カードダスとして登場。しかし良くも悪くも
原作再現な
てきとーなルールだったため、全然ヒットせずに終わる
(更には東映版アニメ自体も子供達の混乱を避ける為か再放送やDVD化に恵まれていない)。
現在は
コナミデジタルエンタテインメントが「遊☆戯☆王オフィシャルカードゲーム」の名で製作・販売している。
こちらは
多少原作無視をしてでもゲームとしての面白さを成立させている
(原作の枷が外れたアニメ版3作目以降はコナミ版のルールに準ずる様になった。
ディスティニードロー?シャイニングドロー?なにそれ知らん)。
原作の人気も相まって、原作完結後もアニメ独自の続編を発表しながら10年以上人気を維持し続けているコンテンツであり、
2009年7月にはギネス・ワールド・レコーズに「世界で最も販売枚数の多いトレーディングカードゲーム」として認定された。
|
+
|
ルール・用語 |
原則として対戦は1対1の3セットマッチで、8000ある相手のライフポイントを先に0にした方が勝ちとなる。
これ以外にも特殊勝利カードやデッキキルなど、ライフが0にならずとも勝利する方法もある。
戦闘を行い、相手モンスターの攻撃からプレイヤーを守ったり、
相手モンスターを破壊したり敵のライフにダメージを与えるカード。
攻撃力と守備力を持ち、縦が「攻撃表示」、横が「守備表示」を示す。
基本的に攻撃表示のモンスターのみ攻撃が可能で、守備表示のモンスターは能動的にライフを減らせない(一部例外有)。
モンスターはそれぞれバトルフェイズに1度攻撃権を持ち、
- 攻撃力<攻撃力:攻撃力が低い側が破壊され、攻撃力の差分だけライフにダメージが発生
- 攻撃力=攻撃力:両方のモンスターが破壊される(攻撃力0同士の場合は互いに破壊されない)
- 攻撃力<守備力:モンスターは破壊されず、攻撃したプレイヤーが守備力―攻撃力の差分だけダメージを受ける
- 攻撃力>守備力:守備側のモンスターは破壊されるがダメージは発生しない
- 攻撃力=守備力:双方破壊されずダメージも発生しない
となる。
なお、相手の場にモンスターがいない場合は相手プレイヤーへダイレクトのダイレクトアタックが可能であり、
モンスターの攻撃力がそのままライフへのダメージとして発生する。
手札及び魔法罠ゾーンから発動する緑のカード。
自軍モンスターの強化、邪魔な相手のモンスターの除去、手札の確保など効果は千差万別で、
モンスターとの組み合わせにより、戦略の幅を大きく広げる。
原作では相手ターンでもバンバン使用しているが、OCGでは相手ターンに発動できるのは速攻魔法のみ。
魔法罠ゾーンから発動する赤紫のカード。
相手ターンでも発動できるが、セットしたターンに発動できず、手札からの使用は一部例外を除き不可能。
エクストラデッキとはメインのデッキとは別に15枚まで用意できるデッキ。
シンクロモンスター登場以前は融合モンスター専用であったために融合デッキと呼ばれ枚数に制限はなかったが、
シンクロモンスター登場に伴うルール変更により名称を変更された。
特定の条件を満たすことでのみフィールドに召喚可能な「融合モンスター」「シンクロモンスター」「エクシーズモンスター」「リンクモンスター」は、
原則ここから召喚される。
|
+
|
エクストラモンスター |
記載されている素材となるモンスターと「融合」魔法カードにより召喚される。
世代を増すごとに「融合」効果を持つモンスターが登場したり、
デッキや墓地のモンスターを素材にできるカードが登場している。
シンクロモンスターに記載されている素材となる「チューナー」と呼ばれるカテゴリのモンスター及びそれ以外のモンスターを素材にして、
素材となるモンスター達のレベルを合計したものと同じ数値のレベルのシンクロモンスターが召喚される。
通常は自分フィールド上の同じレベル同士のモンスターを素材にして召喚される。
一部はランクアップなど通常と異なる手順でエクシーズモンスターを強化するように、
エクシーズモンスターに重ねてエクシーズ召喚扱いで特殊召喚するカードもある。
なお、エクシーズモンスターにはレベルが無く、代わりにランクと呼ばれる概念がある。
素材となったカードはX素材(アニメではオーバーレイユニット)としてモンスターの下に重ねられ、
効果の発動と同時に消費されて墓地に送られる。
破壊されると表向きでエクストラデッキに送られるカード群。
各自「スケール」と呼ばれる数値を持ち、自分の左右両端の魔法&罠ゾーンにペンデュラムモンスターを魔法カードのようにセットし、
左右のペンデュラムゾーンに置かれたモンスターのスケールの数の間のレベルを持つモンスターを、
自分の空いているメインモンスターゾーンの数まで手札とエクストラデッキから好きなだけ特殊召喚する「ペンデュラム召喚」を使用できる。
召喚するリンクモンスターのリンク数と、モンスターに記述された召喚条件、
これら2つを満たしたモンスターを素材としてフィールドから墓地に送り召喚される。
リンクモンスターには守備とレベルの概念が無い。
|
|
また
レアカードのオマケとしてゲームソフトも複数発売されている。
『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』『II 闇界決闘記(ダークデュエルストーリーズ)』、
『III 三聖戦神降臨(トライホーリーゴッドアドバント)』『4 最強決闘者戦記(バトル オブ グレイト デュエリスト)』はGB四部作として知られている。
『I』では
青眼の白龍だろうがコスト無しで出せる大味なゲームだったが
(そのため、当時の公式大会では禁止カードや枚数制限など独自のルールが作られた)、
『II』では攻撃力の差を無視して属性相性で勝敗を判定するシステムが追加されたり、
『III』ではOCGのようないけにえルールの追加や、専用パーツを組み合わせてオリジナルのカードを作るコントラクションモードが登場するなど、
ゲームバランスの調整や独自のユニークなシステムの追加が行われている。
しかし、当時の技術の限界で作りが粗い部分もあり、クソゲー扱いされることも多々ある。
具体例を挙げると、『I』では相手のライフポイントに5000ダメージを与える「火炎地獄」というカードが注目されたが、
入手方法が
「200人以上の相手と通信対戦する」というぼっちじゃなくても不可能な条件など、
ゲーム性以前の問題も見られた。
とはいえ、当時の技術的限界による粗さやこうした達成が非現実的な部分以外の要素を楽しみながらプレイしていたユーザーは多数おり、
2025年には初期ゲーム14作品収録されたNintendo Switch用『遊戯王 アーリーデイズコレクション』も発売された。
なお、実物のカードにはそれぞれ8桁のナンバーが記載されており、
これを入力することでゲームでも同種のカードを入手することが可能だった。
現物のカード入手とゲームのカード入手を連動するための仕様であったが、
(当時のカード一覧の書籍では意図的にナンバーが省かれている物ばかりだった)
インターネットの発達に伴い未購入でもナンバーの把握が容易な情勢になってしまったので、
途中からはパスワードのカードに制限が付くようになり(条件を満たさないと入力できない、使うと報酬が減る、枚数制限があるなど)、
『ZEXAL』の頃からは廃止された。
ただ連動自体が廃止されたわけではなく、ゲームのみだったカードが後に実物のカード化された場合は、
元のゲームで使用できるパスワードが記載されている。
(極端な例では、『4』から21年経ってOCG化されたカードのパスワードが『4』で有効)
それ以降のゲーム作品は比較的OCG寄りに作られているが、
ややルールを簡略化させつつ世界中の決闘者と気軽に戦えるソーシャルゲーム『遊戯王デュエルリンクス』のように、
完全な再現ではないにせよ大きく評価を受けた作品もある。
また、2022年1月にはOCGに沿ったオンラインゲーム『遊戯王マスターデュエル』がリリースされた。
バーチャルYouTuberグループ「にじさんじ」などのプレイ配信が好評を博している。
加えて、2022年の9月には複数人で対戦する『遊戯王クロスデュエル』がリリースされた。
残念ながら2023年9月4日にサービス停止となった。
この他、派生コンテンツとして「ラッシュデュエル」が存在する。
ニコニコにおけるデュエルモンスターズ
デッキ指南や決闘の様子など、多くの動画が投稿されている。
特にその1人であるZirai(福袋)氏は公式に彼の投稿動画をネタにしたデッキレシピを公開されたことで有名。
MUGENにおけるデュエルモンスターズ
NKYMD氏の製作したキャラ……?が公開中。
人操作はできず、撃破挑戦用に近いキャラである。
スプライトはGB版のものが使用されている。
ライフもとい体力は8000あり、ATKの数値が相手に与える大体のダメージとなる。
召喚モンスターのATKを超えるダメージを与えなければ相手にダメージが入らず、
ダメージが入らなかった際(ATK-受けたダメージ)で反撃する。
このため、対戦相手は召喚モンスターのATKを超える火力をぶつけなければ倒せない。
例外的に封印されしエクゾディアだけは攻撃する度についでにパーツが溜まり、全部揃うと
即死攻撃を放つ。
|
+
|
召喚モンスター |
- 1P:ワイト(ATK:300)
- 2P:ホーリー・エルフ(ATK:800)
- 3P:封印されしエクゾディア(ATK:1000)
- 4P:砦を守る翼竜(ATK:1400)
- 5P:炎の剣士(ATK:1800)
- 6P:サンド・ウィッチ(ATK:2100)
- 7P:真紅眼の黒竜(ATK:2400)
- 8P:双頭の雷龍(ATK:2800)
- 9P:青眼の白龍(ATK:3000)
- 10P:完全究極態・グレート・モス(ATK:3500)
- 11P:青眼の究極竜(ATK:4500)
- 12P:ランダムモード
|
出場大会
最終更新:2025年03月18日 03:51