CentOS
この項目では、従来のCentOSについて説明しています。CentOS Streamについては「CentOS Stream」をご覧ください。

▲CentOSのロゴ
CentOSは、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)との機能的な互換性を目指したLinuxディストリビューション。
2020年12月8日に、現行の「CentOS 8」の開発を2021年末をもって終了し、今後はアップストリームである「CentOS Stream」の開発に注力する旨が発表された。(*1)
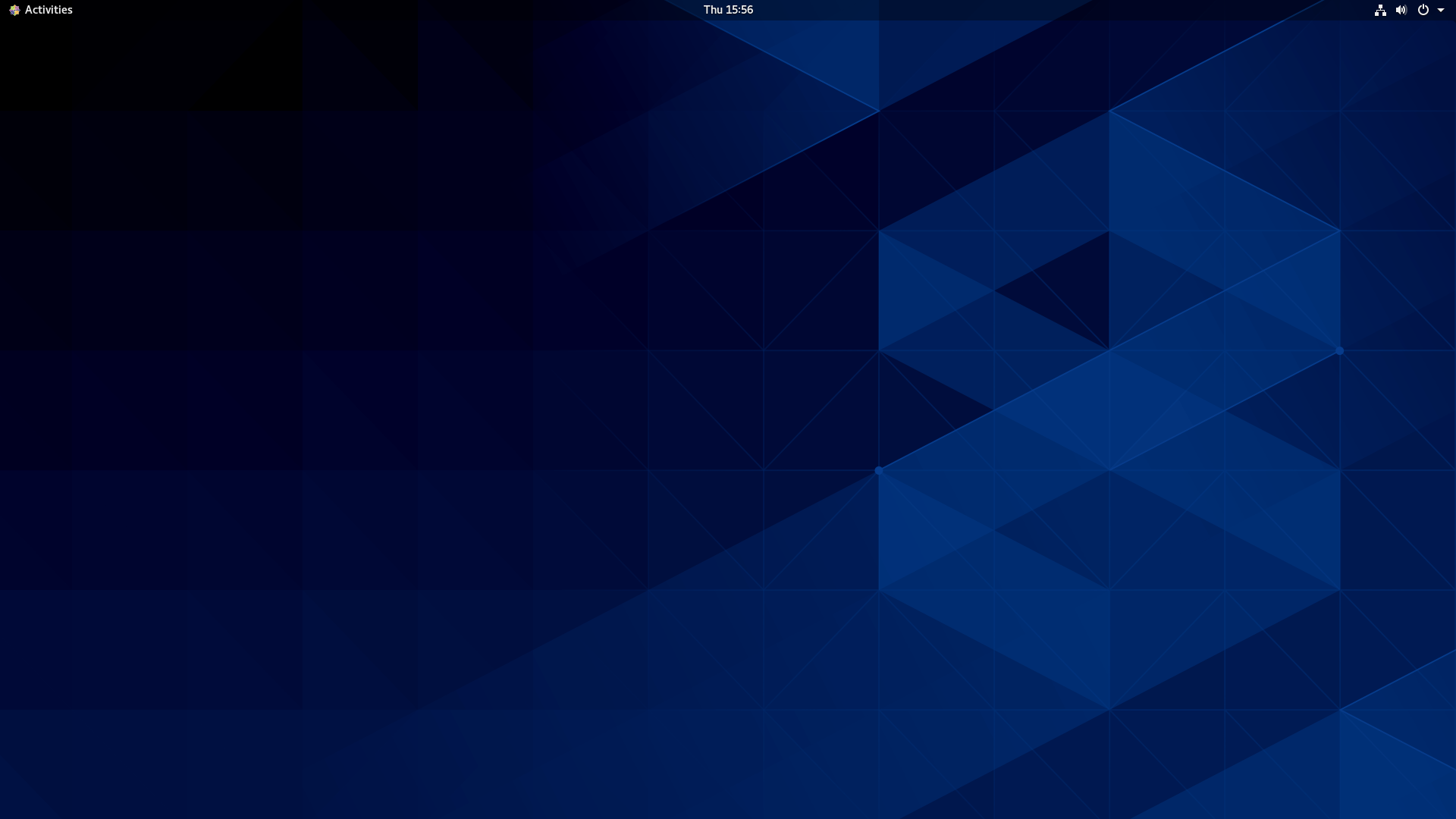
▲デスクトップ画面(CentOS 8.0-1905 GNOME)
各種データ
各種データ
| 開発者 | The CentOS Project |
| 系統 | Red Hat系 |
| 開発状況 | 開発中 |
| 初版 | 2004年5月14日 |
| 最新安定版 | 8: 8.3-2011 / 2020年12月7日 7: 7.9-2009 / 2020年11月12日 6: 6.10 / 2018年7月3日 |
| アップデート方式 | Yum , DNF |
| パッケージ管理 | RPM |
| カーネル | Linux |
| デスクトップ環境 | GNOME , KDE |
| ライセンス | GPLほか |
| ウェブサイト | https://www.centos.org/ |
概要
Red Hat社はRHELに含まれているソフトウェアのソースコードをオープンソースライセンスに基づき無償公開している。
CentOSはこれをもとに、商標や商用パッケージ等を除去したものをリビルドしている。
CentOSはこれをもとに、商標や商用パッケージ等を除去したものをリビルドしている。
CentOSやWhite Box Enterprise Linux、Scientific Linuxなどをまとめて、「RHELクローン」と呼ばれることがあるが、CentOSプロジェクトのFAQでは"CentOS Linux is NOT a clone of Red Hat® Enterprise Linux."と記載されており、RHELのクローンではないとしている。
CentOSでは、RHELに由来するソースコードは変更されないように意図されているが、CentOS独自の追加機能を提供するリポジトリを提供している。
歴史
RHELの一般公開されたソースコードに基づくディストリビューションとしては、CentOSより先にWhite Box Enterprise Linuxがリリースされていた。
これが人気を得たことを契機にCentOSプロジェクトは有志のボランティアにより立ち上げられた。
これが人気を得たことを契機にCentOSプロジェクトは有志のボランティアにより立ち上げられた。
CentOSの名は「コミュニティベースで開発されたエンタープライズクラスのオペレーティングシステム (Community ENTerprise Operating System) 」に由来する。
開発当初、Red Hat社はCentOSの配布・開発に関与してこなかったが、2014年1月にCentOSプロジェクトを支援していくことを発表した。
また、CentOSプロジェクトの中心メンバーを同社員として迎え入れた。
また、CentOSプロジェクトの中心メンバーを同社員として迎え入れた。
2020年12月8日にThe CentOS Projectは、現行の「CentOS 8」の開発を2021年末をもって終了し、今後はアップストリームである「CentOS Stream」の開発に注力すると発表した。(*2)
CentOS公式ブログではCentOS 8終了後の移行先として最善の選択肢はCentOS Streamであるとしているが、CentOS StreamはRHELの開発ブランチでこれまでのCentOSとは異なり、2029年までを予定していたCentOS 8のサポート期間が大幅に短縮されたことなどから、コミュニティのメンバーからは不満の声が上がっている。(*3)
また、新しいRHELクローンとして、CentOSの共同創設者であるGreg Kurtzer氏が「
Rocky Linux
」を、CloudLinux社が「Project Lenix」を発表している。(*4)(*5)(*6)
Project Lenix改めAlmaLinuxは、8.3が2021年3月30日にリリースされた。
Project Lenix改めAlmaLinuxは、8.3が2021年3月30日にリリースされた。
ターゲット
ターゲットはRHELと同様、企業のサーバやデスクトップ環境の構築としている。
デスクトップ利用も想定されていることから、高機能なGUI環境も標準で提供されている。
デスクトップ利用も想定されていることから、高機能なGUI環境も標準で提供されている。
LibreOfficeやOracle VM VirtualBoxなどのパッケージや、後述のサードパーティーのリポジトリを用いてビジネスソフト、デスクトップ仮想化ソフト、GPUや周辺機器のデバイスドライバ、セキュリティソフト、デジタルコンテンツ制作ツール、メディアプレーヤー、ビデオコーデックなどをインストールすれば、本格的なデスクトップOSとして使用することが可能である。
CentOSプロジェクトは、サポートが必要な場合にはRed Hat社の製品を勧めるとしている。
ライセンス費用が無償であるにもかかわらずサポート期限が非常に長く、メンテナンス更新期限はRHELと同じく10年(CentOS 4以前は約7年)程度である。
数あるRHELベースのディストリビューションの中でも安定性に優れ、一部メーカーのLinux搭載パソコンやワークステーションでの採用も増加しつつある。
パッケージ管理
ツール
CentOSはパッケージ管理システムにYumおよびその後継のDNFを採用している。
RHELがRed Hat Networkサーバをデフォルトにしているのに対し、CentOSではCentOS Mirror Networkがデフォルトとして用意されている。
RHELがRed Hat Networkサーバをデフォルトにしているのに対し、CentOSではCentOS Mirror Networkがデフォルトとして用意されている。
リポジトリ
CentOSにデフォルトで含まれるリポジトリ(Base, Updates, Addons, Extras, CentOS Plus)に加えて、Fedoraが提供するEPEL(Extra Packages for Enterprise Linux)、サードパーティーのNux Dextop リポジトリやRPM Fusion、ELRepo、Les RPM de Remi、RPMForge、JPackageなどがよく使われている。
なお、CentOS Plusはデフォルトでは無効化されている。
なお、CentOS Plusはデフォルトでは無効化されている。
RPMForge及びRemiに関しても、オリジナルのパッケージを上書きしてしまう可能性があるとしてインストール後はOFFにして運用することが一般的である。
リリース
完全更新は新たな機能の追加とセキュリティパッチ配布を意味し、年2~4回が予定されている。
その後は必要不可欠なセキュリティパッチ配布のみを想定している。
その後は必要不可欠なセキュリティパッチ配布のみを想定している。
番号の規則
CentOS 6以前はメジャーバージョンとマイナーバージョンの二つより構成される。
メジャーバージョンはベースとしたRHELに対応しており、マイナーバージョンはそのRHELのバージョンアップに対応する。
例えばCentOS 4.3はRHEL 4 update 3のソースコードよりビルドされており、これとの互換が目標となっている。
メジャーバージョンはベースとしたRHELに対応しており、マイナーバージョンはそのRHELのバージョンアップに対応する。
例えばCentOS 4.3はRHEL 4 update 3のソースコードよりビルドされており、これとの互換が目標となっている。
CentOS 7以降はメジャーバージョンとマイナーバージョンに加えて、タイムスタンプ(年、月)が追加された。
例えばCentOS 7.0-1406はRHEL7.0の2014年6月にリリースされたソースコードを基にしていることを示している。
例えばCentOS 7.0-1406はRHEL7.0の2014年6月にリリースされたソースコードを基にしていることを示している。
サポート終了済み
| + | ... |
サポート期間中
| - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アドオン
アドオンは /opt ディレクトリに並行してインストールされて提供される。
scl ユーティリティによってはアプリケーションごとに選択できる。
scl ユーティリティによってはアプリケーションごとに選択できる。
これらはCentOSで標準的に提供されるパッケージを置き換えるものではなく、例えばPerlやMySQLの標準のバージョンはCentOSの基本的なインストールのままである。
Software Collections(SCL)はより新しいバージョンに含まれる、もしくはシステムに元来含まれていない動的プログラミング言語、データベースサーバ、それらに関連した様々なパッケージを提供するリポジトリである。
| アドオン名 | CentOSのバージョン | CentOSのリリース日 | RHELのリリース日 | 遅延 |
| Software Collections(SCL)1.0 | 6.4 | 2014年2月19日 | 2013年9月12日 | 160日 |
| Developer Toolset 2.0 | 6.4 | - | 2013年9月12日 | - |
派生ディストリビューション
- CloudLinux OS
- NuOnce Networks CentOS / BlueQuartz CD
- BlueOnyx
- Openfiler
- Rocks Cluster Distribution - コンピュータクラスタ用のディストリビューション
- SME Server
- Trixbox - PBXソリューション
- XenEnterprise
- PBX in a Flash
- FreePBX Distro
外部リンク
脚注に記載されているウェブサイトへのリンク
- CentOS 8の提供は2021年で終了、今後はCentOS Stream開発に注力 | マイナビニュース
- CentOS終了にコミュニティからは非難の嵐、CentOSの設立者が新プロジェクトの発足を発表する事態に - GIGAZINE
- CentOSに代わる新しいRHELダウンストリーム「Rocky Linux」が正式に発足 - GIGAZINE
- CloudLinuxが「CentOS」の代替目指すプロジェクト「Lenix」--年間100万ドル超投資へ - ZDNet Japan
- CloudLinux、「CentOS」の代替OS「AlmaLinux」の一般提供を開始 - ZDNet Japan
- About/Product - CentOS Wiki
コメント欄
コメント欄の利用に関してはコメント欄の利用を参照して下さい。
| + | 上記の内容を守れる方のみご利用ください。 |
