『ブラウザ版』はこのWikiで扱う作品における「扱えない作品・ブラウザゲーム」に該当するため、評価対象版としては扱っておりません。
【かなばると】
【かなばると】
【かなばると くらしっく】
| ジャンル | エンドレスランナー |
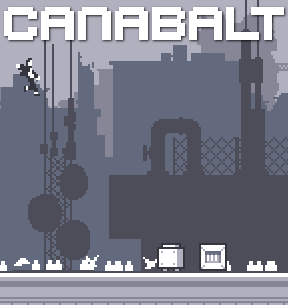
|
|
| 対応機種 | CS機 |
コモドール64 プレイステーション・ポータブル Ouya |
|
| 配信 | itch.io |
Windows Mac OS X Linux |
|
| メディア | C64 | ロムカセット | |
| PSP | PSP minis配信専用 | ||
| Ouya | 配信専用 | ||
| Classic | ダウンロード専売 | ||
| 発売元 | C64 | RGCD | |
| PSP | Beatshapers | ||
| Ouya | Kittehface Software | ||
| Classic | Finji | ||
| 開発元 | Adam Saltsman | ||
| 発売日 | C64 | 2012年1月10日 | |
| PSP | 2012年3月15日 | ||
| Ouya | 2013年3月19日 | ||
| Classic | 2024年2月8日 | ||
|
定価 (税10%込) |
Ouya | 無料 | |
| Classic | 無料 | ||
| プレイ人数 | 1人 | ||
| レーティング | ESRB:Everyone 10+(10歳以上) | ||
| 備考 | 日本語非対応 | ||
| 判定 | スルメゲー | ||
| ポイント |
モノトーンで統一されたグラフィック ビルの屋上をひたすら駆け抜けていく 操作はボタンひとつと非常にシンプル |
||
一般的にAdam Atomicの名で知られるAdam Saltsman氏の代表作として知られており、現在に至るまでFinji発足以前の代表作としても開発者のキャリアに対しての記念碑的存在として実績に名を刻んでいる。
元々は2009年8月31日に開発者本人のサイトにてフリーゲームとして公開されたタイトルであり、 その衝撃から各ゲームレビューサイトで「シンプルさとプレイヤースキルの求められる内容ゆえの高い中毒性を誇る」として高評価を叩き出し、氏の名を不動のものとさせ「エンドレスランナー」と言うジャンルを確立させた。その実績からニューヨーク近代美術館に展示され、The New Yorker誌からは「誰も本作が同様のゲームジャンルを普及させたことには反論しないだろう」とも語られることに。
ブラウザ版はAdobe Flashを用いて制作されたため、2020年12月31日のサポート終了により2021年1月12日以降プレイ不能の状態が続いていたが、2024年2月8日にHaxeFlixel(とOpenFL)を用いて復元された。併せてitch.ioでもダウンロード版が『Canabalt Classic』として無償配布された。
これらとは別になんと当時基準からして見てもビンテージパソコンとなって久しいコモドール64(1982年8月発売)向けの移植として『C64anabalt』が発売された。移植は現在でもコモドール64やAmigaなどのレトロ機種向けに新規のゲーム開発・移植を行っているRGCD社によるものである。
繰り返すが本作はFinjiの実質的な原点にあたるタイトルである。
開発元の現名義にあたる「Finji」は、北米ミシガン州グランドラピッズに拠点を置くインディーズゲームのパブリッシングをメインに活動している企業であり、Rebekah Saltsman氏がCEOを務める。
元々は2006年にAdam Saltsman氏とRebekah Saltsman氏夫妻によって設立されたゲームスタジオ「Last Chance Media, LLC」が起源であり、主にAdobe Flashを活用したゲーム制作やノキア製携帯電話向けのゲーム制作を手掛けていた。後の2014年に北米のゲーム会社と合併し、イタチと王冠のロゴのFinjiとして生まれ変わった。以後はインディーズゲームのパブリッシャーに専念することとなり、内製の新作タイトルもストラテジーゲーム『Overland』 がリリースされた2019年9月19日(北米時間)まで待つこととなる。
また、『iOS版』の発売元にあたる「Semi-Secret Software」は妻Rebekah Saltsman氏が財務とゲーム移植のパートナーシップを務めていたこともあるため、開発者と密接な関係である点も特筆すべき点である。
シンプルさと緊張感からの中毒性
ビジュアル面
ストーリー類は無し
実質難易度固定
曇天を思わせるグレースケールだけで表現された崩壊都市にそびえ立つ、今にも崩壊しそうなビルの上を未知の脅威から逃れるためにただひたすら駆け抜けていき、最終的な目標もまた、ゲームオーバーになるまでに走った距離だけをこれまたひたすら稼ぐだけ…と言う自己完結型に特化した非常にストイックな内容は、迫力ある音響と世界観に見合った暗くも疾走感溢れるBGM、なによりシンプルな操作性と高難易度なステージ構成も相まって中毒になるユーザーを世界中で輩出していった。
しかし同時に内容自体もスコアアタックだけに特化しきった内容であるため、ステージ進行がランダムとは言え「実質難易度固定ステージ1種類」だけも同然なボリューム不足ぶりがどうしても鼻についてしまうため、まさしくストイックな人向けのゲームと言える。
現在は当時の仕様のまま現代の環境でもプレーできるよう復元された『Canabalt Classic』が配信されているため、ボタンを押せばすぐにゲーム開始となるオールドスクールなアーケードスタイルのゲームを懐かしむ意味でも是非とも手に取ってみてはいかがだろうか。
【かなばると】
【かなばると えいちでぃー】
| ジャンル | エンドレスランナー |

|
|
| 対応機種 |
iOS 3以降 Android |
||
| 配信 | Steam |
Windows 10以降 Mac OS X 10.15以降 |
|
| メディア | 共通 | ダウンロード専売 | |
| 発売元 | iOS | Semi-Secret Software | |
| Android | Kittehface Software | ||
| Steam | Finji | ||
| 開発元 | Adam Saltsman | ||
| 発売日 | iOS | 2009年10月1日 | |
| Android | 2012年3月19日 | ||
| Steam | 2015年5月1日 | ||
|
定価 (税10%込) |
iOS | 370円 | |
| Android | 298円 | ||
| Steam | 298円 | ||
| プレイ人数 | 1〜2人 | ||
| 備考 | 日本語非対応 | ||
| 判定 | スルメゲー | ||
| ポイント |
独自要素追加版 なぜか冷遇されている『iOS版』 定価と不釣合いなボリューム 『Ver.2.0』である程度充実化 |
||
ブラウザ版公開開始から程なくしてiOS向けアプリとして配信開始、その後も間を置き「3D表示」機能を実装した『Android版』が配信開始、2014年には追加要素を提げた「Ver.2.0」アップデートが実施され、1年後には「Ver.2.0」をベースとした『Steam版』が配信開始された。
後述の経緯から、リニューアル後にリリースされた『Steam版』は当然としてそれ以前から既にリリース済みの『iOS版』『Android版』についても現在は全てFinji名義に統一されている。ただし基本情報欄には発売当時の方を記載する。
タイトル表記に曖昧な点が見受けられ、公式サイトで現在発売中として扱われている3機種分の版を全て『HD版』としているが、その中で唯一『iOS版』にはゲーム内も含めて「HD」表記が無い。
「3D表示」を除き、2014年にリリースされた「Ver.2.0」より追加された要素である。『Steam版』は全ての要素が配信開始当初より搭載されている。
BGM
3D表示(Android/Steam版)
2人同時プレー
追加ステージ
| + | 追加ステージ一覧 |
追加要素
定価に対して薄いボリューム
ブラウザ版の人気により早速iOSに移植されたことにより、はじめてブラウザ以外でプレーできる環境構築を実現。手軽にプレーできる内容からもスマホとの相性は抜群であり更なる人気を獲得するに至った。その後もAndroidへの移植でHD向けに3D表示機能を提げての配信となり、さらにアップデートで追加要素が、そしてSteamへの移植でついにパソコン上でもHDの魅力を余すことなく体験できるようになった。
しかし移植当初は『Flash版』と大差ない内容のままだったがゆえに(有料販売ゲームとしては)ボリューム不足ぶりがどうしても鼻についてしまう。事実、初の有料版である『iOS版』がリリースされる際も価格不相応である点はどうしても拭えなかったのか、2.99USDで発売された点でそれなりの批判が集まってしまった。2014年の「Ver.2.0」アップデートによる追加要素を加味しても根本的なゲーム内容故にボリューム不足を脱したとは言い難く、依然として人を選ぶことに変わりない。
幸い内容自体は全く変わらず劣化も見受けられないため、価格不相応も甚だしいことは別として、単体のゲームとして見れば面白さは依然として十分であることに変わり無い。それでも3Dグラフィック対応による面白さの差は歴然としているため、今から手に取るならば『Android版』『Steam版』がベストと言えるだろう。