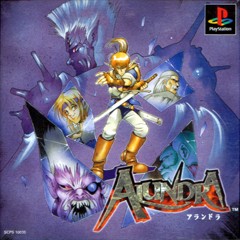アランドラ
【あらんどら】
|
ジャンル
|
アクションRPG
|
|
|
対応機種
|
プレイステーション
|
|
発売元
|
ソニー・コンピュータエンタテインメント
|
|
開発元
|
マトリックス
|
|
発売日
|
1997年4月11日
|
|
定価
|
5,800円(税別)
|
|
レーティング
|
CERO:A(全年齢対象) ※ゲームアーカイブスで付加
|
|
配信
|
ゲームアーカイブス:2007年10月10日/628円
|
|
判定
|
良作
|
|
ポイント
|
ジャンプのある2Dアクション
非常に重いストーリー
す、すげー、かっこいいぞーっ!
|
アランドラシリーズ
アランドラ / アランドラ2 魔進化の謎
|
|
PlayStation Studios作品
|
ストーリー
《神の御姿を描いた如何なる物――絵画、像の所有をここに禁ずることとする》
突然、国王より偶像崇拝を禁じる触れが出された。
神が人間のこの行為に立腹せぬ訳もなく、罰として愛すべき民は物を創り出す力、すなわち創造力を奪われてしまったのだった。
世界は荒み、加えて偶像を失ったことで果たして祈りが届いているのかと不安になる。
だが、神は人間を見捨てはしなかった。
人々は神より授かった、夢に干渉する力を使い、失いかけた生き甲斐を夢の中に求め始めた。
いつしか人間は夢を自在に操ることができるようになっていったのだった…。
「夢歩き」という特技を持つ一族がいる。
一般には「まどろみの一族」と呼ばれている。
彼らは眠っている者と波長を合わせ、その夢に入り込んで自由に歩き回ることができる。
一族の者は夢歩きの力が覚醒するとともに、己の宿命を悟り、世界を旅して回る。
己の夢に導かれるままに。
そしてここにも、夢に導かれて旅に出た少年がいる。
彼の名はアランドラ…。
その晩も、アランドラは夢を見た。
いつの頃からだろうか、眠りにつくと必ず見る。
「イノアの村の北方、湖の深き底に眠る悪魔が今まさに目覚めようとしておる。滅びようとしている世界を救えるのはそなただけだ」
守護者を名乗る老人が、必死に呼びかけてくる。自分は本当に世界を救う《解放者》なのだろうか?
心に湧き上がる疑問に終止符を打つべくアランドラは船に乗り、イノアの村へと向かった。
概要
ソニー・コンピュータエンタテインメントから発売された、『ゼルダの伝説』や『ランドストーカー ~皇帝の財宝~』に似た見下ろしタイプのアクションRPG。マトリックスの初開発作品でもある。
マトリックスは『ランドストーカー』のスタッフである大堀康祐氏が独立して立ち上げた会社であり、キャラクターデザインもランドストーカーと同じ玉木美孝氏であることや、アイテムやアクションの類似性から、謂わば後継作と言える。
世界観やシナリオのつながりはない。同タイプのゲームと比べると一見して理不尽にも見えるやり応えのある難易度が特徴である。
特徴
-
プレイヤーは主人公アランドラを操作して、イノアの村を拠点として村の周辺で起きる事件に巻き込まれたり、悪夢に悩まされる村人を助けたりと言った冒険を繰り広げていく。
-
□で攻撃、〇で装備したアイテムや魔法の使用、△でダッシュ、×でジャンプ。スタートボタンで所持品の確認や装備変更ができる。
-
また手前に持ち上げられる物が置いてあれば□で持ち上げたり持っている物を投げたりすることができる。人と会話するのも□ボタンを使う。
-
武器はリーチが短いが攻撃の出が早い剣、中距離に攻撃できるが大振りな鉄球、遠距離に攻撃できるが威力の低い弓の3種類。
-
攻撃の他にレバー状のスイッチを作動させることができる。また鉄球はブロックや氷柱などを壊すことができる。
-
このように操作自体はとても簡明でわかりやすい。これらのアクションとアイテムやギミックの組み合わせでダンジョンを攻略していく。
-
アランドラはイノアの村の鍛冶師アンゼスの家に居候させてもらっており、イベントが進むとアンゼスから新たな武器や攻略用のアイテムを作ってもらえるようになる。
-
村には道具屋や、次にどこに行けばいいのか教えてくれる占い師もいる。とあるアイテムを持っているなら村から少し離れたところにある酒場内のカジノで遊ぶこともできる。
評価点
歯ごたえのある謎解き&アクション
-
アクションや謎解きの難易度は非常に高い。最序盤こそ簡単なものが多いが、序盤の終わり頃から徐々に頭を使わないと解けない謎解きや操作テクニックを要求される場面が増えてくる。
-
ただスイッチを押すだけの謎解きでも、様々な物やアイテム、時には敵をも利用しなければならなかったりする。思いもよらないものの上に乗れたり、意外な物が壊せたり、大掛かりな仕掛けが用意されていると思ったらそれらはダミーで本当の謎の解き方は別にある、など謎解きの種類、解法ともに実に多様。
しかしダンジョン内をつぶさに観察し、アイテムやオブジェクトを上手く使ったり仕掛けに対してリアクションを行っていけば必ず打開できる。
そのため難解な謎解きや初見では絶対無理だろうと思われるような難所をクリアできた時の爽快感は正に格別。
-
ボリュームも豊富で、多種多様なダンジョンが揃っている。ダンジョン一つ辺りの広さもなかなかのもの。初見では謎解き・アクションに阻まれる事は確実。
-
クリアに必須ではないおまけ的なダンジョンや、フィールドマップ、村の中ですら謎解き要素が詰められており探索が本当に楽しい。
-
マップのあちこちに最大HPを上げる「命の器」や、集めるとレアアイテムと交換してもらえる「金のくちばし」、魔法の使用回数を増やす「マジックシード」が隠されており、探索すればするほどアランドラの強化につながっていく。
-
オープニングデモは単なるゲーム紹介ではなく、実は殆どが謎解きのヒントになっている。詰まったらリセットしてオープニングを眺めてみるのもこのゲームでは有効な手段である。
シンプルながらもよく考えられた戦闘バランス
-
難しいアクションや謎解きと比べると戦闘バランスはそこそこと言ったレベル。真正面から敵と戦うとややきついが、敵や状況に合わせて攻撃手段を変えることで楽に戦える。
-
例えばリザードマンを例に挙げると、「盾でガードしつつ剣で攻撃する近距離タイプ」「酸を吐き出し、プレイヤーとつかず離れずの距離を取りたがる中距離タイプ」「槍を遠くから投げてくる遠距離タイプ」の三種類がいる。
-
近距離タイプは弓などの遠距離攻撃で倒そうとすると殆どの攻撃をガードしてしまうが、攻撃の隙を狙って剣で戦うと楽に倒すことができる。
-
逆にあまりガードしないが距離をとりたがる中距離タイプや遠距離タイプに対しては弓や鉄球などで遠くから応戦すると戦い易い、といった具合。
-
また炸裂弾なら一撃で倒せることを利用して、ガードされる前提で弓で攻撃し、あらかじめ炸裂弾を置いてあるところへ敵を誘導させるといった戦い方もできる。
-
このように相手に対して有利な武器、不利な武器がボスを含めた大半の敵に設定されているため使えない攻撃手段が無い。
-
魔法は使用回数が少ない反面、効果はいずれも申し分なく、切り札として遜色のない価値がある。
プレイヤーのストレスを軽減する工夫と良好な操作性
-
操作性はとても快適。慣れればドット単位で思った通りの動きができる。一見理不尽なアクションを要求されるような場所でも、何度も何度も挑戦すれば必ずクリアできる。
-
アクションに失敗したからといって即ミスに繋がるような局面はない。せいぜい下の階層に落下したり少量のダメージを受ける程度。
-
アランドラのHPが多めなことや「必ずダンジョン内には回復ポイント(兼セーブポイント)がある」「適当に物を破壊していけば回復アイテムが出てくる」「それとは別に薬草などの回復アイテムを持ち歩ける」など回復手段が豊富なこともあってリカバリーが容易。
-
プレイ中のロード時間が短く、リトライのストレスは少なめ。
-
占い師を利用すれば次にどこにいけばストーリーが進むか判るため、進行に詰まることもない。
-
追加料金を払うと全体マップで直に目的地を指示してくれる親切ぶり。
-
ワールドマップが広く移動が大変だが、とあるイベントをクリアすることでフィールド各地点をワープで移動できるようになる。
-
ただ、その場所のヒントはないので気付かず進めてしまう可能性も。
-
最強の剣「雪王」は取得条件がやり込んだプレイヤーへのご褒美ではなく、戦闘に苦労しているプレイヤーへの救済要素となっており、難易度の軽減に一役買っている。
-
取り方さえ知っていれば中盤には入手可能。ボスを瞬殺できるなど、バランスが思いっきり壊れる。
-
尤も、順調なプレイ状況だと「お前ほどの剣士なら使うまでもなかろう」と言われて手に入らないので、最後まで入手できなかったプレイヤーも多い。
独特の世界観とシリアスなストーリー
-
人類は創造する術を失った代わりに夢に干渉できるようになった、という独特の設定を生かしたシナリオの完成度が高い。シナリオ担当はスタジオベントスタッフの手塚一郎氏。
-
主人公アランドラは「夢歩き」の能力を駆使して、人々の夢の中に入ってその中を攻略していく。その状況も人々を悪夢から解放したり、NPCの目的を探るためだったりと様々。
-
「夢と創造」「神殺し」をテーマにしたシナリオは極めてハード。
-
現実的に神を敵に回した場合の恐ろしさや行き過ぎた信仰の狂気が如実に表現されており、パッケージの見た目に反してドロドロとした残酷な展開が次々と待ち受けている。
-
その一方でこうした非情な現実に立ち向かう主人公を支えてくれる仲間たちの心強さや夢の持つ創造性と言ったプラスの面も描かれており、なかなかに考えさせられるストーリーとなっている。
聴き応えのある音楽
-
作曲家の田中公平氏によるBGMも優れている。
-
雰囲気作りがよく出来ており、それでいて謎解きの邪魔にならないダンジョン曲や、冒険心溢れるメインテーマなどが秀逸。
-
ダンジョンは不気味な曲が多いが、パズルメインのダンジョンでは集中力を掻き乱したりプレイヤーのストレスを余計に増やさないように穏やかな曲が流れるなど、プレイ内容に合わせた工夫や配慮が見られる。
-
田中氏自身がゲーム内でコーヘイという名前のキャラとして出演しており、彼に話しかけると進行に応じてゲーム中のBGMが聞ける。
-
エンディング主題歌「Tears」はストーリーの暗さに反して明るくアップテンポな歌であり、数々の悲劇を乗り越えたプレイヤーにカタルシスを与えてくれる。
賛否両論点
高すぎるアクション難易度
-
やり応え抜群と言う点では評価点でもあるのだが、この手のゲームに慣れていないプレイヤーが手を出すには酷な部分も多い。
-
序盤の終わり頃から難しいアクションが試される局面が徐々に出てくるようになり、終盤は本当にシビア。
-
「崖際から半歩はみ出したギリギリのタイミングで」ジャンプしてようやく届くような箇所を渡らなければならない足場が非常に多い。中にはそんな足場をいくつか連続して渡っていかなければならなかったり、足場自体が動いていたり、鉄球などの別のトラップが同時並行で襲ってきたり、時間制限がある状況で行わなければならなかったりするものも。
-
DUALSHOCKには対応しておらず、アナログスティックが使えないので十字キーのみで進めなければならない。柔軟な操作がしづらい事に加え、本作のシビアなアクションの数々は指への負担も大きいため、長時間のプレイは親指が痛くなること必至。
-
ボスも中盤までは(途中のアクションに比べれば)さほど苦労はしないが後半からは一気に強くなる。終盤にもなると攻撃力と耐久力が跳ね上がり、ちゃんとアイテムや装備で強化しないと軽く捻られてしまうようなボスがゴロゴロ居る。
若干の唐突さ
-
村には個性豊かな住人達が住まうのだが、顔見せや自己紹介がちゃんとストーリー上で行われるのは数人で、他の住人は村に来て最初の探索時に自発的に話しかけなければ行われない。次のイベントに進んでしまうとほぼ全員と既に顔見知りという扱いでストーリーが進むので、話しかけていないキャラがいた場合は混乱する。
-
それだけなら他の作品でも見受けられるのだが、そのストーリーを進めるイベントはある家に入ると警告も無しに強制的に発生するので、挨拶回りが不十分なままストーリーが進んでしまう可能性は十分ある。
-
特に本作はNPC達ががっつりストーリーに絡んでくるので、ちゃんと住人の特徴を掴んでおかないと感情移入しにくい。少なくとも序盤はNPCに積極的に話しかけた方が良い。
-
終盤、双子の夢を通り、敵である猿「ムルータ」達が村に現れて焼き打ちをするイベントがあるのだが…
-
黒幕の影響はあるにせよ、エルナの一族にしかできないはずの「他人の夢の中に入る」力を、ムルータ達が何の伏線も無く獲得してしまっている点は、やや唐突さが否めない。
ストーリーの重さ
-
ストーリー中に死亡するNPCがかなり多い。
-
とにかく死人が多く出る。最終的には墓場にずらりと墓標が並ぶ。エンディングでもその大量の墓にアランドラが手を合わせるシーンがあるほど。
-
教会横の墓地は当初は更地も同然なのだが、墓を立てる為のスペースがいくつも用意されている。つまりそれを埋め尽くすほどの死者が出るという事である。
-
「死にかけているNPCを助けようとしたが間に合わなかった」「あるNPCを救出している間に別のNPCが死亡してしまった」「主人公の活躍で一旦は命を取り留めたNPCが後日別のイベントであっけなく死んでしまう」など、やりきれない展開も多い。
-
魔物に殺されるのはもちろん、一部の人間がアランドラを殺そうとしてきたり、別の人間を殺すケースもある。
-
挙句がストーリー終盤の、上述した「焼き討ち」である。幾つもの悲劇を乗り越え、村人の救出に成功したり住人達の意思がまとまりつつあった中で、それをドン底に叩き落す惨劇が待ち受けている。
|
+
|
あまりにも無情な展開(ネタバレ)
|
-
このイベントではそれまで普通に話していた村人が死体となって転がっていたり、後から死を知らされたりと、一気に死者が増える。
-
何よりその犠牲者のうち3人はアランドラが悪夢からの救出に成功し、且つ無事に回復した村人である。これにより、アランドラが悪夢を払うべく務めた村人は誰一人生き残らなかったことになる。
|
-
勿論、その後のイベントでフォローされているため彼らは完全に無駄死にと言うわけではなく、献花や弔いのイベント、墓標一つ一つに刻まれた追悼の言葉と言った表現もあるので命を軽々しく扱っているわけではない。しかし必然的に作中の雰囲気は重い。
-
その一方、この墓石を踏み台にしないと進めないという、死者を冒涜するようなシーンが一度だけある。
本当に悼んでたのか主人公よ。
-
また村にアランドラが来てから死人が立て続けに増えたこともあって、一部の村人から疫病神扱いされたりもする。それ以外の大半の村人は逆にアランドラを庇ったり気遣うが、それらの人々もやがて災難へと巻き込まれていく。
その一方でたまに挿入されるギャグ要素
-
シリアスな場面が多く印象に残るゲームであるが、「人の頭を踏み台にする」「敵がマヌケにもアランドラの手助けをしてしまう」など、シュールで笑える場面もあったりする。
-
しかも前者の相手はヒロインである。数あるゲームの中でも、ヒロインの頭を足蹴にしなければならないゲームなどそうそう無いだろう。
-
しかし、そうしなければならないシーンは数回あるのだが、ヒロインの反応はそのたび「もう…人の頭に乗るなんて」「これで何度目よ?」などと、実に冷静に返される。そのヒロインも主人公の頭を足場にするシーンもあるので、最早そういう世界と捉えるべきか。
-
敵であるムルータ達も後者に当てはまり、ストーリー中では腸が煮えくりかえるような暴虐すら働く一方で、こういったイベントではただのマヌケなコメディリリーフになっていたりする。
-
あまりにも重いストーリーに疲れたプレイヤーの心の清涼剤になる半面、雰囲気が壊されると言う意見もある。メインストーリーそのものは極めてシリアスな分、尚更そう思えてしまう。
-
かといってこういう要素が全く無かったらストーリーの陰惨さのあまりプレイヤーの精神が摩耗し続け、心が折れてしまいかねない。これはもう割り切りが必要だろう。
-
終盤である人物がボスになるのだが、その変身後の台詞が「す、すげー、かっこいいぞーっ!」。
-
そのキャラとは正反対の台詞回し(豹変しているのだからそれまでのキャラもクソも無いので正しいと言えば正しい…方向性が明後日を向いてはいるが)、それまでの緊張感を一言で吹っ飛ばすシュールさ等から一部で人気があり語り草になっている。
-
ネタとしてのポテンシャルは高いのだが、いかんせんゲームの知名度がそれ程でもないので埋もれたネタになってしまっている。
-
一応、そのボスの名誉のために書いておくと、全ボス中でも一、二を争うほどの強敵である。
-
彼以外にも、性格が豹変して信じられないような汚い言葉を吐いたり、威勢が良かったのが急に弱気になったりするボスもいる。
エンディングの演出
|
+
|
ネタバレ
|
-
本編中にムービーは無いのだが、エンディングのみ2Dアニメが流れる。ラスボスを倒し、崩れるラストダンジョンを脱出すると唐突にアニメが流れ出し、それが終わるとそのままスタッフロールに移る。
-
内容は冒険を終えた後の様子を描きながら、唐突に場面転換が入りそれまでのゲームの流れをアニメVerで一通り振り返ると言う演出が連続で続き、アランドラの新たな旅立ちを描いて終わる。
-
エンディングを丸々フルアニメーションで表現するという豪華な作りなのだが、初見では少々理解が難しい内容であり、感慨深いと取るか、置いてきぼりにされると取るかは意見が分かれそうな所。
-
キャラボイスのほぼ無い作品なのでこのアニメも台詞が無く、テキストも一切表示されないので、見れば分かる通常の場面ならともかく前述したような唐突な場面転換の数々は初見では少々理解が追い付かない。
-
村人たちがアランドラを称えて祝杯を上げたと思ったら、急にモンスターとの戦闘が始まり、かと思ったら村を復興している場面に移り、と思ったらまた激しい戦いを繰り広げたり…と、とにかく忙しない。初めて観た人は平和が戻ったのか戻っていないのか混乱するだろう。ちゃんと理解出来れば、冒険の思い出と後日談の両方を交互に味わえる粋な演出なのだが。
-
ちなみにこの回想部分ではラスボスにとどめを刺すシーンもあるのだが、実際はラストダンジョンの神殿で倒した一方でアニメだと何故か洞窟になっている。
-
このアニメではアランドラがヒロインのメディアムと共に旅立ち、その後の旅の様子も描かれるのだが、ラストシーンではメディアムとの別れが待っている。一緒に旅をしてきたメディアムだが、道を違える時が来たらしく、アランドラと口付けを交わして去って行く。そして1人で歩き出すアランドラの後ろ姿で物語は終わる。
-
ヒロインとの別れという幕切れ自体好みが分かれそうだが、更にアランドラが向かう先が暗雲立ち込める不吉な雰囲気に包まれているのもやや後味が悪い。その暗雲を晴らすために立ち向かって行った、と言う見方もできるが…。
|
問題点
入手できる期間が限定されているアイテムが多い
-
住人の夢の中を舞台にしたダンジョンはクリアしてしまうと再度入ることはできないため、そこにあるアイテムは当然入手できなくなる。また現実のダンジョンもクリア後に入れなくなるものが多い。
-
シチュエーションとしては自然なのだが、中には「敵を全滅させると重要アイテムが入った宝箱が出現するが、その数秒後に強制的に夢から脱出させられてしまう」なんてものまであるため、初見では完全に罠である。
-
カジノに入場可能なアイテムは隠しアイテム扱いなのだが、ある時期を過ぎると入手不可になる。当然、カジノにも入れなくなる。
-
コンプリートの為にはカジノも攻略しなければならず、しかも金のくちばしをアイテムと交換するための情報はカジノに入らないと得られないので、取り逃すとこちらも利用不可に。
ダンジョン攻略上の不親切さ
-
見下ろしタイプであるため高低差と奥行きの違いがとても分かり辛い。
-
一見飛び越せそうに見えて進めない場所や飛び越せなさそうに見えて進める場所などもあり、アクションで詰まる要因にもなり得る。
-
固定視点であるため背景に隠れて見えず分かり辛い場所もある。
-
ただしこの点を利用した謎解きもあるため、問題点と言うよりは仕様の趣が強い。
-
ゲーム進行へのヒントは親切な反面、謎解きに関わるヒントが少ない。
-
周りを観察することで察しなければならない物が多いため、物によっては思いつきで試して気づくしかないような解決法もある。
-
「そんなのでいいの!?」と思わず突っ込みたくなるような無茶な方法が正解だったり、どこに仕掛けがあるかと悩んでいたら実は仕掛けなど無く敵を全滅させればOKだったりと、発想にも柔軟性が求められる。
-
パズルそのものの巧妙さではなく、細かな調整の不足による難易度の上昇。
-
ステージの構成などを見ると、意図したと言うよりもテストが足りていないと思しき箇所がちらほら存在する。
-
少し話は変わるが、ゲーム全体を通して難易度の上下幅が激しい。そんなに進んでいないのに難易度が急上昇したり、後半で高難度が続くと思ったらパズルとも呼べないようなぬるいギミックが出てきたりとチグハグさがある。こういうところからも調整不足の感が見えてくる。
その他
-
カジノの攻略がほぼ運頼み
-
カジノでは3つのミニゲームがプレイ可能で、射的、スライム叩きは腕前次第でクリア可能なのだが、ルーレットは運の要素が強い。
-
赤、青、緑のどのランプに止まるかを賭けるのだが、完全クリアにはこれを5連続で当てるという事を4回も達成しなければならない。
-
しかもランプの中には無条件でハズレになる黒のランプもあるので、ここに止まってしまったらどうにもならない。あと一歩という時に黒に止まろうものなら…。
-
実は止まる個所には簡単な法則があるので、それに気付けば当たる確率を上げることができる。それでも確実に当たるわけではないし、黒に止まったらどうしようもないのだが。
-
クリアに必須ではないので無理に挑む必要はないのだが、各ミニゲーム完全クリアの賞品が金のくちばしであるため、コンプリートを目指すならこのギャンブル地獄は避けて通れない。
-
魔法が使い辛い
-
最大MPはマジックシードを全部集めてもたったの4。MP回復の手段も限られるので、なかなか使う場面を見極めるのが難しい。
-
魔法の種類は「大地」「水魔」「火竜」「風神」の四つがあるが、水魔のみ体力回復&バリアを張る、それ以外は全部周囲の敵に攻撃する魔法となっている。
-
攻撃魔法には属性があるが、敵の弱点が見た目では分かり難いので、どれを使えばいいのか分からない事が殆ど。
-
魔法は発動した瞬間にしばらく無敵になる。ザコ敵に囲まれたときはわざと引き寄せて攻撃魔法を使って一掃すると楽だが、あまりそう言う場面に遭遇することが無い。あったとしても出し惜しみをして結局武器で戦い、MPは体力回復のために取っておくと言う展開になりがちである。
-
セーブデータのタイトルの変更タイミングが早い。
-
物語の進行具合に沿ってセーブデータにタイトルが付けられるのだが、一区切りつけた次のシナリオが始まる直前でセーブすると、次のシナリオの開始時点のタイトルが付いてしまう。
-
まだ聞いた事もない場所へ向かうようなタイトルが付いていたり、人の死亡をネタバレされたりすることもある。
-
セーブ完了後はすぐにウインドウが閉じるため、そのまま進行する分には問題ないのだが、ゲームを終了して再開する時にはこの現象に遭遇する可能性がある。
総評
ゼルダタイプのゲームとしてはかなりの高難度ながら、リトライの容易さや操作性の良さ、クオリティの高い音楽やシナリオ、独特の世界観などから未だに評価の高いゲーム。
アクションゲーム初心者に勧められる代物ではないが、見下ろし型2Dアクションが好きでなおかつ腕に覚えのあるプレイヤーならば間違いなくお勧めできる名作である。
余談
-
後にシリーズ2作目として『アランドラ2 魔進化の謎』が発売された。
-
監督の大堀氏を始めとするメインスタッフや音楽の田中氏は続投しているが、シナリオは宮岡寛氏、キャラデザインは今井修司氏に交代しており、作風やビジュアルの時点で別物と言っても良い程に様変わりしている。難易度も大幅に下がり、謎解きにはヒントが多数用意されたりと本作とは打って変わって親切設計になった。
-
キャラも総入れ替え、完全3Dのグラフィックやギャグを中心にした明るい物語、そもそもアランドラ本人どころか名前すら一切関わらないなど、同じゼルダタイプのARPGである事くらいしか共通点はない。夢世界の要素も無くなり、純粋な冒険活劇になっている。どちらかと言うと『ランドストーカー』寄りの雰囲気である。
-
オープニングがヒロインが歌唱するミュージカル調だったり、タイムボカンシリーズの三悪のようなライバルキャラが居る時点で作風の違いがよく判るだろう。
-
その為、『1』のファンからの評価は低めだが、豪華声優陣によるキャラボイス、豊富なミニゲームなどの独自の魅力を持っている為、別物と捉えて高く評価する声もある。
-
「アランドラ」の名は冠してはいないが、同社の『デュアルハーツ』には「街の住民達の夢を冒険するゼルダタイプのARPG」と言う作風が受け継がれている。2Dゼルダ風のアランドラシリーズに対し、こちらは3Dゼルダ風である。
-
前述の通り謎解きのヒント満載のOPであるが、実は本作のほぼ全てのボスとの戦闘シーンまで見られる大盤振る舞いだったりする。そのため、ネタバレOPと言われることも。
最終更新:2024年11月18日 06:17