【すとりーとふぁいたーぜろすりー】
| ジャンル | 対戦型格闘ゲーム | 高解像度で見る | 高解像度で見る 裏を見る |
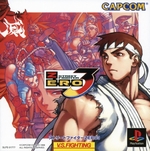 |
| 対応機種 | アーケード(CPシステムII) | |||
| 販売・開発元 | カプコン | |||
| 稼動開始日 | 1998年7月 | |||
| 判定 | 良作 | |||
| ポイント |
ZEROシリーズの集大成 豊富なキャラクター ガチ対戦のバランスは良くない |
|||
| ストリートファイターシリーズリンク | ||||
『ストZERO』シリーズ3作目。『ZERO』『ZERO2』の要素を引き継ぎつつも、様々な要素が追加されてかなりの大ボリュームに。
| + | 登場キャラクター一覧 |
純粋に増えたキャラクター数によるバラエティに加え、従来のストリートファイターの駆け引きに加えた新たな要素が功を奏し、より面白い対戦ゲームとなっている。
発展しすぎたオリジナルコンボ、バグや永久コンボの存在などで極まったガチ対戦環境においては賛否の分かれる要素もあるが、手軽に格ゲーに触りたい初心者にも、とことん極めたい上級者にもオススメできる格ゲータイトルの一つ。
無印『ZERO3』単体としてはプレイステーション(PS)・ドリームキャスト(DC)・セガサターン(SS)に移植。これらはいずれも共通して家庭用独自の追加要素がある。
また、以下のコレクション作品にアーケード版準拠で移植されている。
【すとりーとふぁいたーぜろすりーあっぱー】
基板をNAOMIに変更し、コンシューマー版『ZERO3』の新キャラクターと追加要素を加え、更にDC版のワールドツアーモードで育成したキャラクターも使用できるようになったバージョンアップ版。
追加キャラクター
ゲームバランス調整
DC版との連動
強力なボスが使用可能
操作遅延
家庭用の追加要素反映や、DC版との連動を加えた完全版という触れ込みであり、その点では光る物がある。
しかし、アーケード向け作品としては操作遅延やボス使用可能などにより、無印よりも短命に終わってしまった作品となった。
こちらも複数の機種へ移植された。
*1 飯風呂寝る→MESSY. FULL ON NAIL!→多くは語らねえ!とゲーム内で訳される。ただし勝利メッセージ以外では英語まじりの片言の日本語で普通に喋っている。
*2 本人が権力の象徴と勘違いした
*3 初出の『スパIIX』では耐久力は標準だったが、そのせいで反則的な性能を誇った事から『ZERO』以降は意図的に耐久力が下げられているものと思われる。しかし本作のみ耐久力がやや改善されている。
*4 判定がある程度強い上にダメージが非常に高く、カウンターヒットすると通常技とは思えないほどの減りを見せる。さらにボディプレスを落とせる通常技対空に相性が良い傾向があるジャンプ↓中Kも持っているため、この2種を使い分けるだけでも相当厄介。
*5 一応「キャミィ」だからネームタグを「CAMM」にしよう→「CAMM」って書いてあったから名前を「キャミィ」にしよう、という流れでも矛盾はないが。
*6 コーディーを選択すると、ステージに必ず落ちている。なお同キャラ対戦でも1本しか落ちていない。
*7 厳密には縦幅は全画面を網羅しているものの横幅はベガ自身のグラフィックと同じで、高速で前進するため全画面を網羅しているように見える。
*8 本作の投げは出るまでに時間がかかるものが多く、投げスカりモーションもそれなりに隙が大きい。
*9 一応、最低限のガードクラッシュ下限値は設定されている。
*10 確かに原作のEDでは「おれはふつうにはいきられないおとこだ」と発言していたが…
*11 登場するのは『ストリートファイターV アーケードエディション』から
*12 正確にはX=VでZのみ低い。
*13 Zは1/3消費、Vは1/2消費
*14 これは明確な調整ミスであり、開発陣もこの問題を認識していたのか「ザンギエフは攻撃で与える気絶値が一部技を除いて0」という設定が行われている。
*15 このため変化させるには、先端当てや起き上がりに重ねるなどしてヒットを遅らせる必要がある。
*16 同じセガハードのDCより前世代のSS版の方が後発であった。
*17 一応残り容量を4GB以下にすればセーブデータを作成できるので、以後は4GB以上に増えても問題ないという抜け道はある。