この項目では『レインボーアイランド』・ファミリーコンピュータ移植版『レインボーアイランド(FC)』を取り扱っています。
判定はいずれも
良作
です。
【れいんぼーあいらんど】
| ジャンル | アクション | 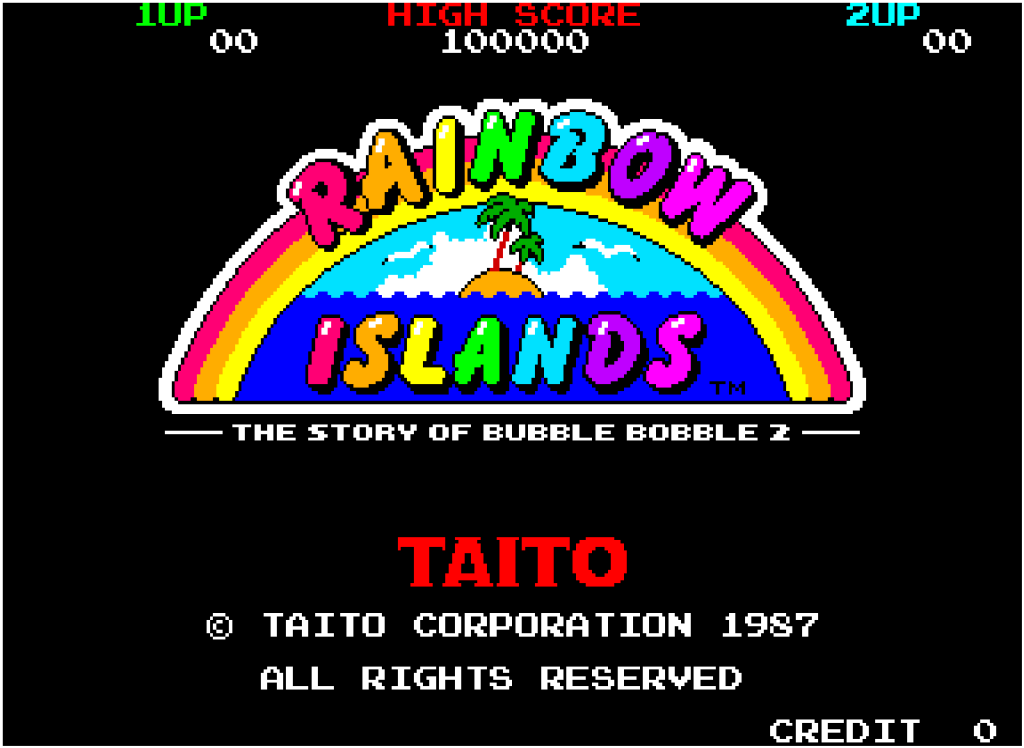 |
| 対応機種 | アーケード | |
| 発売・開発元 | タイトー | |
| 稼働開始日 | 1987年10月 | |
| プレイ人数 | 1人 | |
| 判定 | 良作 | |
| ポイント |
バブルドラゴンは人間に戻って泡は虹になってよりコミカルに 見た目だけでなく効果も多彩なアイテムの数々 難易度バランスはより親しみやすいものに |
|
| バブルボブル・パズルボブルシリーズ | ||
1987年にアーケードに導入されたタイトーのアクションゲーム。
サブタイトルに「THE STORY OF BUBBLE BOBBLE 2」とあるように『バブルボブル』の続編にあたる。
とはいえ前作でドラゴンだったバビーとボビーが人間になったということで設定を引き継いでいるものの、ゲームそのものは別物となっている。
『バブルボブル』のラストから続く………
両親と無事再会し人間に戻ったバビーとボビーは虹の魔法が使えるまでに成長していた。
ある日、7つの海を渡ってきた船乗りから、遠い南の島「レインボーアイランド」にある、どんな願いもかなえてくれる秘宝「ダイヤモンドロッド」の話を聞いて早速旅に出た。
長い航海の果てに島にはたどり着いたものの、たった1人の少女を残して誰もいない。彼女の話によると、自然体が暗黒大魔王に支配され人々はみなとらわれてしまった。
2人は勇気を出して島の探検に乗り出した。
ゲームシステム
ステージ構成
| + | 詳細 |
パワーアップアイテム
| + | 詳細 |
「THE STORY OF BUBBLE BOBBLE 2」というサブタイトルに反して実質まったく別のゲームではあるもののコミカルでかわいらしい世界観は引き継いで更にそのクオリティはいっそう高まっている。
『ダライアス』や『ARKANOID』といった看板作とのコラボも、元々のイメージを壊さずそこに本作独自の雰囲気も見事に溶け込んでおり開発陣のセンスが光っている。
主な攻撃手段となる虹の魔法は攻撃、防御、移動手段と万能で、初見ではバランスブレイカーなほどに感じるがプレイヤーのテクニックと融合することで真価を発揮するものであり単純に見えて奥深い。
難易度も序盤はゆっくり慣れていけるバランスになっており良質なアクションゲームという点では前作以上のものとなった。
【れいんぼーあいらんど】
| ジャンル | アクション | 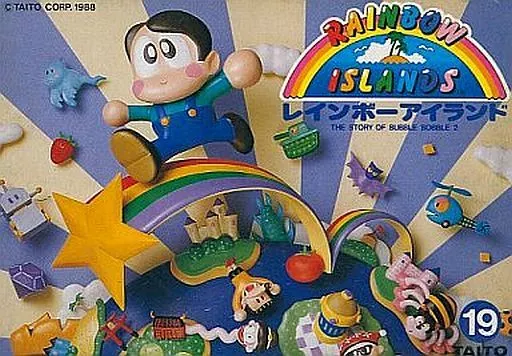 |
| 対応機種 | ファミリーコンピュータ | |
| メディア | 1MbitROMカートリッジ | |
| 発売元 | タイトー | |
| 開発元 | ディスコ | |
| 発売日 | 1988年7月26日 | |
| 定価 | 5,500円(税別) | |
| プレイ人数 | 1人 | |
| 判定 | 良作 | |
| ポイント |
新たに『奇々怪界』ともコラボ ストーリーパートの追加 多少簡略化はあるもののコミカルなかわいらしさは健在 |
|
| バブルボブル・パズルボブルシリーズ | ||
1988年7月にタイトーからファミリーコンピュータ用ロムカセットソフトとして発売された上記作の移植版。
全体的に簡略化され、一部アレンジが加えられている。
ステージや一部仕様の削減はあるものの全体的には、そこまで極端な劣化を感じられるほどではなくファミコンのスペックを考えれば、きれいにまとまっている範疇。
特にグラフィックに感じては元々コミカルでかわいい路線であるためそこまで格下ハードによる悪影響が出にくいことも手伝って、その持ち味が殺されておらずBGMに関してもファミコン向けに上手くアレンジがなされている。
また「奇々怪界アイランド」の和を前面に押し出した雰囲気は本作ならではでありこれもオリジナル版同様、大元のイメージと本作の世界観が見事にマッチングしている。
当時は野球やRPG全盛期ということもあってアクションゲームは少々不遇な時代ではあったものの、そんな中で充分存在感を放っていたのも納得な内容。