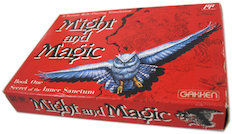「判定不一致修正依頼」にて判定と記事内容の不一致が指摘されています。対応できる方はご協力をお願いします。
Might and Magic
【まいとあんどまじっく】
|
ジャンル
|
ロールプレイングゲーム
|
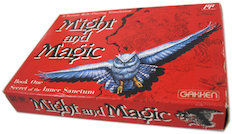
|
|
対応機種
|
ファミリーコンピュータ
|
|
メディア
|
4Mbit+64kRAMROMカートリッジ
|
|
発売元
|
学習研究社
|
|
発売日
|
1990年7月31日
|
|
定価
|
8,500円(税別)
|
|
判定
|
ゲームバランスが不安定
|
|
劣化ゲー
|
|
賛否両論
|
概要
当時のRPGとしては膨大なボリューム、ダンジョンはおろかフィールドまで全て3D表示されたグラフィック、プレイヤーによってシナリオ進行が変化する「小クエスト並立制」などがM&Mの特徴である。
本作はそのシリーズ1作目『Secret of The Inner Sanctum』のFC移植版である。
-
発売元はまさかの「学研」。そのため、児童学習誌『○年の科学』『○年の学習』などで大々的な宣伝がなされ、多くの小学生が
騙されて購入した。
元々高難易度で人を選ぶPCゲームをライトユーザー中心のFCに移植し、そして子供向けの学習雑誌で宣伝するというハチャメチャな販売方法は、当時の人々に強烈なインパクトを残した。これに限らず当時の学研は、自身が提供元である映画等を提供元であることをほとんど伏せたまま『科学』や『学習』で宣伝しまくるという行為で被害者を量産していた(例・クライシス2050)。
-
ただし「学研といえば学習マンガ」というイメージに騙されがちだが、ファミコン登場前には『パックモンスター』等の
パクリLSIゲームを発売していたり、三大アニメ雑誌の一角である『アニメディア』を出版していたりと、学研は昔からこの方面にも力を入れている会社である。
問題点
しかし、多少アレンジしつつもゲームシステム、バランスはオリジナル版に近い形で移植してしまったため、ファミコンのメインターゲットである小・中学生がサジを投げる事態が続出してしまった。
厳し過ぎるゲームバランス
-
導入部分が非常に不親切
-
ゲームを開始すると、突然広い世界に一人、無一文でいきなり放り出される。その後はどこに行って、何をするかは全て自分自身で判断しなければならない。
-
探索を進めることでゲームの目的ははっきりしてくるのだが、後述するゲームバランスの厳しさも相まって、ゲームを途中、ヘタをしたら序盤で投げる人が非常に多かった。
-
ゲーム開始直後の戦闘バランスが異常
-
町なのに平気で敵が出てくる。宿屋や教会の中でも敵が出たりする。ゲームスタート地点である「ソーピガルの町」でも例外ではない。
-
低レベル帯では敵に物理攻撃がほとんど当たらず、当たれば御の字というレベル。命中率が気持ち高い魔法でちまちまと削るしかない。町の中で経験を積み、平均レベル8位になったらようやく外を安心して旅することができる。
-
しかし簡単にレベル8~と言うが、序盤はキャラの成長が遅いので、コツをつかんだ人で1週間、RPGに不慣れな人だとさらに時間がかかる。果たしてそこまでプレイヤーが耐えられるかどうか。
-
敵の同時出現数が多く、最大15匹まで出現する。
-
幸いエンカウント率は低く、戦闘前の逃走も高確率で成功する。ただし、その場合はエリア内の特定ポイント(ダンジョンの入り口など)に強制的に戻されてしまう。また、戦闘中の「にげる」コマンドは、ほぼ100%の確率で失敗してしまう(なら入れるなよ…)。
-
アイテムの詳細データを確認することができない
-
ステータス画面で視認できる効果は、防御力と特性値上昇量くらいで、あとは「自分で試せ、使って覚えろ」という仕様。当時のRPGではこれが当たり前であったのだが、さすがにアイテム総数が数百に達すると解析の手間は計り知れないものになる。
-
レベルアップの効果が微妙
-
レベルアップで上昇するのは最大HPとMP、物理攻撃のヒット数だけで、「力」や「素早さ」といった特性値はレベルアップでは全く上昇しない。特性値を上げるには各地に点在する泉を使用する必要があるのだが、これはクエスト扱いであり序盤では全く説明されない。
-
また、単に経験値を稼ぐだけではなく、必要な経験値を貯め終わった後、町の訓練所に行って「有料で」訓練を受ける必要がある。ただでさえ戦闘バランスが厳しいのに出費はかさむ一方である。
-
探検は常に死と隣り合わせ
-
別の町にテレポートするポイントが存在する。上手く使えば便利なのだが、序盤で利用してしまうと帰りで苦労することも…。
-
特に序盤で「ダスクの町」に飛んでしまうと、ソーピガルの町に戻るのに大変難儀する。ヘタするとクリア以上の苦労(と達成感)を味わえるかもしれない。
-
ダンジョンには危険な罠が多数存在しており、ゲーム序盤から即死、全滅になる罠が続出する。全滅したらセーブしたところからやり直し。対策は「引っ掛かって覚えろ」。
-
やっとの思いで敵に勝利し宝箱を入手しても、盗賊が罠解除を結構な確率で失敗する。運が悪ければ全滅もありうる。
-
フィールド、ダンジョンでは休息が可能なのだが、休息中に突然モンスターに奇襲されることも。
-
手動マッピング・手動メモが必須
-
このゲームにはオートマッピング機能や受注中のクエスト情報・重要情報を記録するオートメモ機能などはない。しかしマッピングしなければクリアできないダンジョンがあり、広大なフィールドのあちこちで断片的に得られる重要情報を手動でメモしそれを纏めて解読しなければ突破できない仕掛けが存在する。
-
ちなみに攻略本でも答えは載っておらず、自分で書き込んでいく形になっていた。
要するに、全てにおいてテーブルトークRPG風味(もしくは『Wizardry』的なゲームバランス)なのである。
しかし、そのことは説明書で一切解説されておらず、ドラクエから入った子供達にとってはハードルがあまりにも高すぎた。
謎仕様、バグ&不具合
-
戦闘時の行動順は「プレイヤー側全員が先に行動→敵の行動」となっているため、素早さの価値がほぼなくなってしまった。
-
鍵などのアイテムは先頭のキャラが持っていないと効力を発揮しない。だが先頭のキャラは最も敵から狙われやすく、敵に盗まれたり「世捨て人と持ち物を全て交換する」というイベントもあるため、常に気を付けていないといけない。
-
戦闘後だけでなく、イベント後でも「さがす」コマンドで調べないとアイテムが手に入らない。そのため、モンスター退治のクエストなどでは「敵を倒す→「さがす」コマンドで敵からのドロップアイテムを入手→方向転換→もう一度「さがす」コマンドを行い、イベントアイテムを入手」という極めて歪な行動を取らなければならない。
-
通常のゲームでは絶対に考えられないシステムであり、結果重要アイテムの取り逃しが頻発する。しかも一度その場を離れればイベントアイテムの入手フラグが消失してしまう。
-
序盤の冒険「兄弟のクエスト」は、最後に犬の石像を壊すことで重要アイテムと大量の経験値が手に入るのだが、その石像は何度でも壊すことができる。ということは、それを利用して無限に経験値を稼ぐことも可能なのだが、レベルアップには経験値だけでなくお金も必要。
-
で、そのお金に関してはこれまた序盤のうちから会える世捨て人とのアイテム交換で、海賊の地図を貰う→隊列を換える→また地図を貰う→隊列を(以下略)する事で地図を最大5枚まで入手でき(この際重要なアイテムを持ってるキャラにまで交換させないように注意しなければいけないので、6人PTだけど最大5枚までとなる)、それを売り捌いて稼ぐ事ができる。しかも何回でも繰り返せるので上記のバグと併せて事実上の無限レベルアップが可能となる。もっともある程度レベルを上げたら普通に冒険した方が率は良くなるのだが。
-
ダンジョン「アストラル・ゲート」では、クリアするために「ダンジョン内で得たパスワードをある装置に入力する」事が求められるのだが、アルファベットで示される答えをカタカナに直して入力しないといけないため間違えやすい。PC版だとどちらでもよかったのだが。
-
戦闘時はAUTO戦闘を選択することで高速スキップできるようになるのだが、AUTO戦闘を解除する方法が説明書にも載っていない(ちなみに「Bボタン押しっぱなし」で解除)。
-
ブラックリッジサウス城の王様「ロード・ハッカー」は全ての依頼をこなした後でもう一度会うと、「全員の荷物を没収した上に遠くにすっ飛ばす」というメチャクチャな事をやってくる。さらにもう一度会うと何食わぬ顔をして前にクリアした依頼をもう一度最初から出してくる。他の王も依頼がループするのは同じだが、こんなひどい真似はしてこない。
-
チート魔法「テレポート」「つうか」の存在。
-
「テレポート」はエリア内の任意の場所に飛ぶことができる。「つうか」はバリアーや壁を通過することができる。つまり、これらの魔法を駆使すればダンジョンの仕掛けや謎解きをすっ飛ばして一気に進行できる。
ただし、ゲームの難易度自体がチート級であるし、ラストダンジョンではちゃんと対策が取られている点も考えると、開発者の想定バランス内だと思われる。
-
バグ・不具合が非常に多い。以下、その一部を挙げる。
-
GEM(高位魔法を使用する際に消費する宝石)はストック数が256個に達すると0に戻ってしまう。
-
キャラのレベルを86に上げると内部的にはレベル1に戻ってしまう。結果、物理攻撃のヒット数が激減し、攻撃力が大幅に下がる。これはレベルをさらに上げることで解消可能(ただし上げ過ぎるとまたループする)。
-
「おおたて+2」と「ゴクリのおおたて(呪いの品)」の性能が逆になっている。
-
各地の王から「いくつかのアイテムを集めてきてほしい」というクエストを受注できるのだが、要求されるアイテムを王に渡してもなぜか手元から無くならない。
-
特性値アップの泉のうち、知性の泉だけは一度しか使えない。他の泉は条件を満たせば何度でも使えるし、PC版では全ての泉を何度でも使える。
-
武器のうち、弓系統は店売りの物しか入手できない。(敵からのドロップで手に入るはずの)強力な弓はデータ上には存在する。
-
教会に寄付をすると時々おまけでキャラを強化してくれるのだが、同時に敵が異常なパワーアップを遂げてしまう。そのため意味がないどころか寄付厳禁となってしまっている。
-
レリーフに書かれている「コリンブルッフ洞穴の位置情報」が間違っている。
-
海は本来僧侶レベル3の魔法「うきしま」を使って浮遊して歩くのが前提となっているのだが、Bボタンを押して一歩前へ進む「突進」では普通に進めるため、「うきしま」の魔法が死に魔法となっている。
-
前述のアストラル・ゲートは「クリアしないと絶対に脱出できない」という設定なのだが、FC版では僧侶魔法の「まちへ」を使うと脱出できてしまう。ただしクリア扱いにはならないので、ハマリ防止のために意図的に入れた仕様とも考えられる。
PC版からの改悪点
元となったPC版からはかなりの変更がなされており、改良された部分もあれば人によっては改悪と思われてしまう部分もある。
改良点については後述。
-
序盤が高難易度化している。PC版の序盤も簡単とは言えないが、FC版では罠の解除率、敵とのエンカウントの量の変更等が響いたせいで、より難しくなってしまっている。
-
前述の「さがす」コマンドでなければ見つからないイベントアイテムや、マップ上に固定で配置されたアイテム(「ぎんのかぎ」など)は、PC版ではおなじマスに入るだけでおおむね自動的に発見される。
-
壁のグラフィックの種類が若干減っており、その影響で一部の通り道や隠し通路が分かりにくくなっている。
-
通れる森と通れない森が同一のグラフィックだったり、氷河、城の色違いの壁などが普通の山、壁と同じだったりしている。
-
メッセージの簡素化。洋ゲーにありがちな叙述的表現がなくなり、全体的に説明不足。
-
例えば、とあるイベントにて「死体から影が立ち昇り…」という文章が削られたせいで、倒したはずの敵が急に話し始めたように思えてしまう。
-
ストーリーの簡略化。M&M特有のSF設定は総カット。それに関するメッセージも全廃止し、単純明快なヒロイックファンタジーとして再構築されている。それに伴い、幾つかのクエストの内容も変更。
-
本作のあらすじをぶっちゃけると、「よその世界から脱走してきた囚人がとある国の王様に化けて悪さをしていたが、主人公達がそれを見破ったので別の世界へ逃げました」というお話。諸悪の根源が逃げてしまい、続編の『Might and Magic:Book2』にて彼を追いかけるという展開となるため、本作だけではストーリーが消化不良気味。
評価点
小クエスト並立制
-
このゲームの最大の特徴の一つ。各地には大小さまざまなクエスト(=「おつかい」のようなもの)が存在し、「別の街に手紙を届けてほしい」とか「無くしてしまったとあるアイテムを探してほしい」といった頼みごとを聞いてあげると、報酬としてお金や経験値がもらえる。連続クエスト以外は自由にオファーできるため、攻略する順番はプレイヤーによって千差万別。本作の自由度は非常に高い。
-
前述したとおり、本作はゲーム開始直後にいきなり広い世界に放り出される形となるため、導入部分は非常に不親切ではある。
だが、所謂JRPGの様な「作者の用意した物語をなぞる」のではなく、広い世界を自分の足で歩き回り少しずつ謎を解いていくという「手探りの冒険」こそがM&M最大の醍醐味である。つまり攻略本は使わずに、腰をすえてじっくりと解いて行くのが正しい楽しみ方と言える。
-
ハマリが起きないようフラグ管理はかなりゆるく設定されている。各種クエストは何度でも受けられるし、クリアに必須となる重要アイテムでも捨てられたり敵に盗まれたりするが、何度でも再入手可能。
-
ただし、クエストのオファー状況および進行状況をゲーム中に確認できず、「セーブ&ロードをすると、進行中のクエストのフラグが消える『フラグ消失バグ』」なるバグが発生したりもする。なので、受けたクエストは一気に済ませてしまうのが基本。
PC版からの改良点
-
グラフィック強化。
-
背景やモンスターに至るまでグラフィックが一新されている。
-
特に3Dダンジョンの完成度はファミコンの域を超えており、そのヌルヌル動く3D描写は、数年後のSFCのソフトと比較しても決して引けを取らない。
-
オートマッピング機能搭載。
-
店や入り口などのシンボルが表示されず、純粋に迷路のみの表示ではあるが、非常に見易いので攻略の大きな助けとなる。
-
また、PC版同様付録に「世界地図」がついており、冒険のヒントが書かれている、裏面はマッピングシートとなっているなど気の利いた造りとなっている。
-
ゲームにおける地上マップも地図に則った作りとなっているし、「地図上でモンスターの絵が書かれている場所に実際にゲーム内で行くと、そのモンスターが襲ってくる」といった仕掛けもある(ちなみにそのモンスター達はクエストに関わる重要な存在でもある)。
-
敵・アイテム・呪文名の再翻訳。
-
モンスターや魔法・アイテム名は日本人向けにアレンジされている。なぜか「ゴクリ」や「ガラドリエル」といった『指輪物語』の固有名詞が入っていたりもするが…。
-
BGMの一新。
-
BGM担当は後に『伝説のオウガバトル』『BAROQUE』などを手掛けることになる岩田匡治氏であり、プレイ者からの評価は高い。
-
また、オープニング曲がなぜかパッヘルベルの『カノン』である。ファミコン音源3和音によるカノンもまた乙なものである。
-
バトルバランスの若干の調整。
-
敵は大量に出現するが、1ターン内で行動するのは先頭から6匹目までに変更。数の暴力で圧殺される機会は減った。
-
「魔法の武器しか効かない敵」は廃止され、普通の武器でも倒せるようになった。
-
AUTO戦闘が強化され、弱い敵(=レベル差が圧倒的に開いている敵)相手なら、AUTO戦闘で被害をこうむることなく一瞬で全滅させられるようになった。
総評
シリーズファン及びPC版経験者にはストーリー関連の改変で批判され、新規ユーザーからはあまりの高難易度のせいでクソゲー扱いされるという哀しき運命を背負った作品。
途中でゲームを投げ出した人は数知れず、気の短い人は最初の町から出ることすらできなかった。懐かしのクソゲーの話題になった時本作の名が挙がることも多く、今の基準で見るなら間違いなく「ゲームバランスが悪すぎるクソゲー」であろう。
しかし、一方で本作の特長である広大な3Dマップとフリーシナリオが斬新に映った人も多く、異常な難易度もバグも跳ね除けどっぷりとハマる者も続出。そういう意味では典型的な「賛否両論ゲー」である。また、「世界三大RPGの一つを手軽に楽しめる」「アレンジされた部分はおおむね好評」であることを考えれば、「良移植」とも言えたりする。
人によって評価の分かれる、判定の難しい作品と言えよう。
その後の展開
-
3年後に続編の『Might and Magic:Book2』がSFCにハードを移して移植された。
|
+
|
日本のCS機におけるMight and Magicシリーズについて
|
-
FC版から3年後に1作目のPCエンジン(CD-ROM2)版がハドソンからリリースされた。画面レイアウトはスタークラフトから発売されたパソコン版に近く、全体的に難易度が引き下げられている。イベントシーンでは声優によるボイスパートもある。但し、キャラクター名が固定化されており、それに合わせて設定やシナリオは原作とは異なった物となっている。
-
ナンバリング3作目の『Might and Magic III:Isles of Terra』はPCエンジン(SUPER CD-ROM2)版とメガCD版が1993年に発売された。
-
4作目である『Might and Magic IV:Clouds of Xeen』以降シリーズ7作目まではCS機での展開はされずPCのみとなった。
4作目と5作目の『Might and Magic V:Darkside of Xeen』はPC-9801版とFM-TOWNS版がリリースされた。
-
6作目から9作目はWindows98からXP時代に完全日本語PC版が販売された。
8作目の『Might and Magic 8 Day of the Destroyer』は当時日本語PC版を販売していたイマジニアからPS2にも移植されている。
-
現時点のシリーズ最新作であるナンバリング10作目の『Might & Magic X:Legacy』(2014年)ではプラットフォームにMac OSXが加わった。
-
尚、一部のスピンオフ作品は以下の作品がCS機にて展開された。
『Heroes of Might and Magic』、『Heroes of Might and MagicⅡ』(GBC、2000年)
『Warriors of Might and Magic』(GBC/PS/PS2、2000~2001年)
『Heroes of Might and Magic:Quest for the Dragon Bone Staff』(PS2、2001年)
『Dark Messiah of Might and Magic:Elements』(Xbox360、2008年)
『Might & Magic:Clash of Heroes』(DS/PS3/360、2009~2011年)
この内、日本では『Warriors of Might and Magic』のPS2版が2002年にサクセスから、『Dark Messiah of Might and Magic:Elements』は『マイト・アンド・マジック エレメンツ』のタイトルで360日本版が2008年にUBISOFTから発売されている。
|
余談
-
本来は1988年後半に発売予定だったのだが、実際の発売日の通り予定からかなり遅れている。おそらく一度大幅に作り直したためにここまで発売が遅れてしまったと思われる。
-
こちらの21:55~あたりとこちらの2:00~あたりで開発中の映像を少しだけ見ることが出来るが、製品版とは画面構成やサウンドがまったく異なっている。
-
PC版のパッケージ裏には「クリアまで何百時間もかかるゲームだから覚悟しろ」というようなことが書かれている。
-
実際その通りであり、「歴戦のゲーマーが事前情報無しで挑む」という前提なら冗談抜きでその位に達する。ただし、攻略の自由度が高いので、極めれば1時間もかからずにクリアすることも可能だったりする。
-
自社ブランドのゲームということで、当時の学研の学年別の学習雑誌でも、とことん取り上げていた。
-
少し前に発売された話題の大作RPG『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』(2月)『ファイナルファンタジーIII』(4月)を名前まで隠さずモロに使って引き合いに出して、本作を不自然なほど高い評価にする小学生から見ても清々しいまでに八百長にしか見えないほどえげつないアピールをしていたものの、結果的にはその両作の足元にも及ばなかったことは言うまでもない。
最終更新:2024年05月14日 20:32