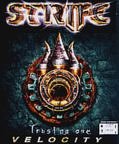STRIFE
【すとらいふ】
|
ジャンル
|
FPS
|
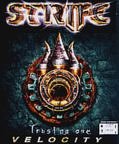
|
|
対応機種
|
MS-DOS
Windows
|
|
発売元
|
Velocity Inc.
Studio 3DO
|
|
開発元
|
Rogue Entertainment
|
|
発売日
|
1996年5月31日
【Steam】2014年12月12日
|
|
定価
|
980円(Steam)
|
|
配信
|
Steamにてオンライン販売中
|
|
判定
|
なし
|
|
ポイント
|
擬似オープンワールドFPS
会話・探索主体のゲームプレイ
不釣合いに少ない自由度
|
概要
1996年2月23日にシェアウェアとしてリリースされ、その後1996年5月31日に発売されたハブ構造を特徴とするFPS。
『DOOM』に使用されたid tech 1エンジンを使用しているが、銃撃戦ではなく会話と探索を主体としたRPG的なゲームシステムを採用している。
開発はid Softwareと関係が深く、後に『American McGee's Alice』を開発したRogue Entertainment。
2014年にはNightdive Studiosによって『Strife: Veteran Edition』として復刻された。
ストーリー
彗星の衝突と同時にウイルスが撒き散らされた地球。
ウイルスによって多くの人々が死に絶えたが、それと同時に突然変異を遂げ邪神の声が聴こえ始めた者たちがいた。
彼らは自らを「オーダー」と呼び、困窮する市民を支配、絶大な権力を誇る1国家としてその勢力を拡大させていく。
それに対抗する人々は、「フロント」と呼ばれるレジスタンスを結成。圧政に対抗し、密かに軍事力をかき集めていた。
そんな緊迫した状況に置かれている街「ターンヒル」に、フロントの話を聞きつけた一人の傭兵がやってくる。
警備兵とのひと悶着で到着早々追われる身となった傭兵は、オーダーを打倒すべくフロントに加入。破壊工作やオーダーとの戦闘を繰り返し、次第に彗星衝突の裏に存在する陰謀に立ち向かっていく。
ゲームシステム
操作方法
-
基本的には『DOOM』に準拠しているが、RPC化に伴いWキーでミッション目標表示(ブラックバードの連絡)、[キーでアイテム選択しQキーで選択アイテム名表示、Enterでアイテム使用、Backspaceでアイテムドロップ、Zキーで所持弾薬確認、Kキーで所持キーの確認など複数の操作が追加されている。
武器
-
数字キー順に「パンチダガー」「クロスボウ」「パルスライフル」「ミサイルランチャー」「グレネードランチャー」「火炎放射器」「ブラスター」「シギル」が存在し、状況に応じて使い分けていく。
-
クロスボウとグレネードのみ弾薬の切り替えが可能になるなど、やや拡張性も考慮されている。また、毒クロスボウと素手でのみ警報を鳴らされずに敵を倒すことが可能。
ゲーム進行
-
ステージクリア方式ではなく、市街地の会話でミッションフラグを建て、警戒区域に侵入、オーダーの兵士を倒して目的を達成し、再び市街地に戻る..という方式。『Hexen』に近いハブ構造を採用している。
-
経験値システムなどはなく、NPCとの交渉や落ちているものを拾うことで武器を取得し、探索や敵からのドロップで弾薬や資金を確保していく。
-
NPCとのコミュニケーションや商品の売買を行う市街地レベルと銃撃戦を行う警戒区域レベルの二つが存在し、それらが相互に接続され擬似的に1つの巨大なレベルとして機能するようになっている。
-
基本的にはWキーで表示可能なレジスタンスメンバー「ブラックバード」の指示に従い、該当するエリアに潜入したり特定の人物に接触したりといった形でレジスタンスとしての活動を行っていく。
-
警戒区域レベルでは『DOOM』同様の銃撃戦が挑めるが、市街地レベルやレジスタンス基地では中立NPCに発砲すると敵対状態に移行する。市街地レベルで一般市民を攻撃するか選択肢を間違えるとプレイヤーの近くに保安機構であるアコライト兵が無限に出現し続け、サブマシンガンでプレイヤーを攻撃する。商店などのシャッターは警報と同時に閉まるため、警戒状態で店を利用することは出来ない。
評価点
RPG要素の導入
-
金銭要素やインベントリ要素を簡易的ながら実現しており、DOOMクローンに囚われない独自性を獲得している。
-
エンジンが共通しているのもあり、本作の会話システムはRPG要素のあるファンメイドの『DOOM』用WADのベースとしても利用されている。
ストーリーの重要性向上
-
NPCとのストーリーに関わらない会話などを通じてストーリーを把握できるようになり、当時のスポーツ系FPSでは疎かになりがちだったストーリー面の補強が行われている。
賛否両論点
面白みに欠けるストーリー
-
SFとファンタジーをごちゃまぜにしたようないびつな世界で、宗教団体の圧政にレジスタンスが立ち向かうというなんとも形容しがたいジャンルの世界観が特徴。
-
ストーリーの完成度はお世辞にも高いとは言いがたく、グッドエンドとバッドエンドで設定が矛盾するなど突っ込みどころも多い。
-
グッドエンドの締めくくりは「ヒロインが主人公とキスをして終了」という短く唐突なもの。世界が救われるだろうということは語られるが、肝心の救われた世界が描かれることはない。
問題点
2Dグラフィック
-
1996年は既に手書きグラフィックから3Dモデルをベースにしたプリレンダリングが主流となり、一部作品では部分的に3Dポリゴンが用いられていた時代。それに対して本作は全てのドットが手書きのものであり、チープさが否めない。
豊富な選択肢に不釣合いな攻略の自由度の無さ
-
会話の選択肢が多いわりに、その内容は「正解か、もしくは詰みか」の両極端な内容。間違った選択肢を選んで詰む場面が非常に多く、更に序盤のイベントのほぼ全てに詰み選択肢が仕込まれているという拘りよう。
-
最初に発生するイベントである、Rowanによる地下組織への勧誘から選択肢の理不尽さは全開。Rowanに対して「Sure.」「No thanks.」「See you later.」の三択が示されるが、「No thanks.」を選択した途端辺り一面に敵が無限にワープして詰む。「See you later.」を選択しても会話がリセットされるだけで、実質的な選択肢は「Sure.」のみ。
依頼を達成し信頼を得た後に加入を断っても容赦なく通報されて蜂の巣にされ、反乱軍指揮官との会話で加入を断ってもその場の全兵士から一斉射撃を食らって死ぬ。このように、選択すると詰むだけの不必要な罠選択肢ばかり揃っており、ストーリーを真面目に進める場合は選択肢の自由度は皆無。
-
FPSというスタイルやその会話システムの見た目から『Deus Ex』などの先祖と見なされることも多いが、それら固有の特徴である攻略の自由度や選択の自由度といった要素はほぼない。唯一のストーリー分岐も「グッドエンドか、バッドエンドか」の二択のみで、グッドエンドを目指すなら実質的に一本道となる。
詰み要素として乱用される警察機関
-
重要アイテムを破損させたり、ミッションを失敗したり、選択肢を間違えたりといったタイミングで毎度のように上級アコライトの無限湧きが多用される。後のオープンワールドタイトルの警察のように通報システムが洗練されておらず、ただ大量に出現し続け、詰んだことをシステムでプレイヤーに伝える要素でしかない。
-
市街地の店などで奪えるアイテムもなければ一般NPCを射殺した際のドロップアイテムもなく、「犯罪行為を犯して警察から逃げる」といったシチュエーションは皆無。基本的に、まともに機能する警察を見るのはストーリー的に詰んだ場合に限られる。
総評
非戦闘NPCとの会話や共闘といったRPG要素を加えた『DOOM』として発売された作品。
一見すれば豊富な選択肢が与えられているように見えるが、選ぶと詰むハズレ選択肢を増やしているだけで実質的にストーリーの自由度はほぼない。
『DOOM』と比較すれば多くの革新性が存在するものの、単体の作品としては詰めの甘さが多く見られる内容となっている。
余談
-
本作は「id Tech 1エンジン」を使用した公式ライセンスの商業ゲームとしては最後の作品となっている。
-
2001年にRogue Entertainmentは閉鎖されたため、オリジナルのソースコードは失われていた。しかしid tech 1自体が既にオープンソース化していたこともあり、ファンのリバースエンジニアリングによって再現と拡張が行われ、最終的にZDoomなどの統合ソースポートに至るまでは、Vavoom、SvStrifeといった複数のStrife用エンジンが開発された。
-
2014年には版権を取得したNightdive Studiosが復刻を行ったが、この際のベースもオリジナル版ではなくChocolateDoomエンジンのStrife版である「ChocolateStrife」をベースにしている。
-
ゲーム内のUI、音声および字幕は英語だが、GZDoom ver.4.2.0から『STRIFE』のIWADが日本語に対応したため、GZDoomを使えば、UIおよび字幕が日本語に翻訳された状態でプレイすることができる。
最終更新:2022年05月03日 17:49