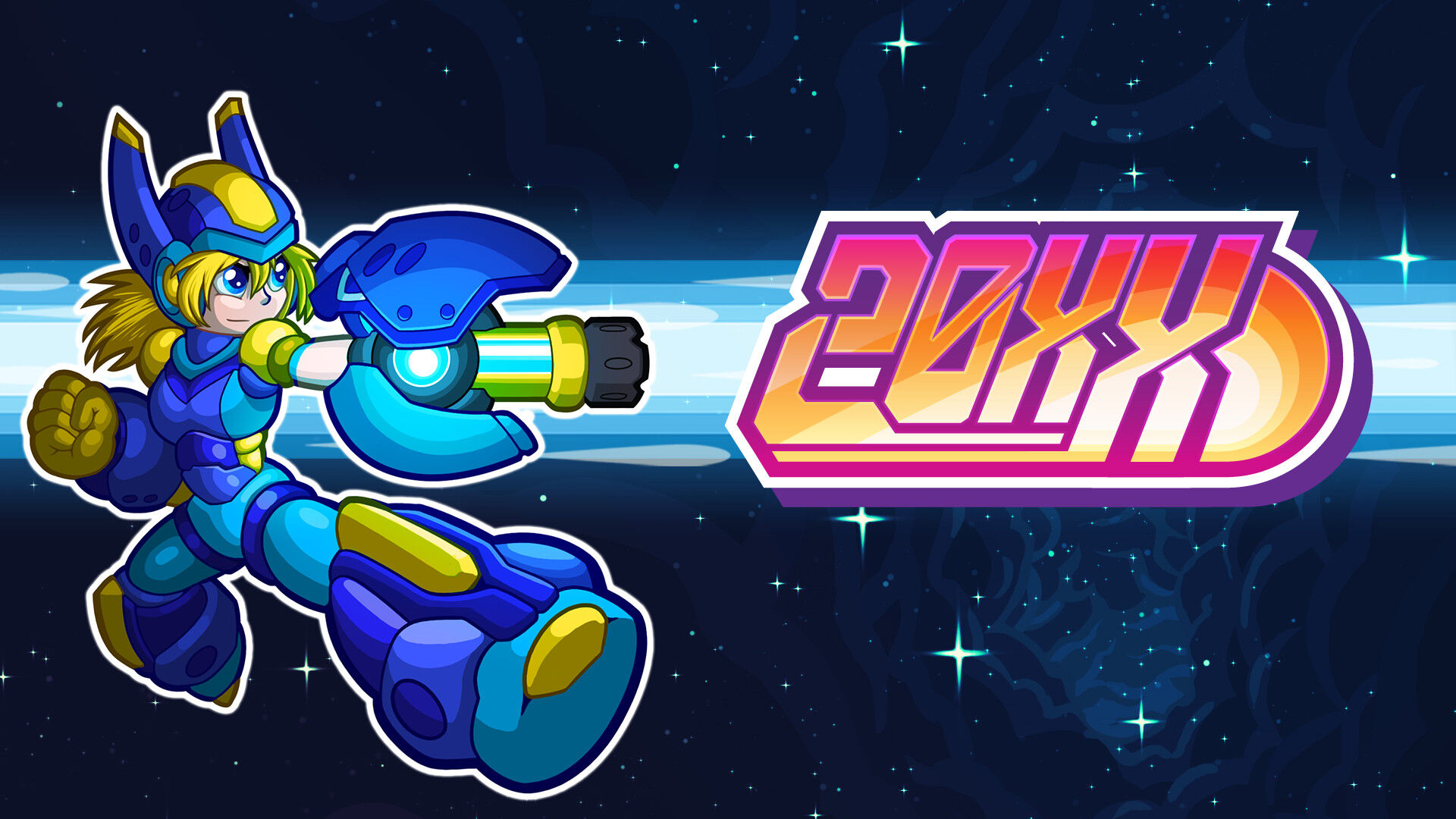20XX
【とぅえんてぃえっくすえっくす】
|
ジャンル
|
アクション+ローグライク
|
|
|
対応機種
|
Windows 7~10
Mac OS X 10.6~(Steam)
プレイステーション4
Nintendo Switch
Xbox One
|
|
発売元
|
Batterystaple Games
|
|
開発元
|
Batterystaple Games
Fire Hose Games
|
|
発売日
|
【Win】2017年8月16日
【PS4/Switch】2018年7月10日
【One】2018年7月11日
|
|
定価
|
【Win】1,480円
【PS4】2,016円
【Switch】1,980円
【One】2,100円
|
|
判定
|
良作
|
|
ポイント
|
外国製のインディーズゲーム
露骨な名作オマージュ
劣化コピーで終わらぬシステム
「自分で決める」難易度
他人と競い合う楽しさ
|
概要
正義のロボット達が悪い博士達のメカ軍団に立ち向かう、どこかで見た様な最早定番となった2Dアクション。
「プレイヤーキャラのカラーリングや攻撃手段」「ダッシュや壁張り付きの挙動」「八体のボス」「倒したボスの特殊能力を獲得できるシステム」等々、一見しただけで往年の名作アクションを彷彿とさせるあからさまな作りとなってはいるが、
本作はその分かりやすい雛形に「マップ自動生成、敵やアイテムのランダム配置といったローグライク要素」や「スコアによる競技性」を混ぜ込んでおり、その結果「繰り返し遊べるリプレイ性」を加え独自の個性を獲得する事に成功している。
システム
-
基本的な操作は五つ。
「通常攻撃」「パワーの使用」「ダッシュ」「ジャンプ」「アイテムの獲得及び項目の決定」
-
通常攻撃はボタン押しっぱなしでチャージが可能。チャージ後最初の攻撃が強化される。
-
自機は地形の側面に張り付きが可能(但し少しずつずり落ちていく)。側面からジャンプも出来る。
-
ゲームの流れは
「プレイヤーキャラクターと、ゲームモードを設定してゲームスタート」
-------------------------------------------↓
「道中で自機の強化をしながらステージ最後に控えるボスを倒す」
-------------------------------------------↓
「撃破後は、任意で「ボスパワーの獲得」「ナット(いわゆる通貨)の獲得」「基礎能力強化の獲得」を選択し、次のステージを提示される三択の中から決定する」
-------------------------------------------↓
「ステージが進むとゲームの難度が1段階上昇。敵や地形トラップのパターンやボスの耐久力・挙動が変化し、段々と難しくなってゆく」
-------------------------------------------↓
「全10ステージを踏破する、あるいは自機のHPが0になる事でゲーム終了。それまでの道中やボス撃破で獲得した"ソウルチップ"を用いて"新しいアイテムのアンロック"や"自機の恒久的或いは次回プレイ限定の強化"等を施す」
-------------------------------------------↓
「また次のゲームへ」
となっている。それぞれの構成要素の説明は以下の通り。
-
基礎能力
プレイヤーキャラの具体的な強さを表す数値。プレイ中に獲得する様々なアイテムによって、それぞれの値が増減していく。
-
HP
所謂生命力。これが0になるとゲームオーバー。
-
エネルギー
パワーの行使に必要。基本的には一回の行使につき1消費だが、例外あり。また視覚ではわからないが内部的には1未満の数値も計算されている。
-
攻撃力
各キャラの通常攻撃及び一部の「リプロ(自立兵器型アイテム)」のダメージに影響。
-
パワー攻撃力
各パワー及び一部のリプロのダメージに影響。
-
走る速さ
キャラの移動速度に影響。「走る」とはあるが、当然歩く速さも変わる。
-
ジャンプ力
キャラのジャンプの高度に影響。これと上記の走る速さの数値如何で実際のジャンプの軌道は微妙に変化する。
-
パワー
各ステージのボスを撃破する事で獲得できる能力。
オマージュ元よろしく8体のボスは必ず何かしらのパワーを弱点としており、ボス戦にそれらを持ち込めば戦闘を有利に進めることが出来る。
但し、それらは本体に当てて大ダメージというような単純なものではなく、
「一部の行動に対するカウンターとして使用する」
「特定のタイミングで当てることで相手の動きを止める」
「本体ではなくお供の方に使用して本体を巻き込む」
といった、ちょっと捻った使い方が要求される。
また、各パワーはそれぞれ自機の挙動やステージのギミックに強烈に干渉する「特殊効果」を持っており、弱点武器以外の使い道も用意されている。
場合によっては寧ろそちらの方を目当てにされたり、ボスに対し弱点武器よりも有効に機能する事すらある。
|
+
|
パワーの一覧
|
-
ヴェラ
任意の4方向に真っすぐ進む弾を大量に打ち出す能力。
連射速度は相当なもので瞬間火力はまずまず。しかし単発威力が低いので燃費は最悪。
特殊効果は「下向きに発射する事で自機を浮遊させる」
このおかげで攻撃手段以上に移動手段として重宝される変わった一面を持つ。
-
ブーメランブレード
射出方向にある程度進んだ後しばらく停滞し、逆方向へ加速しながら折り返すブレードを撃ちだす能力。
単発威力は低いが、停滞している間は連続ヒットするため潜在的な火力は中々高い。
特殊効果は「ドロップアイテムをブレードに巻き込んで回収できる。また、その際は消費エネルギーが還ってくる」
自機での取得が間に合わないアイテムを咄嗟に回収したり、敵とアイテムを巻き込んで実質無消費で攻撃するといった芸当が可能。
-
モーター
接触する事で爆発する弾頭を撃ちだす能力。
弾頭と爆発両方にダメージ判定があり効果範囲が広い反面、軌道が山なりで弾速も遅いのが難点。
特殊効果は「敵が展開するバリア類を貫通してダメージを与える事が出来る」
バリアを展開してくる敵はこちらの攻撃を無効化するだけでなく、撃ち返し弾を発生させたり、周りにいる敵に対してもバリアを付与したりと厄介な個体が多い。
この能力はそれらに対抗する数少ない手段の一つとなる。
-
クエイント・レーザー
前方にゆっくりと飛翔する方形の光弾を打ち出す能力。チャージによって三段階まで威力を強化可能。但しその際の消費エネルギーも増加する。
単発威力は最高峰だが、チャージの段階を経る度に燃費は悪化するので使い分けが肝要。
特殊効果は「最大チャージで道中にある自販機を破壊して中身を取り出すことが出来る」
エネルギーを消費するものの、普通に利用するより圧倒的に高効率となるので便利。
-
シェイドスパー
地形を貫通するクリスタルを「自機の移動と同ベクトル」で発射する能力。
この「同ベクトル」というのが厄介で、望む方向・速度に飛ばすには少々熟練が必要となる。その点を踏まえれば、理論上360°あらゆる所を攻撃可能な事が利点となる。
特殊効果は「出現消滅を繰り返す足場(所謂"消える足場")を固定させる」
本家のモノに負けず劣らずこの手のギミックは厄介なので、この効果の利用価値は高い。
-
スプリンターフロスト
敵或いは地形に接触する事で広範囲に礫をばらまく氷柱を発射する能力。
「軌道が直線で弾速もそこそこ」「本体と礫の両方に判定がある為火力も良好」と曲者揃いのパワー群の中では珍しく素直な性能。
特殊効果は「壁や地面に設置されている炎を吐き出す砲台を凍らせて無力化させる」
この手の砲台は大抵大量に設置されているので、無力化できるか否かで難易度はかなり変わってくる。
-
フォースノヴァ
自機の周辺に一瞬だけ敵弾をかき消す電磁バリアを展開する能力。
高い防御性能が売りだが、その分攻撃力は最低クラス。
特殊効果は「地形トラップであるレーザーをショートさせて無力化させる」
炎の砲台同様、この手のトラップは以下略。
-
フレイムシールド
自機の周囲を廻りながら敵弾をかき消す炎のバリアを4つ展開する能力。
一見フォースノヴァと似た能力だが、仕様は大分異なる。具体的には、
「フォースノヴァは時間経過(一瞬)で判定消失。範囲内全てに効果がある。但し敵一体につきヒット回数は一回」
「フレイムシールドは接触で判定消失。効果範囲は炎の部分のみ。炎毎に判定が独立している(最大4ヒットする)」
よってノヴァと比較して、大量の敵弾や炎の内部からの攻撃には対応出来ないが、事前に展開する事が可能で瞬間火力も高いのが特長となる。
特殊能力は「壁や地面から吐き出される氷柱と接触しても炎が消えない」
上記二つと違って、炎が欠けない限り一度の使用でいつまでも自機を守れる反面、氷柱の発射そのものを停止することは出来ない。
|
-
自機の強化
-
プレイ中自機は「道中のアイテムボックスから取得する」「ショップでナットを対価に購入する」「特別なエリアに侵入する」等の方法で様々な強化アイテムを手に入れることが出来る。
強化アイテムはその特徴から「オーグメント」「メインウエポン」「プロトタイプ」「コア・オーグメント」の四種類に大別される。
-
オーグメント
自機の直接的な強化を司るアイテム群。
一部の例外を除いて効果は重複するので、同じアイテムを繰り返し取得する事で自機はより強化される。但し、一部数値がマイナスになる物や、強化が過剰になりかねない物もあるので単純に「取れるだけ取るのが良い」というわけではない。
-
メインウエポン
弾が3way,4wayになったり、攻撃範囲が狭くなる代わりにリーチが伸びたりと、自機の通常攻撃方法を変化させるアイテム群。
同じアイテムが繰り返し出現する事もあるが、オーグメントと違い「強化」と言うよりは「換装」なので、複数取得してよりパワーアップという真似は出来ない。そして一キャラが同時に持てるのは一種類だけ。(一機例外がいるが)
-
プロトタイプ
「シークレットラボ」というゾーンに入る事で取得できる特別なアイテム群。
「通常攻撃のダメージが増大するが、パワーが一切使えなくなる」
「ステージごとに攻撃力が増強されるが、その都度HPの最大値が減少する」
「以降のオーグメントの効果が倍化する代わりに被ダメージが3倍になる」
等々、非常に強力且つオンリーワンなメリットを享受出来るが、それを差し引いても尚割に合わない重大なデメリットを課せられるのが大きな特徴。
-
コア・オーグメント
自機の「頭」「胴体」「腕」「足」に装着する事で特別な効果を付与するアイテム群。
同部位同時所持は不可なので、性質としてはメインウエポンに近い。
但し、このアイテム群は「系統」という分類があり、全ての部位を同系統で揃えることで追加のボーナスを発揮する特徴を備えている。
|
+
|
各系統の説明
|
-
「ドラコペント」シリーズ
「二段階目のチャージ解禁」「チャージ攻撃直後の攻撃もチャージ扱いになる」等、主に通常攻撃及びチャージを強化するシリーズ。
同系統でそろえた時のボーナスは「全ての通常攻撃がチャージ扱いになる」
-
「オウルホーク」シリーズ
「通常攻撃で敵撃破時、確率でエネルギー回復」「パワー使用時確率でエネルギー消費免除」等、主にエネルギーリソースを改善するシリーズ。
同系統でそろえた時のボーナスは「全てのパワーの性能が強化される」
「同時展開数が増える」「攻撃ヒット時周りの敵にも連鎖する様になる」など、具体的な効果はパワーによって様々。
-
「アーマートートシリーズ」
「チャージ攻撃に敵弾消滅効果付与」「被ダメージによるノックバック無効」等、主に自機の生存性を高める事に特化したシリーズ。
同系統でそろえた時のボーナスは「トゲや穴等の地形トラップダメージの無効化」
-
「オクスジャック」シリーズ
「ダッシュ方向に追加弾を発射」「ダッシュ時前方にバリア展開」等、主にダッシュの性能を強化するシリーズ。
同系統でそろえた時のボーナスは「空中で3回ダッシュが出来るようになる」
|
-
プレイヤーキャラクター
-
用意されているキャラクターは4体。それぞれが異なるコンセプトを持っているので、
例え同じゲーム設定でも、この選択によって道中の立ち回りや強化の取捨選択、設定による有利不利など、実際のプレイの内容は大きく変化する。
|
+
|
各キャラクターの説明。
|
-
ニナ
青いカラーリングの遠距離攻撃主体のキャラクター。いわゆるエックス。チャージ効果は「ダメージアップ」「弾の巨大化」「限定的な貫通効果付与」
離れた間合いから一方的に攻撃できるのが強みで、且つ場合によっては3way、4wayのウエポンも手に入る為、道中の安定性はトップクラス。
加えて弾の発射制限は「画面内に残っている弾の数」に依存するので、一対一の雑魚戦に限り瞬間火力も非常に高い。
しかし「連続ヒットでダメージが減衰しヒット数自体にもキャップがある」ボス戦では他キャラに比べてメインウエポンの火力不足が顕著に表れる。
また、貫通攻撃がチャージ時の一発のみで効果も限定的な為「高耐久な敵の大群を素早く捌く」のが苦手、遠距離故に倒した敵のドロップを回収できない場面が多々ある、といった欠点も備えている。
とはいえこれらは直接本体を脅かすような危険にはなりにくい為、「クリアを目指すだけなら誰よりも安定する」初心者向けのキャラクターと言えるだろう。
-
エース
赤いカラーリングの近距離攻撃主体のキャラクター。要はゼロ。チャージ効果は基本的には「ダメージアップ」のみ。但し一部のウエポンには「リーチの増加」も付与される。
ニナとは真逆のコンセプトで、リーチが限定的な反面全ての攻撃が貫通効果持ち、さらに連撃によってモーションが変化し、連撃の後の方ほどダメージがアップする特徴がある。
よって「大群相手でも殲滅力が落ちにくい」「ボスにも高効率のダメージを与えられる」事が強みとなる。
但し攻撃を当てるためには兎に角相手に肉薄する必要があり、被弾の危険性はニナとは比べ物にならないほど高い。
また高い攻撃性能はあくまでも理論値で、実際の運用となると「自分と相手の挙動を正確に測る技量」と「限られたチャンスに挑む思い切りの良さ」が要求される。
敵の攻撃に尻込みして、結局ニナよりDPSが下回ってしまう事も珍しくない。
さらにニナと比べて攻防両面でパワーへの依存度が高くなりがちな為、プレイヤーはゲーム全体を通してのリソース管理能力も試される。
総じて「潜在能力は高いが、要求される事も多い」上級者向けのキャラクター
-
ホーク
紫なカラーリングのパワー主体のキャラクター。Steam版のみDLC扱いで追加の課金が必要となる。チャージ効果は「ダメージアップ」及び「エネルギーの回復」
彼女の特徴は何と言ってもメインウエポンである「サイフォン」にある。これはチャージをヒットさせるか敵を撃破することでエネルギーが回復する効果を持っている。
これによって一度得たパワーはほぼ無制限に使えるのが最大の長所。
前述の通り、各パワーはボスの弱点武器になるだけではなく道中でも有用な物が多いので、これらを常時展開する事で安全かつ素早いステージ攻略が可能となる。
また、メインウエポンの換装がない代わりに「彼女専用のパワー」が用意されており、これらも中々強力な代物が揃っている。
反面「望むパワーが揃わないと長所を活かせない」「初期ステータスにペナルティがある(パワー攻撃力-5)」というデメリットも抱えており、どうしてもスロースターターになりがちな点は否めない。
上記二体と比べて「ハマれば強いが、前半にやや不安がある」キャラクターといった所か。
-
ドラコ
黄色いカラーリングの通常攻撃主体のキャラクター。ホーク同様Steam版のみDLC扱いで追加の課金が必要となる。
各キャラが同時に一つしか持てないメインウエポンを複数持てる事が最大の特徴。また、チャージのルールも上記三体と異なり、
「時間経過で自動的に、最大二回分チャージをストック出来る(特定の条件下では3回分、5回分にもなる)」「チャージ攻撃は各ウエポン毎に異なる特殊効果が付与される」
という仕様となっている。
専用ウエポンの数々を用いた特殊効果のお陰で、他三体とは全く異なるアプローチでの攻略を可能としている。これが長所。
一方パワーの運用能力は最低で、彼はパワーを原則一つしか持てず、初期エネルギーも他三体の半分しかない。
しかもボスを倒した際の報酬がパワーになるかウエポンになるかの確率も五分五分、さらにウエポンの場合は何が抽選されるかも完全にランダムである為、ビルドがかなり不安定。
独特の仕様を活かした攻略を強いられる故に他三機との共通点に乏しく、彼を使いこなすには彼専用のノウハウが必要になる。
|
-
ゲームモード
選べるゲームモードは通常プレイのノーマルに加えて、
「オマージュ」「ディファイアント」「チャレンジ」「シードレーサー」「ラッシュ・ジョブ」の計6種類。
これらのモードを一人用の「ソロ」か二人用の「マルチプレイ」かを選んで遊ぶ形になる。
詳細は以下の通り。
-
オマージュ
所謂イージーモード。ライフが0になっても3回まではコンティニュー出来る。
-
ディファイアント
所謂ハードモード。
このモードには有効にすることでプレイに様々な障害が発生する「スカル」という項目があり、それをプレイヤーが任意で組み合わせて難易度を設定する。
|
+
|
スカルの詳細
|
-
マラソン
ステージ道中が長くなる。
-
飢餓
HP回復アイテムが出現しなくなる。
-
破産
ナット及びショップが出現しなくなり、買い物による強化が出来なくなる。
-
純粋主義
移動力に関わるオーグメント及び、コア・オーグメント全般が出現しなくなる。但しプロトタイプだけは例外。
-
ライトニング
ゲームスピードが1.5倍になる。
-
ロック
落とし穴やダメージ床で即死するようになる。曰く「先人リスペクト」。
-
大群
雑魚敵及びトラップの配置数が激増する。
-
毒素
各ステージに設定されているタイマーの仕様が変わる。
通常時は「時間までにボスを倒せば追加のボーナス」だったものが、「時間までにボスに辿り着けないとHPが徐々に減っていく」様になる。
また、時間内に辿り着いてもボーナスの恩恵は受けられなくなる。
-
最終目的地
一切の強化アイテム類及びナットが出現しなくなる。強化の機会はボス撃破時の3択だけ。
-
熱狂
敵の一部の攻撃速度と攻撃頻度が高速化する。ライトニングはと違い加速するのは敵の挙動だけ。
-
憤怒
敵からのダメージが2倍に。地形トラップのダメージは対象外。
-
不屈
全ての敵の耐久度が2倍に。
-
ストーン
落とし穴やダメージ床のダメージが4倍に。敵からのダメージは対象外。
曰く「先人よりはマシ」
-
エンドレス
9ステージ目を選択をしない限り、いつまでも8ステージ間でループし続けるようになる。
また、ステージ進行に併せて、こちらの被ダメージと敵の耐久力も増大していく。
-
最高潮
ゲーム開始時点で難度が+4。つまり最初のステージが5ステージ相当になる。
-
ディスティニー
通常時では三択だった次ステージの選択が一択になり、完全ランダム化する。
-
欠乏
ボス撃破時の選択報酬が最初の三体で打ち止めになる。
|
-
チャレンジ
全プレイヤーが同条件のゲームをプレイして、そのスコアを競うモード。
日毎に内容が更新され挑戦は一回限りの「デイリーチャレンジ」と、週毎に更新され期間内に何度でも挑戦できる「ウィークリーチャレンジ」の二種類に大別され、
そこからさらに、スカルなしの「ノーマル」と、三種類のスカルがランダムで設定される「ハードコア」の二種に分かれる。プレイヤーのスコア及び順位はゲーム開始前ロビーの「リーダーボード」にて閲覧することが出来る。
-
シードレーサー
シード値(ランダム要素の中身を決定づける数値)を固定してプレイするモード。
各ゲームは終了時に今回のシード値が表示され、それを入力する事によってその時と全く同じ内容のゲームをプレイすることが出来る。
苦手な編成の練習や、特定のトロフィーの獲得に利用など色んな用途で使用される。ソウルチップは出現しない為、同じパターンで手軽にチップ稼ぎという真似は出来ない。
--ラッシュ・ジョブ
所謂一つのボスラッシュモード。スカルの設定ももちろんできる。
1プレイが短めな為か、こちらのモードもソウルチップは出現しない様になっている。
-
マルチプレイ
上記の難易度設定とは別に、一人で遊ぶ「ソロ」、同画面で二人で遊ぶ「ローカルマルチプレイ」、オンライン上のプレイヤーと遊ぶ「オンラインマルチプレイ」の三種を設定できる。
マルチプレイの具体的なルールは以下の通り。
-
オンラインの場合は、部屋を建てたホスト側のデータ(アイテムのアンロック状況やスカルの設定など)が反映される。
また、意思疎通の手段として用いる8種類の「エモート機能」と、エネルギーを消費して相手側の座標に即座に移動する「ワープ機能」が操作に追加される。(但し後者は「オマージュ」及び「ノーマル」時のみ)
-
「オーグメント」は取得した時点で必ず両者に適用される。片方はマイナス効果を嫌って強化を放棄、といった真似は出来ない。
それ以外の強化アイテムは生成時に二人分用意され、取得した方のみに適用される。但し、プレイヤー間に互換性はなく、片方が換装により残したアイテムをもう片方が使う事は出来ない。
-
相方のHPが尽きた場合は、道中或いはボス手前・直後に出現するカプセルを利用する事で復活させることが出来る。
その際生き残っている側の現在HPが折半され相手に分け与えられるが、「復活する方」は最低3目盛分のHP保証があり、「復活させる方」もこの行為でHPが3未満に"減る"事は無い。
但し、これは「復活させる方もHP3が保証される」という意味ではない。
(例えばHP4で復活させた場合は両者HP3、HP1で復活させた場合はそれぞれHP1とHP3になる)
評価点
-
極限まで制限が取り払われたアクション性
-
アクションゲームをプレイする際、プレイヤーがまず気に掛ける所は
「プレイヤーの操作がきちんと反映されるか」「どれだけ自由な動きがゲーム内で許されているか」
であるだろうが、本作はこの点に関して満点をつけてもよいレベルでキャラが自由自在に動く。
真っ先に注目すべきはジャンプアクションで、
「ドット単位での調整が可能」「先行入力可能」「ダッシュジャンプに助走がいらない」「空中制御に制限がない」と至れり尽くせりの性能で、操作の快適性を支える基盤となってくれている。
また攻撃・パワー類も基本的にボタン押下で即発動、硬直時間のような面倒な要素も極力排除されており、移動と攻撃は原則互いを阻害しない。
よって操作に慣れてくると
「落下判定ギリギリのブロックの側面に連続小ジャンプで張り付きながら空中で振り向き、足場に陣取る敵を攻撃」
「動く足場群に併設されているダメージトラップを"足場に乗らず側面だけを伝って"回避」
「ダメージを受ける天井との隙間が数ドットしかない隘路にある穴を超低空連続ダッシュジャンプで渡りきる」
「空中で攻撃→キャンセルを入れてもう一回→さらに空中ジャンプでキャンセルしてもう一回→さらにさらにキャンセルを入れて……」
といった、スタイリッシュなプレイをキメる事が出来るようになる。
このようにプレイヤーの反応速度及び操作を妨げる要素が皆無なアクション性は、移動・攻撃・回避全てを並列でこなしながら攻略するテンポのよさを提供するとともに、プレイヤーの操作で実現できる挙動の限界をより高いレベルに引き上げている。
-
柔軟な難易度
-
いくらプレイヤー次第でどこまでもハイレベルな操作が出来たとしても、攻略するステージがそのレベルを要求する物でなければ只の自己満足、宝の持ち腐れで終わってしまう。
逆に操作側のレベルの高さを見越して初めから高難度のステージを用意すれば、多くのプレイヤーが早々に脱落してしまう。
このジレンマを解決してくれるのが「スカル」による「プレイヤー自身で選択する」難易度システムである。
このスカルはその数の多さもさることながら、それぞれが組み合わさる事でより高い難度を実現する「シナジー効果」も持ち合わせている。
例えば「飢餓」に「純粋主義」や「破産」を組み合わせればHP回復の機会がほぼ皆無になって、一回の被弾が命取りになる凄まじく緊張感のあるゲームとなり、
「欠乏」に「ディスティニー」を組み合わせれば、プレイで得られるパワーが完全にランダムになって、その時その時で引いた能力を駆使するプレイを強いられるゲームとなる。
大半のスカルを盛ろうものなら、1ステージ生き延びる事すら困難な凶悪な難度と化す。
もちろん難度を上げる方向だけに腐心しているのではなく、コンティニュー可能な「オマージュ」モードを始め、繰り返し遊ぶことで解除できる「恒久的な強化」や「スタート前ドーピング」、マルチプレイによる他プレイヤーとの協力等、アクションが苦手なプレイヤーにも無理なく攻略させる配慮も欠かしていない。
多種多様な組み合わせによる難易度を用意することで、自身のレベルに合わせたプレイを可能にし、さらに磨いた己の技が腐る心配もない。
カジュアルからコアまで幅広い楽しみ方が出来るこのシステムが本作の美点の一つとなる。
-
リプレイ性の塊「デイリーチャレンジ」
-
実は本作はノーマルを只クリアするだけなら、プレイ毎の内容にあまり差を感じる事は多くない。
しかしこれに「スコアによる競技性」を一つ加えただけで状況が一変、忽ち隠されていたゲーム性が姿を露にする。
「チャレンジモード」のスコアは大きく分けて、「敵の撃破による加点」「タイムボーナスによる加点」「被弾による減点」の三種類で成り立っている。そしてそれぞれは、
「敵を余すことなく倒していけばそれだけリソースが多く手に入り以後の攻略が楽になるが、被弾の危険性も増し返ってスコアを落とす事にもなりかねない」
「余計な戦闘や寄り道によるアイテム回収を避けつつゴールを目指すのは確かに早いが、手に入るリソースが少なくなり段々と攻略が苦しくなっていく」
「被弾を恐れて慎重に立ち回れば失点を抑えられるが時間は犠牲になってしまう」
という具合に絶妙なバランスで競合しており、プレイヤーは自分の実力とリスク、リターンを常に天秤にかけながらハイスコアを目指すことになる。
さらにそのバランスも「ステージの順番」や「選択したキャラクターとの相性」「スカルの組み合わせ」等の要素によって日毎に目まぐるしく変わって行く。
またデイリーは「一発勝負」である故に、自分の選択がベストかどうだったかは最後までやってみないと分からない。
以上のようにデイリーチャレンジは、操作のレベルがモノを言う「アクション」の側面、条件毎に最適を模索する「ノウハウ」の側面、そして不透明な状態での判断を迫られる「運」の側面が色濃く現れるゲームとなっており、
それがもたらす「リプレイ性」をもって繰り返し長く楽しめるようになっている。
-
その一方で、「ウィークリーチャレンジ」は、期間内ずっとシード値が固定且つ挑戦回数に制限がないモードとなっており、
「アクションゲームなのに運の要素で順位が決まってしまいかねないのは我慢できない」
「一発勝負は性に合わない」
というプレイヤーは、こちらで納得いくまでリトライを繰り返しスコアを煮詰める事が出来る様になっている。
相いれないニーズに対してきちんとフォローしている点も高評価。
問題点
-
マルチプレイ時の「意志表現」の乏しさ
-
マルチプレイ時は原則部屋を建てたホストの設定が反映される。ゲストは全面的にこれに従う形となり拒否権がない。
さらにゲスト側は、ホストがどんなスカルを設定しているかをゲームスタート後にしか確かめる事が出来ず、事前に相談する術を持たない。
よって入室したは良いが、自分の実力とは程遠い超絶難度のゲームに付き合わされたり、逆に設定が簡単すぎて退屈してしまったりといった事がままある。
またプレイ中に使えるエモートも種類が少ない上に、表現として曖昧で分かりにくい、或いは限定的過ぎて使う機会自体に乏しいモノばかりで、互いの意思疎通にはかなりの苦労を要する。
-
因みに実際のプレイではプラットフォームであるSteamや、ゲームコミュニティであるDiscordなどのチャット機能を使う事で解決するパターンが多い。
但し、グローバルなツールである故に内容が英語であったり、ボイスチャットを希望されたりと、使用する際のハードルが少々高い傾向にある事は否めない。
-
先行入力の弊害
-
コア・オーグメントの中には足のパーツに「二段ジャンプを可能とする」「空中でホバリング出来る」といった機能を備えているものがあるが、
これらの発動条件は「空中でジャンプボタンを押す事」であり、ジャンプの先行入力と条件が被ってしまっている。
通常時の先行入力に慣れてしまっていると、望まない形でパーツの効果が発揮されるトラブルが起きやすい。(例えば先行ジャンプのつもりがホバリングが優先されてしまい動きが止まってしまう等)
きっちり地に足がついている事を確認した上で入力すればこのトラブルは避けられるが、前述の通りジャンプの先行入力はこの作品のテンポの良さを支える大事な要素の一つなので、
「熟練したプレイヤーほどこれに引っ掛かりやすい」という少々厄介な問題点となってしまっている。
総評
ともすれば本家のファンから色眼鏡で見られかねないあからさまなゲームシステム
そのフィルターを通して尚ユーザー達を頷かせるに足る骨太なアクション
そしてそこに繰り返し遊びたくなるよう大いに盛り込んだスパイス
これら三つを上手に混ぜ合わせた本作は、クローンゲームとしての面目を十二分に保ちつつ、只のクローンとは呼ばせないだけの説得力をもつゲームに仕上がった。
ただローグライクの宿命故か、同じ事の繰り返しの様に見えてその実、骨までしゃぶりつくすとなれば相当な時間がかかる一品であることだけは述べておく。
しかしそれを強制するようなデザインでは決してなく、価格もそこそこ軽めなので、
「取り敢えず一通りクリアまで軽く遊ぶ」のも
「最初から全プレイヤーの頂点を目指してイバラの道を進む」のも
「カジュアルに遊んで終わるつもりが、気が付いたら深みにハマっていたりする」のも
全てはコントローラーを握っているあなた次第。
「自分なりの選択・プレイスタイルが許される事」こそ、ローグライクを遊ぶプレイヤーの本懐というものだろう。
最終更新:2023年07月01日 15:54