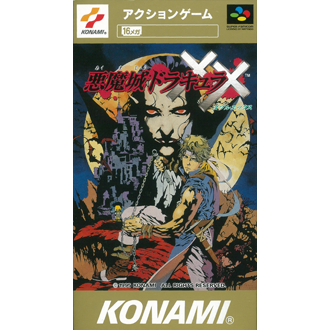悪魔城ドラキュラXX
【あくまじょうどらきゅら だぶるえっくす】
|
ジャンル
|
アクション
|
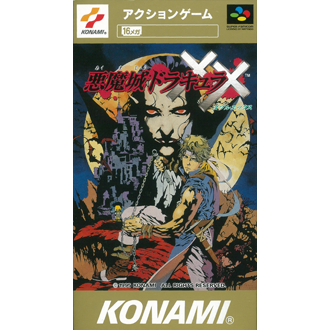
|
|
対応機種
|
スーパーファミコン
|
|
メディア
|
16MbitROMカートリッジ
|
|
発売・開発元
|
コナミ
|
|
発売日
|
1995年7月21日
|
|
定価
|
9,800円(税別)
|
|
プレイ人数
|
1人
|
|
配信
|
バーチャルコンソール
【WiiU】2014年4月23日/823円
【New3DS】2017年8月23日/823円
|
|
書換
|
ニンテンドウパワー
1997年9月30日/1,000円/F×4・B×0
|
|
判定
|
なし
|
|
ポイント
|
ジャンプ操作感に癖がある
マリアプレイなどPCE版から色々削られた
PCE版と別物として見ればそこまで悪くない
|
|
悪魔城ドラキュラシリーズリンク
|
概要
PCエンジンで人気を博した『悪魔城ドラキュラX 血の輪廻』のリメイク移植作品。
リメイク移植といっても共通点は主人公リヒター・ベルモンド、アイテムクラッシュやステージ分岐システム、敵キャラクターのドット絵(新規はボス5体のみ)、BGM(本作での新曲もある)、ドラキュラ討伐という基本ストーリー、といったいわば素材の部分。
ステージデザイン・構成などはほとんど別物であり、キャラクターイラストに山田章博氏を起用するなど、『血の輪廻』を素材に再作成されたオリジナル作品ともいえる。
開発は『血の輪廻』を担当した東京開発部ではなく、従来のドラキュラシリーズを開発してきた神戸開発部が担当している。
ちなみに『血の輪廻』は当時、宗教上の問題などで海外では発売できず、後の『悪魔城ドラキュラ Xクロニクル』が発売されるまでは、本作が海外における『血の輪廻』という扱いだった(実際、北米版のタイトルは『Castlevania Dracula X』である)。
パッケージやキャラクターデザインも北米版においては『血の輪廻』のものが用いられている(欧州版については本作に準拠)。
本作はSFCアクションゲームの中では普通の出来だが、オリジナルである『血の輪廻』のPCエンジン・CD-ROMゲームならではの魅力的な部分が、SFCというハード性能の制約のため削除及び変更されており、微妙扱いもされている。しかし逆に本作にしかない演出や効果音の向上などもあり、一長一短である。
特徴
基本的なゲームシステムは『血の輪廻』と同様なので割愛。以下の点が異なる。
-
オープニングやエンディングなどは本作オリジナルのグラフィック絵とBGMが使われている。
-
『血の輪廻』のアニメ絵では海外に受け入れられないと判断されたためか、パッケージやデモ画像の絵には上述の通りの山田氏を起用している。
-
…が、肝心の北米版のパッケージが『血の輪廻』と同じもので、説明書などにはアニメ絵も載せられていたりする。
-
本作ではアネットのデザインが紫髪から金髪に(ゲーム中のドット絵はラウラの流用)、マリアがロングヘアーからショートカットに変更されている(イラストのみ服も変更)。なお『血の輪廻』の真のリメイク作品である『Xクロニクル』では、おおむね本作のデザインが採用されている。
-
クロスと時計のアイテムクラッシュは本作でしか見られないモーションになっている上に後者のアイテムクラッシュは効果までも変更(通常よりも長めに時を止める→一定時間バリアを貼る)されている。
-
鞭の先端付近をアーマーナイトに当てると何故かガードを貫通してしまう。本作のアーマーナイトの配置はこの仕様を踏まえた物になっている。
-
2人の女性の救出状況によってエンディングの内容が変化するマルチエンディングを採用。
-
救出の成否が後のステージに影響を与えることもあり、このシステムは『Xクロニクル』にも採用された。
評価点
-
効果音
-
『血の輪廻』ではPCエンジンの内蔵音源を使用していたために鞭の音が「プニップニッ」という気の抜ける攻撃音になる事もあったが、今作では全編通して「ビシィッ!」とハッキリと聴こえる痛快な攻撃音に変わっている。
-
攻撃音と同様に鞭の音に鎖の効果音が追加され、より鎖状の鞭を振っているという感じが出ており演出面がアップしている。
-
良質なBGM群
-
本作のBGMはSFC作品としては相当頑張ってる方で、SFC後期の作品のためか音質も良い。
-
加えて、ステージマップ画面やステージクリアといったSFC移植に伴い新曲も追加され更にゲームを盛り上げている。
-
やりごたえのある難易度
-
本作はSFCへの移植に当たって全てのステージの構成が変更されたが、比較的難易度が低めだった『血の輪廻』と比較的して難易度が高くなっている。
-
また、本作のボス戦も初見殺しが多く、SFC初代と比較してゴリ押しが通用しないボスが多い。PCEからの引継ぎ及び新規ボス共にパターンが存在し、やり込みが攻略につながる余地はある。
賛否両論点
-
操作性
-
本作では大ジャンプ(十字ボタン+ジャンプボタン)と小ジャンプ(ジャンプボタン→十字ボタン)の使い分けが可能となっている。ステージも明らかにこの二つのジャンプを使い分ける構造になっているため、このジャンプアクションを使いこなせないと攻略にかなり苦労する事になる。しかし、使いこなせれば攻略方法もかなり変わってくるため、本作の個性であるともいえる。
-
それに加え、ジャンプの横方向への移動速度が歩行よりも速くなるという他のシリーズとは違った癖があり、ジャンプ滞空もふわっとしていて慣れるまで戸惑う。このため、大ジャンプで移動した際に素早く迫ってくる敵(コウモリ、スケルトン、メデューサ等)がスクロールによって登場&接敵してくる場合には、ジャンプの制御が効かなくなることから対処できずに被ダメージを貰うといったことが非常に多い。
-
ちなみに、全編バック転だけで進むのがもっとも速く進める。
-
ジャンプを抜きにしても、伝統仕様に戻った攻撃方法はSFC初代を遊んでから見た場合明らかに劣化と捉えられなくもない。
-
グラフィック
-
『血の輪廻』の鮮やかな色合いから、前回SFC版に若干だけ近づき全体的に落ち着いたゴシック調の色合いになった。透過+ラスタースクロールで炎の揺らめきを表現していたり、時計塔など『血の輪廻』よりもグラフィック(雰囲気)が良くなったステージもある。
-
ハード性能上、PCEより同時に使える色数が多いため、色鮮やかなステージもあったりする
-
ゲームの難易度は全体的に上昇
-
本作の難易度は当時発売されたシリーズ作の中でも難しい部類に相当しており、硬派なイラスト群の存在と相まってライトユーザーお断りな作品と言わざるを得ないだろう。
-
シリーズの中では比較的低難易度でアニメ絵だった「血の輪廻」とは真逆である。
-
BGM
-
ハード性能の違い故仕方がないことだが、どうしてもCD-DAである『血の輪廻』に比べると劣る部分がある。但し本作のBGMは、一部音の変更があるとはいえ『血の輪廻』 のBGMがSFC音源によって高い再現度でアレンジされており、アレンジ自体の完成度は高い。
-
特に「幽霊船の絵」「Op.13」「Cemetery」「獄幻界乱舞」「巣窟」はかなり原曲に近いアレンジとなっており、CD音源である『血の輪廻』の雰囲気を崩さずにアレンジされている。
-
「乾坤の血族」は『血の輪廻』 版に比べ、イントロ部分のスラップベースのパートが若干変化しているが、ベースの音源自体は非常に高い完成度で、パートの変化に関しても寧ろXX版の方が好みという声もある。
-
ステージ構成が変わったため、(致し方ないとはいえ)「幽霊船の絵」「Op.13」など曲名がステージと合っていないものも存在している。
-
CD-DA曲の「Overture」、「鎮魂歌」、「Cross a Fear」、「Slash」、「聖者の行進」、「Mary Samba」の6つは未採用。ただし新曲も6つなので差し引きゼロ(?)。その他、ステージクリアやゲームオーバーBGMの差し替えもある。
-
収録楽曲のうちFC版初代から存在する「Vampire Killer」は『血の輪廻』バージョン準拠の、イントロ部分に初代原曲のサビ部分が来るアレンジとなっているため好みが分かれる。
-
しかしながら曲の再現度は高く、さほど変なアレンジでもないため前述の通りSFC音源アレンジと考えればそこまで悪くない。SFC後期作だけあり新規曲も含め高クオリティに仕上がっている。
その他
-
前述の通り、エンディングは一枚絵による淡々としたものになっている。
-
セリフも何もなく、本当に一枚絵が次々と表示されていくだけのものなのだが、BGMとの相乗効果もあって言葉にはできないくらい深い印象を心に刻んでくれる。
問題点
-
操作周りの劣化
SFC版『悪魔城ドラキュラ』で実装されていた『8方向への鞭攻撃』『鞭の振り回し』『ジャンプの軌道修正』が尽くオミットされている。
何故これらの要素がオミットされたかは不明だが、とにかく難易度の上昇を手伝っている事は否定出来ない。
『血の輪廻』との比較
-
マリアが使えない
-
特徴の項目で記載した通り、12歳にして主人公リヒターよりも強かったマリアプレイがばっさりとカットされており、プレイキャラはリヒターのみ。性能、キャラ人気共に高かっただけに、惜しいと思うプレイヤーもいる。
-
なお、マリアというキャラクター自体は救出できるキャラとして存在するが、アネットの妹と設定が変更されている。このため、マリア・ラーネッドと本作のマリアが同一人物なのかは未だにはっきりとはされていない。
-
ステージ、敵の削減
-
ステージ数は『血の輪廻』13に対し本作は9に減少。
-
敵もボスを中心にかなり削減されており、ドラキュラの参謀役として登場したシャフトは登場せず、ボスラッシュステージもなくなった。
-
死神は登場するが、ルートの進め方次第では遭遇しないこともある。
-
死神が登場しないルートでは、カーミラの下僕のラウラのグラフィックを流用されたアネットにカーミラが憑依合体してシャフトのような攻撃をしてくるという、カーミラ&ラウラとシャフトの要素を1体に圧縮したようなボスが登場する。
-
ビジュアルシーン、ボイスの削除
-
容量の関係上、当然ながらアニメーションデモシーンのキャラ救出や伯爵の会話は削除され、代わりに一枚絵でこれが表現されている。またテラ、イリスの2人の救出キャラも削除された。
-
その他
-
輪廻同様にダメージ後の無敵時間が極端に短い。コウモリなど、触れると連続ダメージが確定するパターンも多々存在する。
-
マリア・アネット救出ルートのゲームバランスが悪い。
というのも、マリアが囚われているステージ4で使用するサブウェポンの「鍵」は前のステージから持ち越す必要がある。そのうえマリアを救出した後もステージボス直前の部屋にあるアネットが囚われているステージ5'に分岐する扉の地点、つまりほぼステージの冒頭から最後まで鍵を保持しつつ進まなければならない。道中で別のサブウェポンに切り替えたり途中でミスしたりして鍵を失うと当然バッドエンド確定。
しかも鍵自体も(アイテムクラッシュ時含め)ハート消費量こそゼロだがリーチが1キャラ半と極端に短く、アイテムクラッシュも攻撃判定を出しながら無敵のポーズを取るだけと性能が低い関係で緊急回避手段にしかならない。このため、実質的にムチ縛りで例のステージを攻略しなければならない事もバランスの悪さに拍車を掛けている。お前はクリストファーか。
-
とはいえ、そのルート自体は中~上級者向けの難し目のステージであることから、単にエンディングのみを目指すのなら素直に別のルートを進めば良い。また、同ステージも鍵以外のサブウェポンを駆使しつつ進めばボスまで辿り着ける難易度になっていたり、ステージクリア時のパスワードに所持しているサブウェポンが記録されるのがせめてもの救いか。
-
また、上記の鍵のアイテムクラッシュも全く役に立たない訳ではなく、長時間の無敵回避&攻撃判定を生かし上方の敵を安全に処理出来るなどメリットも多い。何よりもハート無消費でアイテムクラッシュを行えるのはやはり恩恵が大きい。
-
ちなみにこれと同様のシチュエーションは輪廻の頃から存在するが、こちらの場合は該当する箇所がステージの一部分程度と非常に短く問題視はされなかった。
-
シリーズでは珍しく、伯爵戦のステージが穴だらけで非常に足場が悪い。そのため、「シリーズでもっとも卑怯な伯爵」「真のラスボスは穴」とネタにされる事もある。
-
ドラキュラはいつも通り第2形態まであるのだが、第1形態は「姿を完全に見せてから攻撃終了するまでのわずかな時間内に」「非常に当たり判定の狭い頭に」攻撃を当てる必要がある。現れてから場所を移動するのでは全く間に合わないので基本的に特定の場所でガン待ちしつつ、画面外からの攻撃を適当に避け、たまに画面内に出現したら一瞬のスキで攻撃するだけと非常に単調で時間がかかる。第2形態は当たり判定が全身になる代わりに攻撃が激化し避けづらくなるので速攻を決めるのが無難。速攻だとそう難しくもなく敵が2回行動する前に倒すこともでき、とても味気ない。
総評
PCエンジンの『血の輪廻』を知る者にとってはマイナーチェンジともいえる作品。一方で、SFC版の続きとして遊んだ場合はゲーム性の劣化と言う印象を抱きかねない作品でもある。
『血の輪廻』と比較しなければ、問題に成りうる点はジャンプを主とした操作性の違いや時間がかかりテンポの悪いラスボス戦、高めの難易度だろう。
ハードの限界に迫る程のグラフィック表現技術及び音楽面などSFC作品としては優れている点も多く、むしろPCエンジンのギャルゲー風潮に乗った『血の輪廻』の軟派な部分はごっそりスポイルされているので、硬派ファンには好評である。
余談
-
2014年4月23日よりWii Uのバーチャルコンソールにて配信開始。若干のプレミア化などの被りを受けてプレイが困難になっていた状況からは脱した。
-
本作のBGMを集めたサウンドトラック発売の要望も少なくないのだが、2010年03月24日に発売された「悪魔城ドラキュラ Best Music Collections BOX」には収録されず、2021年12月15日に発売された『ミュージックフロム悪魔城ドラキュラ黒』が初収録となった。また聞くだけであれば上のアドバンスコレクションのミュージックプレイヤー機能を使うという手もある。
-
後に『血の輪廻』の新たなリメイクとして『悪魔城ドラキュラ Xクロニクル』が発売されている。
-
全体的に『血の輪廻』に忠実なリメイクであるが、キャラクターデザインはどちらかというと本作に近い作風になっており、また一部のストーリー展開は本作のものが取り入れられているなど、本作の存在にもかなり配慮されたリメイクとなっている。
最終更新:2024年03月19日 20:02