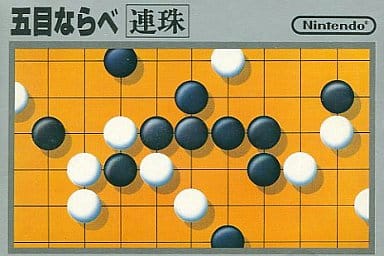五目ならべ 連珠
【ごもくならべ れんじゅ】
|
ジャンル
|
テーブル(五目ならべ)
|
|
|
対応機種
|
ファミリーコンピュータ
|
|
発売・開発元
|
任天堂
|
|
発売日
|
1983年8月27日
|
|
配信
|
バーチャルコンソール
【Wii】2006年12月2日/500Wiiポイント(税5%込)
【WiiU】2014年10月29日/524円(税10%込)
|
|
定価
|
3,800円→4,500円
|
|
プレイ人数
|
1~2人
|
|
判定
|
なし
|
|
ポイント
|
任天堂の無印タイトル系では最も地味
据置ゲーム機に限れば10年以上も唯一の存在であり続けた
|
概要
ファミコン初期に代表される「現実にアナログで行われていたゲームをコンピュータゲーム化しそのままの名前をタイトルにした」任天堂の無印タイトルゲームの1つ。
パッケージだけ見ると囲碁のゲームに見えるかもしれないが、タイトルに「五目ならべ」と明記してあるため、そこで混同されることはなかったであろう。
同様の無印タイトル『麻雀』と同日発売の準ローンチタイトルで、大人を狙って発売されたものである。
このような任天堂の無印系タイトルのゲームは後に発売される『ベースボール』『テニス』などスポーツ系が主流となるが、同日発売の上記と並んでファミコンにおける同様のタイトルのゲームとしては初作品である。
ルールなどは、現実通りの基本ルールに準じている。
またタイトルのBGMや効果音は『麻雀』と併用されている。
内容
-
基本ルールそのままで先に五つ石を並べた方が勝ちとなる。
-
ただし両脇に何もなく四つが並んだ「四」や「四・四(白のみ)」「四・三」など片方が防げない形が成立すれば、その場で勝ちが決まる(一部例外あり)。
-
先手が黒、後手が白。
-
ただし最初の三手(黒2つ・白1つ)は19通りの特定パターンの中から自動で行われるのでプレイヤー操作では白が先に打つことになる。
-
先手の黒のみ「三・三」「四・四」「長連(六つ以上が並ぶ)」の禁手が適用され、これが成立すると負けとなる。
-
後手の白に関しては禁手はなく「四・四」「長連(表記上は「五連」扱い)」もそのまま勝ちとなるが「三・三」のみその時点では勝ちにはならず次の手で「四・三」等の形にしないと勝ちが成立しない。
-
黒にのみ禁手が設けられているのは、連珠においては先手が圧倒的に有利だからである。これらの禁手を設けてなお先手が有利とされる。
-
基本的に6本勝負となり最初は1Pが黒、2Pが白。
-
次の回ではそれが逆となるので、双方のプレイヤーが公平に黒と白を3回ずつ行う。
-
つまり4勝以上すれば勝利と言うことになる。3勝3敗の場合は引分けとして終了する。
-
決着がつかずに盤面全部を埋め尽くすと「引分け再試合」になり、この試合はノーカウントとなる。
-
ゲームの最初に難易度を初級・中級・上級のいずれかから選べるが、思考自体はいずれも同じ。基本は中級で初級・上級はそれぞれに追加要素がある形。
-
「初級」
-
「上級」
-
制限時間があり、時間内に手を打てないと「時間切れ」で負け扱いになる。
最初は90秒で、基本減算のみだが20秒未満になった場合、以後20秒となる。
評価点
-
基本ルールはしっかり網羅されており、コンピュータの思考時間も短いのでスムーズな展開で進められる。
-
現実の五目並べなど少年層は普通に五つ並ぶまで淡々と続けていたが、これにより「四・四」「四・三」などを知ることができる。
-
しかも、それをプレーしながら覚えられるので書物などを読むより飲み込みやすい。
問題点
-
誤操作での投了をしやすい。
-
Bボタン1つで投了できてしまうので、ついうっかり触れただけで負けになるのは少々手軽すぎる。
-
例えば「五」が成立して、本来なら勝利が確定している状況でも点滅している時にうっかりBを押しただけで負けになる。
-
せめて一度ぐらい確認があっても良かっただろう。
-
滅多にないが、盤面を埋め尽くすまで引分けが成立しないので、お互い勝ちがなくなった後でも埋める作業をやらされる。
-
これは当時のファミコンレベルでは難しかったので仕方がないが。
-
これはファミコンで共通だがCPUの思考が弱く、本来のターゲット層である大人からすれば相手にならない。
-
『麻雀』は配牌に運が絡むが、五目ならべや将棋といったものはそれがないのでその弱さが如実に現れる。
総評
スポーツを含めた無印タイトルの中では売上本数では伸び悩んだものの、現実の五目ならべをそのままゲーム化したもので、派手さはないものの無難に楽しみながらルールを理解できる。
ファミコンのみならずPCエンジンやメガドライブでも以後五目ならべに該当するゲームが発売されなかったが、裏を返せば長い間本作一本で五目並べをゲームとして楽しめる出来だったと言えよう。
余談
-
同日発売の無印タイトルのテーブルゲーム『麻雀』は後にディスクシステムのローンチ(1986年2月21日)として片面ソフトとして移植され、他にも『テニス』『サッカー』など無印タイトルのゲームがゴッソリ移植された。
-
1989年5月30日には書換え専用として『ピンボール』も後追い移植されたことで、ファミコン草創期の任天堂無印タイトル系のテーブルゲームでディスクシステムに移植されなかった唯一のソフトとなった。
-
ファミコンソフトで五目並べはこれ一本のみに終わった。
-
1990年2月23日にゲームボーイソフト『対局連珠』がトーワチキから発売。
-
1994年3月25日にまるで本作のスーパーファミコン版のようなタイトル『スーパー五目ならべ連珠』が発売されているが、こちらはナグザットによるもので本作との関連性はまったくない。
-
ゲーム内容は1981年に日本物産がリリースしたアーケードゲーム『五目並べ 連珠』とほぼ同一であるが関連性は明確にされていない。
最終更新:2025年01月02日 09:31