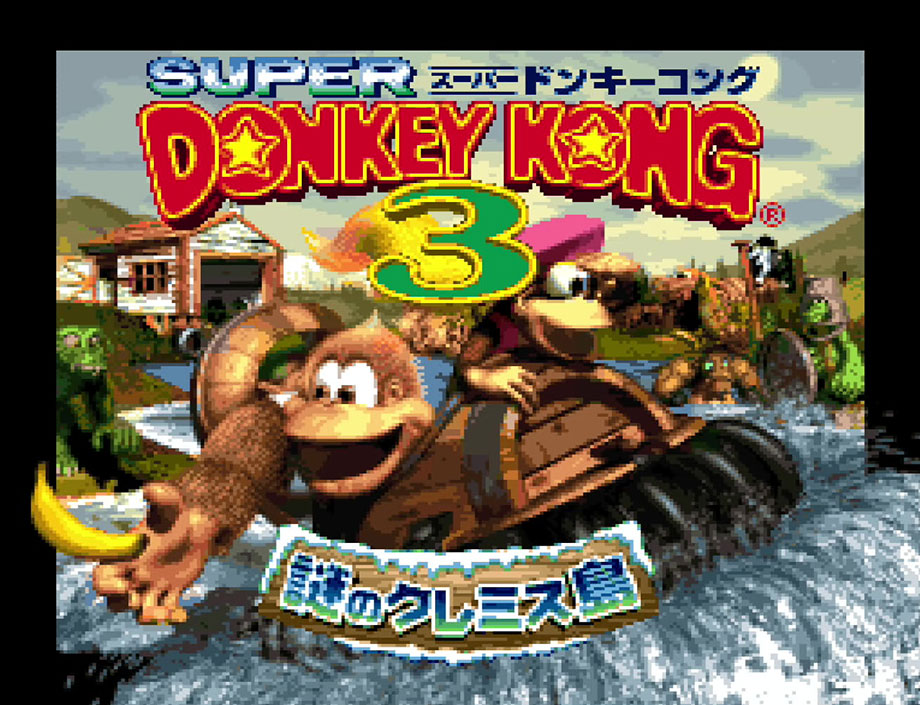スーパードンキーコング3 謎のクレミス島
【すーぱーどんきーこんぐすりー なぞのくれみすとう】
|
ジャンル
|
アクション
|
高解像度で見る 裏を見る
|
|
対応機種
|
スーパーファミコン
|
|
発売元
|
任天堂
|
|
発売元
|
レア
|
|
発売日
|
1996年11月23日
|
|
定価
|
6,800円
|
|
プレイ人数
|
【SFC/Wii/WiiU】1~2人
【New3DS】1人
|
|
セーブデータ
|
3個(バッテリーバックアップ)
|
|
レーティング
|
CERO:A(全年齢対象)
※バーチャルコンソール版より付加
|
|
配信
|
バーチャルコンソール
【Wii】2008年10月21日/800Wiiポイント(税5%込)
【WiiU】2014年11月26日/823円(税8%込)
【New3DS】2016年5月9日/823円(税8%込)
|
|
書換
|
ニンテンドウパワー
1997年9月30日/1,000円/F×8・B×1
|
|
判定
|
良作
|
|
ポイント
|
完成度の高いシリーズ最終作
前2作とは少しだけ雰囲気が異なる
|
|
ドンキーコングシリーズ・関連作品リンク
|
概要
任天堂・レア社のタッグで制作されたスーパードンキーコングシリーズの第3弾。
前作『2』に登場したディクシーコングと、新キャラクターのディンキーコングが主人公を務める。
ストーリー
キャプテンクルールとの戦いに勝ったドンキーたちは、DKアイランドでのんびりと過ごしていました。
ある朝、ディクシーがディディーの部屋を訪れると、ディディーの姿はなく、走り書きのメモだけが置いてありました。
ディクシーへ
ドンキーとしまをたんけんしてくる。あす、もどる。
ディディーより
しかし、2日経ってもドンキーとディディーは帰ってこない。
心配になったディクシーはクレミス島へ向かい、リンクリーとファンキーに話を聞くことにした。
リンクリーによると、ドンキーとディディーの姿は見かけたけれど、行き先は聞いていないとのこと。
ファンキーを訪ねると、親せきのディンキーコングを連れていくように言われます。
ディンキーは赤ちゃんコングですが、きっと冒険の大きな助けとなるでしょう。
ディクシーとディンキーは謎につつまれたクレミス島でドンキーとディディーを見つけ出すため冒険に出発しました。
特徴および前作からの変更点
「チームアップ」の性能の変更
-
今作のチームアップはディクシーかディンキーのどちらを持ち上げるかでアクション内容が大きく変化する。
-
ディンキーがディクシーを持ち上げた場合、歩行スピードやジャンプ力がやや低下するが、前作『2』と同等の使い勝手で遠くまで投げることができる。
-
ディクシーがディンキーを持ち上げた場合、歩行スピードやジャンプ力が大幅に低下し、遠くに投げることもできない。その代わり特定の地点に投げ落とすことで、ディンキーの体重を生かし地面に穴を開けたり埋まっているアイテムを掘り起こすことができる。また、使う必要がある場面はないが、壁にぶつけて転がってきたディンキーに乗って移動できる「ローリングプレイ」が行える。
アニマルフレンドの変更
-
前作のアニマルフレンドのうちランビ・ラトリー・クラッパー・グリマーがリストラされ、代わりに「エリー」と「パリー」(+α)が追加された。アニマルフレンドが登場する機会も多く、アニマルバレルで変身するステージも増えた。
-
エリー:象のアニマルフレンド。パワーはないが、以下のようなさまざまなアクションが可能。エリーのアクションを主体にしたステージも多く、アニマルフレンドの中で最も多く登場する。
-
タルを持ち上げて投げることができる。鼻で離れたところにあるタルを吸い寄せることも可能。
-
滝や水辺の水を吸い込み、発射して攻撃できる。使えるのは一部のステージのみで、使えるステージでは画面右下にゲージが表示される。
-
ネズミが苦手で、スニークという敵を明るい場所で見ると一目散に逃げ出す。暗い場所ならスニークを踏んで倒せる。ロストワールドではスニークに驚いて暴走するエリーを操作するステージもある。
-
エンガード・スクイッター・スコークス:基本的には前作と同じ。スクイッターは敵やタルを踏むことができるようになった。
-
コークス:アニマルバレルによる変身でのみ登場。今作ではスコークス同様、自由に飛ぶことができる。卵を吐くことはできないが、代わりにタルを足でつかんで運ぶことができる。
-
パリー:小鳥のアニマルフレンド。コングたちの頭上を一定距離を保って飛び、アイテムを取ってくれる。アイテムを持つ鳥「ブーティバード」程度の敵しか倒せず、主に蜂の敵である「バズ」にぶつかると逃げてしまう。禁止サインまで連れて行くと他のアニマルよりも貴重なアイテムを残してくれる。ボーナスバレルに変わることもある。
ディクシーのアニメーションの変更
-
前作よりもディクシーのダッシュした時とロープで移動している時のアニメーションが鈍化している。操作性には全く問題はない。
ボーナスステージの変更
-
新ルール「バナナを15つかめ!」が登場。
-
決められた数か所からランダムに現れる緑色のバナナを制限時間以内に15本集めるという内容。各ステージのギミックを利用したり避けながら集めることを要求される。
-
ボーナスステージの入口はすべてボーナスバレルに変更。
-
「壁に空いている、あるいはプレイヤーが開ける穴から入る」「弾を込めた大砲から撃ち出される」形式は無くなった。
-
主に屋内ステージではバレルに入ると発射ではなくワープするような演出がとられる。
-
ボーナスステージの数は基本的に1コースにつき2個に統一された。
-
ただし、ロストワールドの1、3、4番目のコースのみボーナスステージが3個ある。また最終コースにボーナスステージは存在しない。
評価点
シリーズ最高のグラフィック
-
「スーパーファミコン史上最高のグラフィック」を自ら謳うだけあって、シリーズでは勿論、全スーファミソフトの中でもトップクラスに描き込まれたグラフィックを誇る。
-
前作までのほとんどのマップ画面の背景は動きのない一枚絵だったが、今作では全てのマップ画面に揺れる水面や流れ落ちる滝、ほら穴から漏れ出る光などのアニメーションが付けられており、リアリティの向上に一役買っている。
-
ステージ構成も巨大な木の中や崖など雄大な自然を舞台にしたものから、工場やダクトの中といった近代的なものまで様々。
-
特に桟橋、川辺、湖、滝…と水をテーマにした景観が多く、過去作とはまた違った趣がある。
やりこみ要素のパワーアップ
-
前作にはない新要素として、各種イベントアイテムが登場。各ステージのボス打倒により獲得するアイテムをファンキーコングに渡すことが新ステージ到達への鍵となる他、
クレミス島の各地に住むクマ達の頼まれごとに関するアイテムは主に後述の「バナナバード」収集に関わる。
-
「ボーナスステージ」「DKコイン」が前作に引き続き登場。
-
各ステージに隠されたボーナスステージをクリアすると「ボーナスコイン」が入手できる。前作のクレムコインに相当する収集物であり、隠しエリアのステージを開放するために必要となる。
-
今作の「DKコイン」は各ステージに1体だけ配置されている「コイン」という
そのまんまな名前の敵を倒して入手する。
-
コインは攻撃手段を持たずその場から微動だにしないのだが、あらゆる攻撃を防ぐ盾を常にコング達のいる方向に構えており、正面からの攻撃が全く通用しない。ヘルメットを装備しているので、上からの攻撃も無効。
-
そのため、コインを倒すには鋼鉄製タンクを壁に当てての反射などを利用してコインの背面に当たるよう攻撃しなくてはならず、コインの攻略法が一種の謎解きになっている。
-
ちなみに、今作の最大達成率は103%(後述のチートモードを除く)。
-
本作にもレア社おなじみの「チートモード」が存在する。
-
データ選択画面でコマンドを入力したあと特定のチートコードを入力すると発動する。チートコードの中には「服の色を変える」「ボーナスステージのBGM・星・緑バナナをクリスマス風に変える」といったお遊び的なものから「DKバレルの数が減る」「常にコング2匹そろった状態でスタートするかわりに、DKバレル、コンティニューバレルが消滅する」というハードモード2種(この状態でクリアすると達成率が上がる)まで、さまざまなものがある。
練りこまれたステージ構成
-
相変わらず高めの難易度設定に加え、ステージごとに凝ったギミックが用意されており、以下のステージが楽しくもトラウマなステージとしてよく名前が挙げられる。また、ボーナスステージも一ひねり加えられており、一筋縄ではいかなくなっている。
-
後ろからついてくる魚「ニブラ」の機嫌をとるように敵を食べさせながら進む「はらペコ ニブラ」
-
下から迫ってくる巨大ノコギリに追いかけられながら木の中をのぼっていく「ハラハラのこぎり」
-
謎のガスが充満していて、低重力を活用して進んでいく「ふわふわダクト」
-
スクイッターに変身して正体不明の照準に撃たれないように工場地帯を進む「ねらわれたスクイッター」
-
ステージ全域で落雷が常時一定間隔で襲いかかり、逃げこんだ水中に落雷してもミスになる「カミナリに気をつけろ」
-
キャラの操作が左右反転の状態で進まなければならない「さかさまパイプライン」
-
左右逆の操作+後半の高速スクロールが過酷な「ポンコツロケットでゴー」
-
ボス戦は通常アクションのステージだけでなく、雪合戦を行うステージがある。
良質なBGM
-
今作のBGMは主にイーヴリン・フィッシャー氏が担当しており、デヴィッド・ワイズ氏が担当した前作とは雰囲気が異なる(わずかだがワイズ氏が作曲した曲もある)が、軽快なメロディーが楽しい『Stilt Village』(湖ステージ)やエレキギターが唸る『Nuts and Bolts』(工場ステージ)、「ハラハラのこぎり」でおなじみの『Treetop Tumble』(森ステージ)など、いずれも良曲揃いである。
前作からの改善点
-
セーブポイントは無料かつゲーム開始地点にも存在する。さらにエリアと全体MAPを自由に行き来できるため、「セーブポイントまでのステージが難しくて詰む」ことがなくなった。
-
相変わらず残機は保存できないが、買い物などに必要なベアーコインがセーブに反映されるようになった。
-
スワンキーのミニゲームに何度でも挑戦可能になった。
-
今作ではボールを的にぶつける「ポイポイゲーム」のテントを経営しており、そこで対戦相手のクランキーとの勝負に勝つとバナナやベアーコインが入手できる。負けても景品をくれるのは良心的。
-
種目は3種類。的に当てるたびにランプが自分の方に寄っていき、先に自分の方に寄せきった方が勝ちとなる「こっちにポイポイ」、25点先取で勝利となる「ポイポイ25」、先にミスした方が負けとなる「スーパーポイポイ」がある。スーパーポイポイ以外は制限時間60秒で、時間切れの場合は判定で勝敗が決まる。
-
なお、クランキーはこれまでのシリーズ通り台詞テキストのパターンが非常に豊富。彼に負けると調子に乗って煽られるが、勝つと大いに悔しがって負け惜しみを吐き捨てる。この勝利後のパターンはテキスト以外にもいろいろあり、これを全部見ようと勝負を仕掛けるのも面白い。
-
前二作には「暗いステージをライトで灯すアニマル」が振り向くと、画面がフラッシュしてプレイヤーの目に優しくないという問題点があったが、本作では照らされ方の変更により改善されている。
問題点
雰囲気の路線変更
-
ステージクリア毎の爽快感が薄い。
-
本作のコースクリア時の演出が「ロープにぶら下がって旗を立てる」という地味な内容に変更され、ジングルもかなり簡潔かつ穏やかな音色となってしまった。
-
前身の『2』を経験したプレイヤーほど「あれ、これでクリア?」と肩透かしな感想になるだろう。メロディそのものは『2』のゴールターゲットのボーナスなしクリアと似たジングルなのだが、ボーナス付クリアと比べて遥かに目立ちにくく、コースによっては音量すらも小さい。
-
ボス戦の撃破演出も同様で、前二作にあった「コング達の勝利のポージング」は本作には無く、撃破報酬のアイテムやコインを取れば、クリアジングルがブツ切り気味になるほどの速度で画面暗転となるため、勝利の達成感や余韻が台無しになっている感が否めない。
-
その上で本作は、倒したボスの見た目にほとんど変化がないケースが多く、爆発や吹き飛ぶなどの視覚的に勝利したことが一目瞭然な演出が減少し、「ボスが目を瞑っただけ」といった手抜き感の漂うボスまで存在することもこの難点に拍車をかけている。
-
前々作『1』の時点で全てのボス戦で、ボスの体躯がきっちり倒れた横で喜びのポージングを取るという敵を懲らしめた感がプレイヤーに十分伝わる演出だっただけに、本作のボス勝利演出はSFC三作の中で最も劣っていると言わざるを得ない所である。
-
新登場の効果音(SE)がいずれも迫力・存在感に乏しい。
-
前作から続投の効果音は変わらず存在感抜群なものの、今作初出の敵やステージギミックにより発する効果音は、一言で言えば全体的に薄味で地味。
-
わかりやすい所では、踏みつけやローリングで小型の敵を倒した際の効果音は前作から比較するとかなり貧相であり迫力が損なわれているといえる。
-
この難点が特に顕著なのがボス戦である。
-
前作『2』では、ボスの攻撃行動の多くが危険性を示す効果音と共に放たれ、避ける必要性をプレイヤーの聴覚にも訴えかける他、ボスへの攻撃が命中した際もしっかりとしたダメージリアクションとそれに負けない派手な効果音で手ごたえを演出するなど、戦闘を盛り上げる優れた音響だった。
それに対し、本作は派手さを抑えたダメージリアクションと地味でささやかな効果音にスケールダウンしており、ボス戦の爽快感も前作から大きく劣化していると言わざるを得ない。裏を返せば『2』で改善された点から逆戻りしているとも言える。
ドンキーコングが空気
-
今作でもドンキーは敵に捕まっているため、ゲーム中にはほとんど登場しない。「キャプテンクルールにトドメを刺す」という見せ場があった前作に比べてさらに存在感が薄くなってしまった。
-
ドンキー同様に本作ではディディーも空気化。一度主役を務めたら次作で降格されてしまうのが当時のレア社の風潮にすら思える。仮に同路線の『スパドン4』が発売していたらならば、ディンキーが主役になってディクシーもまた空気化していたのかもしれない。
-
ただ、ゲーム内でドンキーがテキストで喋ったのは本作が初である。
ディクシーとディンキーの性能差
-
前作同様、ディクシーの空中ポニーテールスピン(いわゆるホバリング)が便利すぎる。対してディンキーは、体格が災いし当たり判定が大きい上に俊敏さに乏しく秀でた部分が少ない。
-
最も性能差が顕著に現れるステージは、着地位置の正確な調整が必要な「コインドーザーのもり」。完全にディクシーでプレイすることを前提とした難易度となっている。
-
他にも、追跡してくる敵をかわしながらロープを移動するコース「クラスプロープ」「クレバスをのぼれ」や動きが鈍くなる水中ステージは、ディンキーにとってつらいステージとなる。「さいきょうのふたご」などは、敵のジャンプを避けるために下をくぐって立ち止まる際、ここで敵に背を向けないと、手を踏まれるなどの事故も。
-
前作でディクシーと共に冒険したディディーはわずかにスピードなどの能力が高く、タイムアタックに挑戦する層などからは必要とされていたのだが、体格が大きいディンキーのメリットは水切りジャンプと踏みつけの威力の高さ、タルの投げやすさぐらいしかない。
-
おそらく最大の個性であろう「水切りジャンプ」も使うことを想定したと思われる場所が3つしかない。トドメとばかりに、実はそれらのポイントも水切りを使わずとも少し頑張れば到達可能だったりする。
-
ローリングアタックで敵を倒した際の判定持続時間の長さなど、使いこなすと重要になる点はある。これはディクシーの性能が一部前作より落ちていることも一因。
操作キャラの入れ替えの問題
-
コングが2匹揃っている時にセレクトボタンで行うキャラ入れ替えが、時折うまく出来ない不具合がある。
-
狭い足場などでディクシーとディンキーがほぼ同じ位置に立っていると入れ替えが出来ない。この場合自キャラの位置を少しズラして背後にパートナーを立たせる必要がある。
-
また恐らくバグだが、ディンキーを操作している時に、ディクシーが地上にいるのにもかかわらず落下しているモーションになる事があり、その場合も操作キャラを変更することができない。
このディクシーのモーションバグはかなりの頻度で起こる。
ボーナスステージの難しさ
-
今作のボーナスステージは入る条件がシビアなものが多い。
-
特に前述のアニマルフレンド「パリー」がボーナスバレルに変化するステージの場合、完全クリアを目指しているプレイヤーは、パリーを失った際にはステージ攻略からやり直さなければならない。また、パリーの箱の場所へ後戻り不可能なステージの場合はボーナスステージ自体もやり直しができず、この場合もステージ攻略が最初からのやり直しとなってしまう。
-
『2』のクランキーの小屋のような、コインを支払ってボーナスバレル・DKコインのヒントを購入するといった情報提供は本作には存在せず、自力でのコンプリートが非常に難しい。
-
にもかかわらず、真の最終ボスと戦うためにはゲーム内のすべてのボーナスコインを集めきる必要がある。
-
ただし、水中ステージや強制スクロールステージではゴール付近に「コイン」がいるケースがほとんどで、倒し方も捻りが無いため攻略情報は意味が無い。
やりこみ要素「バナナバード」がアクションゲームと無関係
-
本作のやりこみ要素として、各地のほら穴に封印されていたりクマに飼われていたりする「バナナバードの収集」があるのだが、バナナバードは全てフィールドマップ上に隠されており、ボーナスステージやDKコインのようにコース中に隠されているわけではない。
-
ほら穴のミニゲームはいわゆる「サイモン」をやらされるだけ。クマに飼われているバナナバードも、所定のアイテムを渡すなどにより、アクションを介さず会話するだけで獲得される。
-
こうしてバナナバードが集まったとしても、ステージ解放といった冒険への恩恵は無く、真のエンディングの発生条件に関わるのみである。結果、バナナバード収集の方法・恩恵共にアクションと無関係な要素のみで完結しており、アクションゲームとしての楽しさは全く伴っていない。
賛否両論点
-
全体の雰囲気が前作までと比べ若干洋ゲーチックになった。
-
特に敵キャラクターについては前2作からほぼ完全に一新され、「ジンガー」などお馴染みだった敵キャラも似た役割のキャラクターに置き換えられている。前2作の敵の多くは、キャラクターチックにアレンジされながらもデザイン自体はリアルな動物の姿をしていたが、今作の敵は頭でっかちで身体はヒョロヒョロなど、造形からして所謂アメコミ調を感じさせるものとなっている。
-
そのほかには以下のような点が挙げられる。
-
前作までのクレムリン軍団の配色が茶色、灰色、くすんだ青や緑などの爬虫類らしいものであったのに対し、今作では緑(コブル、コプター、ノッカ、コイン、緑バズ)・青(クランプル)・黄色(リコイル)・ピンク(スキッダ、クリンプ、コインドーザー)・赤(バズーカ、クラスプ、赤バズ)など極彩色の単色になっている。
-
なぜかピエロの顔をした魚「ココ」や大きく血走った目をしたトゲつき二枚貝「リラーチ」など、水中の敵のデザインが不気味。
-
様々な作風から「実質バトルトードの続編では?」という声も。
-
攻撃の正確性を問われるボス戦
-
今作のボスの多くは喰らい判定が小さめに設定されている関係で、前作までで使えた「タルを持った状態で体当たりして確実にダメージを与える」といった戦術があまり通用せず、弱点部位に対して的確な攻撃を行う必要がある。
-
もしも攻撃を外してしまった場合は、次の攻撃タイミングまで直前の攻撃を避ける事になるのだが、攻撃が中々当たらず何度もボスの攻撃を繰り返してしまい、結果的に今作のボス戦では慣れないうちはしんどい思いを抱きやすい。
-
タルを投げてダメージを与えるタイプのボスの場合は、弱点に対して直接タルをぶつけられるディンキーがかなり有利になり、逆に後ろに大きく振りかぶる上に軌道にも癖があるディクシーは不利になりがち。
-
アニマルフレンドの扱い
-
本作では、アニマルバレル(コングが変身する樽)が大半であり、フレンド本人の出番が実はそんなにない。
総評
ボーナスステージの難易度がさらに上昇している、ディクシーに比べディンキーが使い辛い、ゲームの雰囲気が前作までと比べ洋ゲー寄りになった等の難点の他、人によっては気になってしまう部分もあるものの、グラフィックやギミックなどは前作からさらに進化を遂げている。
SFC末期ゆえか一大旋風を巻き起こした前々作に比べ売上本数は半分近くに落としたものの、それでも177万本という凄まじい本数は十分に評価されるべき数字と言えるだろう。
SFC末期を代表する傑作としてスーパードンキーコングシリーズの有終の美を飾る作品となった。
その後の展開
-
前作までと同様、『ドンキーコングGB ディンキーコング&ディクシーコング』というタイトルで、GB向けに本作をアレンジした作品が制作されている。
-
ストーリーからコース設計、ボスの挙動までがほとんど別のゲームとなっている。詳細については当該記事にて。
-
同作は当初『ドンキーコングランド2』としてGB後期に開発されていたが、国内では一端開発中止となってGBC用に作り直された逸話がある。
-
なお、国内版はGBC専用ソフトとして発売される事になったが、北米・欧州ではGB・SGBに対応したソフトとして日本より3年早く(GBCの発売よりも早い)発売された。
-
2005年にGBAに移植された。
-
しかし、BGM・ボイスやミニゲームの差し替え、追加ボスなどのテコ入れがことごとく不評を買う微妙な出来となってしまった。ただし、新規追加されたエリアの完成度は高い。
-
詳細については当該記事にて。
-
2008年10月21日から2012年12月7日の期間、Wiiバーチャルコンソールで配信。
-
2014年11月26日より、Wii Uバーチャルコンソールの配信に合わせて、『1』『2』と共にWiiバーチャルコンソールで配信が再開された。2016年5月9日にはNew3DS向けにも配信。
余談
-
今作はリンクリーコングが存命していた最後の作品で、次回作『ドンキーコング64』では幽霊の姿で登場している。僅か2作品の登場で死亡させられるとは何とも不遇である。
-
この時期は既にN64が発売されてたため、リンクリーのほら穴へ行くとリンクリーが『スーパーマリオ64』で遊んでいるパターンがある。その際BGMが同作のお城のテーマになる。
-
ちなみに、GBAのリメイク版では『1』に登場したキャンディー、『ドンキーコング64』に登場したランキー、タイニー、チャンキーが登場している。
-
ゲーム中、バザー(雑貨屋の熊)との会話で『ゼルダの伝説』のリンクがこの島を訪れたと思われるセリフがある。
-
情報を聞く際、バザーに足元を見られ大金を支払ったようだ。
-
北米版では「ポンコツロケットでゴー」にGパネルが存在せず、KONGパネルが揃わない。欧州版や日本版では修正済。
-
通常プレイでは最後にクリアすることになるステージ「ポンコツロケットでゴー」はステージ名の表記が間違えられやすい。
-
ゲーム内では「ポンコツロケットでゴー!」と表記されているが、この「!」は未クリアのボーナスステージがなくなるとステージ名の後ろに表示されるものであり、ステージ名には含まれない。
このステージにはボーナスステージがないため最初から「!」が表示されていること、さらにステージの名前的に「!」がついていても違和感がないことから、勘違いするプレイヤーが多かった。
-
黒幕の「バロンクルール」は恐妻家という設定があり、表向きのボスとしていた戦闘メカ「カオス」をカミさんの家財道具で作ったというシュールなエピソードが語られる。
曰く、「カミさんのナベやカマをつかってヤツをつくったんだぁ!(I used all her best pots and pans to make him....)」とのこと。
-
スタッフのインタビューによると、このカミさん関連のネタはイギリスのコメディ番組に基づいたジョークであるとの事で、本当に恐妻家なのかはスタッフすら知らないらしい。
-
また、レア社の設定ではSFC三部作のラスボスである三人のクルールは全て同一人物であり、キャプテンクルールもバロンクルールも、キングクルールがただ変装して別の名前を名乗っているだけとの事である。確かに、キング・キャプテン・バロンのどれも名前と言うより称号に近い。
-
一方、当時の小学生向けの雑誌(『小学●年生』に掲載されていたSDK2の漫画というか絵本)や『大乱闘スマッシュブラザーズX』のフィギュアの説明文ではキングクルールとキャプテンクルールが兄弟であると書かれていたりと、ややこしい事になっている。
-
コロコロコミックで連載していた『ウホウホドンキーくん』でも三人とも別人として描かれている。また、同作では上記のジョークとして語られたバロンクルールのカミさんが実際に登場している。
最終更新:2025年06月22日 01:01