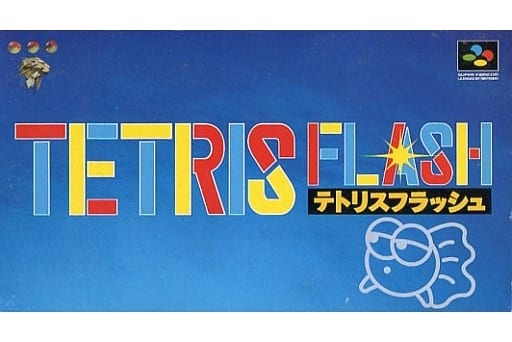テトリスフラッシュ
【てとりすふらっしゅ】
|
ジャンル
|
落ち物パズル
|


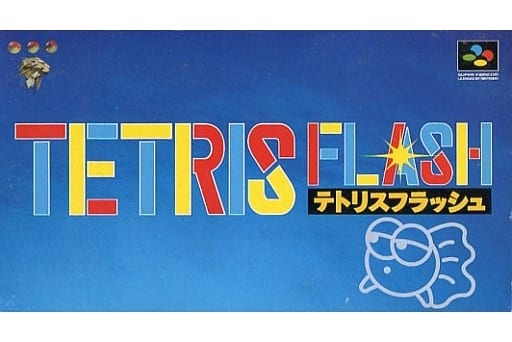
|
|
対応機種
|
ファミリーコンピュータ
ゲームボーイ
スーパーファミコン
|
|
発売元
|
【FC・GB】任天堂
【SFC】BPS
|
|
開発元
|
任天堂
トーセ
|
|
発売日
|
【FC】1993年9月21日
【GB】1994年6月14日
【SFC】1994年7月8日
|
|
定価
|
【FC】5,900円
【GB】2,900円
【SFC】8,800円
|
|
プレイ人数
|
1~2人
|
|
周辺機器
|
【GB】GB専用通信ケーブル対応
|
|
判定
|
なし
|
|
ポイント
|
テトリスとは名ばかりで『ドクターマリオ』の発展形?
テトリスにはない連鎖ができるが『ぷよぷよ』に比べると爽快感ではるかに劣る
テトリスを意識しなければゲーム自体はそれなりに楽しめる出来
|
|
テトリスシリーズ
|
概要
1993年に任天堂から発売されたファミリーコンピュータソフトの落ち物パズルゲーム。通称『テトフラ』。
落ち物パズルでブロックを消すゲーム性から名前に「テトリス」と冠しているが、消し方などはまったく違うためタイトル名をよく問題視されがちな作品である。
実際『テトリス』生みの親であるアレクセイ・パジトノフ氏は関わっておらず共通点は「落ちてくるブロックが4つ構成」「上まで詰まったら終わり」というだけ。
大まかのゲーム性は名前に反して『ドクターマリオ』(1990年、任天堂)に近い。
翌1994年にはゲームボーイ、スーパーファミコン版が発売され、スーパーファミコン版のみBPSによる発売。ゲームボーイ版は同日発売の『ドンキーコング』と並んで『スーパーゲームボーイ』初の対応ソフトとなる。
GB版とSFC版は新しいゲームモードが追加されている。
内容
-
ブロックの区分は3種類で、それぞれに下記の色がある。
-
移動ブロック
プレイヤーが操作するブロックで『テトリス』同様、A・Bボタンで90°ずつ回転させることができる。
中には面ではなく角しか繋がっていないブロックがあり、そのようなブロックは設置すると分離する(分離後も残ったブロックを操作可能)。
-
移動ブロックをタテ・ヨコで6つ一気に消すと、フィールド内にあるその色の移動ブロックがすべて消える。
-
固定ブロック
最初からあるブロックで空中に固定されている。移動ブロックの邪魔になる要因。
-
フラッシュブロック
本作のキーポイントになっているブロックで、モードによって異なる様々な特典が得られる。
-
赤・青・黄色のブロックが『テトリス』の「テトリミノ」状の形で落ちてくる(『ドクターマリオ』では2つのペア)
-
タテ、ヨコに同じ色のブロックが3つ以上並ぶとブロックが消え、その上に乗っているブロックが落ちるので連鎖消しもできる。
-
ブロックのスピードは「LOW」<「MED」<「HI」の3段階で選択可能。
-
「ROUND」は『ドクターマリオ』の「レベル」にあたるもので30段階あり高いほど固定ブロックの初期数が増える。
-
VSモード(1P VS CPU)時はSPEEDとROUNDの設定を変える際にFC版とGB版ではBボタン・SFC版ではLまたはRボタンを押しながら操作することでCPUの数値だけを変更することができ、任意にハンデをつけることができる。
-
GB版は『スーパーゲームボーイ』に対応しており、ポーズ中にAまたはBボタンでゲームオリジナル枠背景が発動し以後AまたはBで選択できる。
ゲームモード(全共通)
1Pモード
-
すべての固定ブロックを消して得点をハイスコアを目指す。
-
移動ブロックは10点、固定ブロックは20点、フラッシュブロックは40点。
-
連鎖により得点は倍増する。2連鎖で2倍、3連鎖で4倍、4連鎖以上は8倍。
-
他に早くクリアすることでボーナス点が入る。
-
このモードでのフラッシュブロックの効果。
-
これを消すと同じ色の固定ブロックが全部一気に消える。
VSモード
-
2人対戦またはCPU相手に対戦するモード。
-
勝利条件は自分のフィールド内の固定ブロックをすべて消すか、相手がシャッターの位置まで詰まったら勝利となる。
-
5本制で、3本先取した方が勝利。
-
表示されているNEXTブロックは、両者で共有しているため今動かしているブロックが設置した側にNEXTブロックが出る。
-
自分が今必要なブロックを確実に取り、いらないブロックは設置を遅らせて相手に押し付けるというような戦略や判断スピードが求められる。
-
後発の『テトリス武闘外伝』でもこのNEXT共有が採用されている。
-
対CPUの場合、その思考ロジックレベルは「EASY」<「NORMAL」<「HARD」の3段階用意されている。
-
このモードでのフラッシュブロックの効果。
-
相手のフィールド内のシャッターを1段下げる攻撃になる。
-
既に自分のフィールドでシャッターが下がっている場合は、それを1段解除する。
-
フラッシュブロックを消すと、同じ色の固定ブロックのいずれかが新しいフラッシュブロックになる。
-
GBの場合、VS2PでもVSCOMでも相手側の画面がわからずシャッターの位置が見えないので、フィールド右側のバーでその位置を示している。
-
このような仕様なので『スーパーゲームボーイ』を使用しても1つのハードのコントローラによる1画面対戦はできない。
-
連鎖による攻撃。
-
このモードで連鎖をすると、次の相手の移動ブロックが落ちるスピードが急激に速くなる。
-
2連鎖なら1回、3連鎖なら2回、4連鎖なら3回までその効果が持続。
-
相手側には効果音と共にシャッターの最下段が赤に変化することで予告される。
-
SFC版の場合、フィールドが水中になっておりブロックが水面の上まではみ出すと詰まりと同様で負けとなる。
-
上記のフラッシュブロックの効果が「水面を下げる」になっているが見た目が違うのみで事実上同じもの。
パズルモード
-
後発のGB版・SFC版のみに搭載されたゲームモード。
GB版
-
移動ブロックの仕える数が最大100個までに限られ、その落ちてくる順番も決まっている。
いかに少ない移動ブロックで画面内のすべてのフラッシュブロックを消すか(必然的にすべての固定ブロックを消すことになる)というスピードよりも頭脳を試されるモード。
-
100個以内に消せないと失敗となる。
-
このモードではNEXTブロックが落ちるのをマニュアルにすることができる。マニュアルにすると、ゆっくり考えることができる。
-
最低の数でクリアできれば「パーフェクト」と表示される。
-
クリアしてもパーフェクトでない場合はリトライも可能。パーフェクトなら強制的に次のレベルへ進む。
-
残りのピースの数がスコアとなり、クリア後に記録される。
SFC版
-
「画面内のすべてのフラッシュブロックを消す」という目的はGB版と同じだが、こちらでは使えるブロックは5個以内ということで、よりパズル要素が強い詰将棋のようなものになっている。
-
こちらは全100ステージあるが初期で選べるのは30まで。以降は1ステージクリア後に次のステージに進む格好になる。
-
コンティニューはパスワード方式。
評価点
-
落ち物パズルとしては、均整が取れたバランスになっている。
-
後述の通り『テトリス』として考えるといろいろ違和感があるが「色を並べて3つ以上になると消える」「フラッシュブロックを消すが目的」と当面や最終の目的はしっかり見えていて、且つシンプルでわかりやすい。
-
対戦における連鎖やフラッシュブロック消しによる攻撃も、これも単純明快且つ効果的なものでルールはシンプルながら対戦が白熱する要素として機能している。
-
『ドクターマリオ』の発展形として考えても常に2ブロックで構成されたカプセルが4ブロックになっただけでなく、アウトライン自体が大きくなったことで、そのブロックを通す道筋を考えて配置する必要があるなど、より考えることが多くなっているなど、より落ち物パズルの深みが感じられる。
-
名前こそ『テトリス』、大まかな特徴こそと『ドクターマリオ』と思いがちだが、単純にくっつけた安直なものではない。
-
実際、対戦における攻撃方法はどちらのマネでもない。
-
フラッシュブロックの効果がモードによって異なる。
-
1P(パズルモード含)では、それを消すことがクリア目的、VSではそれを消すことで相手のフィールドの上部を狭める攻撃と、そのモードに対応した形で機能している。
-
効果が違うのは紛らわしいと思える反面、「フラッシュしているブロックを消す」という目的には変わりないため、それがゲームのカギであることに変わりはない。
-
またVSでは、フラッシュブロックの位置が変わることもあり、今見えているフラッシュブロックにばかり目が行って他をないがしろにしたため消しにくくなったり詰まることもあるなどシンプルながらも一本槍な思考では上手くいかないなど、その奥深さが感じられる。
-
対戦パズルとしては、珍しく攻撃の手段が2通り。
-
当時の対戦パズルゲームは攻撃の強弱があれども1種類しかなかった。参考までに2年後の『パネルでポン』でもそれは変わっていない。
-
その点、本作は「落ちるスピードが速くなる」と「天井を1段下げる」という2通りがあり、その役割も異なっている。
-
またフラッシュブロックは1つ消すと別の場所の固定ブロックが新しいフラッシュブロックになるので、それを考えてブロックの配置を考えることができるようになると、より対戦の深みが増してくる。
-
時期を隔てたGBもSFCも単なる移植ではない。
-
実際GBやSFCにはパズルモードがあるし、それそのものも同じモード名称ながらお互いに個性を持っている。
-
そのため発売時期の隔たりも、まんざら無意味ではない。
問題点
-
名前とは裏腹にヨコ一列を揃える概念がない。
-
『テトリス』と言えば言わずもがな「ヨコ一列に揃えて消しそのハイスコアを目指す」ものだが名前を冠しているのに反して、ブロックを似せているだけでゲーム根本ではテトリス要素がゼロ。
-
そのため、タイトルを意識してしまうとどうにも別物感は否めない。
-
連鎖ができるのは良いが、既に『ぷよぷよ』が既存でタテでもヨコでも一定数以上連なっていれば簡単に消えて連鎖がガンガンできた左記作品に比べると、その幅が狭い。
-
せめて上記作品が出る前ならば、問題なかったがどうにも上記作品のような手軽な連鎖がガンガンできたことを思うと爽快感では大幅に劣る。
-
パズルはブロック出しを「オート」にする意味があまりない(特にSFC版)。
-
考える時間が短くなるため、いわゆる難しいモードにあたるのだが、それをクリアしたところで特に特典はない。
-
どちらかと言えば上級者向きの感があり、とっつきやすさという点では当時の同ジャンルの中では劣る。
-
同じようなゲーム性の『ドクターマリオ』と比べると、ブロックがテトリミノ形状のため自身で置いた移動ブロックが邪魔になりやすく、いろいろ複雑に考えることが多いため勢いだけで楽しめるようなスタイルとは言い難い。
-
また、分離するブロックもあり、本作特有のクセの1つとして無視はできない。
総評
当時から「どこがテトリスなの?」というツッコミが多かったようにテトリスの発展モデルのような名前に期待して購入してみると全然別物で期待していたものとの違いを感じずにはいられない。
自分で置いたブロック自身が邪魔になりやすかったり連鎖が手軽でなかったりととっつきやすさという点では今一つで、この当時既に様々な落ち物パズルゲームがあり特に『ぷよぷよ』のようなとっつきやすい名作があってはタイトルの不整合も含めて否定的に見られやすいのも無理はない。
ただ、それに囚われずオリジナルのパズルゲームとして見れば完成されたゲーム性であり、対戦では2種類の異なる攻撃方法があるなどしっかりとした個性を持っているのは間違いなく若干の難しさも含めてこのゲームの持ち味として受け入れられるならエキサイティングな対戦を楽しめるし、1人プレイでも深みのあるパズルにとことんハマっていけることだろう。
余談
-
欧米では本作が『TETRIS 2』のタイトルで発売されている。
-
「発展形テトリス」をより意識しやすいタイトルだけに期待外れな印象を抱いたことだろう。
-
これにより、国内のFC『テトリス2+ボンブリス』やSFC『スーパーテトリス2+ボンブリス』は欧米では未発売となっている。
-
本作は『ヨッシーのクッキー』以来のファミコン・ゲームボーイ・スーパーファミコン三兄弟ハードでの発売作品である。
-
しかもスーパーファミコンのみが任天堂ではなくBPS発売という点でも同じ。
-
BPSからアーケード版も発売する予定で、1994年の春頃に新宿等でロケテストが行われていたが、未発売に終わっている。
-
アーケード版ではアトラスの『ななめでマジック』みたいなコミカルタッチのキャラクターを選んで対戦するといった内容だった。
-
CMでは「あのテトリスブロックがピカピカピカピカフラッシュする」と最初に言われる。
-
確かに間違いではないが直後のゲーム画面を見て、やる前から「どう見てもテトリスじゃない」と思った人多数。
-
ゲームの内容そっちのけでナレーションを担当した声優の古川登志夫氏の必殺技よろしく「テトリース フラーッシュ!!」の叫びはムダに印象に残るものだった。
-
CMのラストにも見られるようにゲームボーイ版は当初ファミコン版発売から1ヶ月後の10月21日に発売される予定だったが、結果的に8ヶ月も後ろ倒しとなった。
|
+
|
CM「テトリース フラーッシュ!!」
|
|
最終更新:2023年08月13日 18:22