下書きの記載に関するルールの変更について
(24/5/26変更)
記事が完成するまでの間は最低でも週に1度は記事作成相談スレを確認するようにしてください。
記事作成依頼の判断は初稿者に委ねられますが、下書きが完成したと判断しても別の利用者が追記や修正を行うことも踏まえ、記事化依頼前にスレで意見が挙げられているか確認してください。
記事を直接投稿できるメンバーの方も、「記事下書きページを利用する場合は」性急な記事化は避け、スレを確認することを推奨します。詳しくは利用法をご確認下さい。
ゲーム記事や用語集項目など、Wikiコンテンツ作成時の下書き用ページです。ここにある記事は正式作成前の扱いのため、リンクの作成や修正依頼・要強化依頼の添付は禁止です。
また、表示負担軽減のため動画はコメントアウト状態で記載してください。
下書きに画像をアップロードするのは控えてください。記事化後も画像が下書きに残り続けてしまうためです。
アップロード画像を使用する場合は記事化後に該当記事にアップロードしてください。
また、記事化前に画像のチェックが必要な場合には、外部の画像アップロードサービスを利用してください。
メンバー権限がない人は新規ページ作成ができないため、記事の作成は下書きページを経由する必要があります。
メンバーではない人は下書き完成後に記事作成依頼所から記事ページ作成を依頼してください。
権限がある人は下書きを経由せず直接ページを作成して構いませんが、以下の場合は下書きページの利用が推奨されます。
加筆、修正、下書きを元にした新規記事の作成は自由です。ただし、
自分がプレイしたことのない作品の記事化は禁止
とします。
また「このWikiで扱う作品」及び「記事作成のガイドライン」を参照の上でお願いします。記事作成相談スレも活用してください。
「記事下書き」は用途別にページが分かれています。
| + | 下書き用テンプレート。書き方の詳細はテンプレのページを参照 |
一般的な編集の練習は「サンドボックス」へどうぞ。
初稿投稿日: 2025/10/13 追記修正歓迎
【ばーちゃふぁいたー つー】
| ジャンル | 格闘ゲーム | |
| 対応機種 | アーケード(MODEL2基板) | |
| 発売元 | セガ・エンタープライゼス | |
| 開発元 | セガ・エンタープライゼス(第2AM研究開発部) | |
| 稼働開始日 |
『2』:1994年11月 『2.1』:1995年7月 |
|
| プレイ人数 | 1~2人 | |
| 判定 | 良作 | |
| ポイント |
『ストII』に続く社会現象を起こした格闘ゲーム 筐体の中で人間が生きているとも評されたグラフィックの進化 操作性の良さや爽快感も抜群 |
|
| バーチャシリーズ | ||
『バーチャファイター』の続編。
1995年には一部ゲームバランスを調整した『バーチャファイター2.1』が稼働開始している。
グラフィックは変わっておらず、タイトル画面やゲーム中の残り時間のUIの上側にゲーム内フォントで「.1」と示されているかどうかで判別可能。
(セガサターン版説明書4ページから引用)
「世界格闘トーナメント」…。
それは、世界中から集まったあらゆる格闘家が己の肉体だけで死闘を繰り広げ、
世界一の格闘技王を決める、究極の武闘大会であった。
栄えあるその第1回大会に出場した戦士たちの顔ぶれは、そうそうたるものであった。
八極拳の使い手、結城晶。
截拳道の担い手であるジャッキーとサラのブライアント兄妹。
虎燕拳のラウ・チェン、燕青拳のパイ・チェンの親子。
パンクラチオンの使い手であるジェフリー・マクワイルド。
プロレス技を得意とするウルフ・ホークフィールド。
葉隠流柔術の影丸ら8人。
そして…。
第1回の優勝者は、伝説の虎燕拳を使うラウ・チェンであった、
その風格さえ漂う拳の前に、八極拳の使い手、結城晶は自分自身の未熟さを知る。
そして大会終了後、修行の旅に再び出ることになる。
1年後、修行を続ける晶の元に1通の手紙が届いた。
それは第2回世界格闘トーナメントの招待状であった。
招待状の中には参加者リストが同封されており、前回優勝者ラウの名前と彼も知らぬ
新たな挑戦者の名前があった、
そして何かしら感じる、邪悪な雰囲気。
しかし彼の格闘家としての血が、トーナメントへの参加を決意させた。
新たな技を身につけたであろうライバルたち、新しい挑戦者、謎の組織。
様々な思惑をまといつつここに、「第2回世界格闘トーナメント」が開催される…。
これらの仕様は本作が同ジャンルの先駆者(他に参考になるタイトルがない)であることから開発中に厳密にゲームバランスが検証・調整が出来ておらず、全国的に対戦が行われた事で問題が発覚し現在では格闘ゲームを作る上でご法度になっている、いわば「昔の格闘ゲームあるある」が多い。
これらの仕様を本作ならではの味として楽しむプレイヤーも少なくない事から賛否両論点扱いとしている。
この他にもキャラ単位で「躍歩頂肘」「立ち斜上」に代表される調整が甘く異様に強力な技は多数存在しているが、ここでの説明は割愛する。
格闘技を通してポリゴンを使ったリアルタイムレンダリングによって描かれた人間が生き生きと躍動する姿を描いたゲームとして、本作はゲーム史上に鮮烈な印象と名を残した歴史的一作となった。
対戦ゲームとしての完成度も高く、熱中性の高い対戦型格闘ゲームというのも相まって全国にバーチャジャンキーを生み出すことにもなった。
稼働から30年経った現在から見るとキャラクターの少なさからボリューム不足にも感じられるが、3D格闘ゲームのプリミティブな面白さを味わえる作品として現在もその価値は色褪せていない。
初稿投稿日: 2025/10/13 追記修正歓迎
本記事は『スタージャッカー』に追記する形での追加を検討しています。
【すたーじゃっかー】
| 対応機種 | SG-1000/SC-3000 | 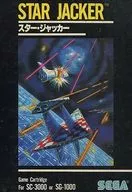 |
| メディア | 32KbitROMカートリッジ | |
| 発売日 | 1983年7月15日 | |
| 定価 | 4,000円 | |
| 判定 | 良作 |
アーケード版との相違点は以下の通り。
また、ROM版には前期版と後期版があり、後期版では以下の要素が追加/変更されたいわゆるアップデート版となる。
アーケード版との性能差から一部オミットされた要素こそあるものの、プレイ感覚はそのまま維持しつつ遊びやすい難易度に調整された良移植。
初期のSG-1000/SC-3000を代表する名作として名高い。
初稿投稿日: 2025/10/19 追記修正歓迎
【どんきーこんぐ ばなんざ】
| ジャンル | アクション |  |
| 対応機種 | Nintendo Switch 2 | |
| 発売・開発元 | 任天堂 | |
| 発売日 | 2025年7月17日 | |
| 定価 |
パッケージ版:8,980円 ダウンロード版:7,980円(全て税込) |
|
| レーティング | CERO A(全年齢対象) | |
| 判定 | 良作 | |
| ポイント |
爽快感と自由度の高さ 良好なストーリー |
|
| ドンキーコングシリーズ | ||
Nintendo Switch 2専用で発売されたドンキーコングシリーズ最新作。
ドンキーコングとしては『ドンキーコング64』以来、約26年ぶりの3Dアクションである。
開発は『スーパーマリオ オデッセイ』の開発チームで、ドンキーコングのパワフルなアクションを重視しており、あらゆる物を破壊できる爽快感満点なゲームとなっている。
黄金のバナナの発見に沸く鉱山の島インゴス島。
バナナに目がないドンキーコング(以下、DK)もインゴス島を訪れるが、突然島を異変が襲い、島ごと地下へと沈んでしまう。
DKは不思議な岩の中から出てきた少女ポリーンと出会い、バナナと異変の原因を探るため地下世界へと向かう。
DKはバナナのため、ポリーンは地上へ戻るため、何でも願いが叶うという星の中心を目指し大冒険がはじまる。
DKの基本アクション
バナンザ変身
スキル
その他
DKアーティスト
有料ダウンロードコンテンツ
あらゆる物を破壊する爽快感と自由度の高さ
改良されたゲームシステム
多彩なステージとNPC達
DKとポリーンの関係性を描くストーリー
| + | 終盤の重大なネタバレ注意! |
BGM
ドンキーコングのパワフルなアクションとゲーム性がマッチした傑作アクション。
ストーリーやキャラクター描写も良好で、全体的な完成度の高いNintendo Switch 2を代表する一作と言えるだろう。
Switch2を購入したら、まず本作を遊べば間違いない。