私によく本を貸してくれる友人の、一番のお勧め本がこれでした。ある一頭の競走馬オラシオンが誕生し、やがて競走馬になる過程を、彼を取り巻く牧場や馬主、ジョッキー達の人間模様が描かれています。馬自体は感情を表さず、ただ生れ落ちて走るだけなのに、周りを奔走する人間は対照的にどろどろぐちゃぐちゃ感情が入り乱れます。
前に宮本輝を読んで思ったのですが、オチやどんでん返しやネタばらし、そういうものが無いんですよね。それを文学と言うのでしょうか。流れるような、そんなお話でした。決して面白くなかったわけではないのですが、なーんか感想を言葉にできないもやもや(物語に対してではなく)が残ります。なんでだろう。思いつくままに羅列するとこんな感じ。
途中で読むのをやめたくなったか?→そんなことはない。
ハラハラドキドキしたか?→それはない。
あまり好きなキャラはでてこなかった。性格が生々しくて、あまり好きになれなかった。地味なお話だった。だからこそ現実にありそうな、あり得るお話だった。
私は元々競走馬に興味が無かった。馬主やら牧場やら、私の生活には接点が全然ないお話。感動したようなしなかったような変な感じ。
いつもなら、結局面白くなかったのでは?という結論に行き着くのですが、この人のお話に関しては、一刀両断にそう切り捨てることもできない、と思ってしまうのです。これを面白くないと言ってしまうのが怖いだけかもしれませんが。
牧場経営とは/競馬のジョッキーの事情/馬主になるとこんなことがある、とか私の知らない世界でそのへんは純粋に面白く読めました。競馬が好きな人は一度読んでみてはいかがでしょうか。私にこれを勧めてくれた人は無類の競馬好きでした。だからお気に入りみたい。
ここから先はネタばれになります。
登場人物に感情移入できないと書きましたが、周りにいないタイプばかりだったので(野心家タイプやらお嬢様、純情朴訥牧場少年)それも原因かもしれません。特に久美子は同性なのに、全く共感できませんでした。ホテルに行くくだりは、なんじゃそらと思いながら読んでいました。例えば自分とは全く違う考え方をする人に、共感できなくても理解はできる、ということがあるのですが、今回はそれもありませんでした。なんとなくですが「島耕作」を楽しく読める人が合ってるんとちゃうかな。私が子供で、人生に疲れてもいなくて野心家でもないから、生々しさを感じる一方で、リアリティを感じられないのかもしれません。
文章は読み易くて、流れるように綺麗です。でも多分もう読まない。でもでもこの人のほかの本は多分読む。
(2009/02/13)

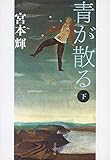
この人の本を読むのは四作目になります。苦手に思っていたのですが、これは面白く感じました。また、苦手なところはそのままで、それでも面白かったので、大収穫だと言えます。トリックや小細工、伏線とかどんでん返し、そういうのがなくても本は面白いのだ、と思えたことがとても嬉しいです。
お話は主人公の燎平という大学生が、自分が一期生となる新設大学に入学し、卒業するまでを描いています。入学直前に夏子という同い年の女性に出会って恋心を抱いたり、強引な誘いに負けて渋々入ったテニス部が意外と続いたり、色んな種類(神経を病んでいたり、歌手を志していたり、バンカラ応援団だったり、皮肉屋だったり、熱血テニス野郎だったり)の友人ができたり。全く甘酸っぱくない(当社比)のですが青春物語といったところでしょうか。
全員が関西人であることや、神戸・大阪が舞台であることや、硬式テニスの描写が面白かったことで、読んでいて楽しかったです。
私がこの作者を苦手な理由の一つに「登場人物の誰にも共感できない」があるのですが、今回は「共感はできないけど嫌いではない」って感じでした。好きでもないけど。若者なりの怠惰なところや青臭さが率直に書かれており、それはそれで良いのだけれど私は「こういう奴苦手」で終わってしまいました。でも金子や祐子は実際にいたら好きかもしれない。
燎平は主人公でしたが最初から最後まであまり好きにはなれませんでした。特にテニスの公式試合で「知らない奴の試合なんかどうでもいい」と適当に審判したシーンでは、猛烈に腹が立ちました。私もテニスをしていたので、「それはしたらあかんやろ」と一気に嫌いになりました。まぁ彼にはショックなことがあったのですが、それにしてもその一点は憤慨しました。
時代が古いので、今若い人が読んだら「それの何があかんの?」ってこともあると思います。そうそう、「国鉄」って懐かしい!「傷物」なんて久しぶりに聞いたよ。
厳密に言うと私がしてたのは硬式テニスではないのですが、テニスの描写があったから面白かったのかなとも思います。特に燎平とポンクの試合は、読んでいるのに続きが気になってしょうがなかったです。
ここから先はネタバレです。
色んな人が出て来て、結局なんやったんかいなという気はしないでもないですが、誰かの生活を追いかけたらきっとそんなもんなんだろうし、その出会いが何も生み出さなくたって不思議には思わないでしょう。「ある男性の大学生時代4年間を切り取った本」、そう私は受け取りました。
燎平の大学生活は夏子で始まり夏子で終わりました。オチとしては「結局二人は何もなかった」になるんでしょうけど、
その他にもたくさんエピソードがあって、覗き見をしているような気分になりました。夏子を好きだけどテニスにのめり込む、言いたいことが言えない、祐子にも何らかの感情を抱いていた。この作者には「もどかしさ」をよく感じますけど、きっと私の生活を上から見ている人がいたら同じように感じるのかなぁ。
夏子が婚約者のいる田岡と付き合った挙句別れて、結局田岡は婚約者と結婚するのが分かった時、燎平は夏子に「田岡は何も失わなかった。夏子を抱いただけ得やった(意訳)」と言うシーンがありましたが、すごく違和感を感じました。確かに婚約者を傷つけた点では許されないことですけど、夏子は何かを失ったのかなぁと考えてしまいます。失ったとしたら「純粋な強さ」とかそういう目に見えないものでしょうか。それか「純潔」。でも燎平は違う意味で言っていると思うし。夏子の「私が田岡を嫌いになった」という台詞を信じるなら、捨てられたのは田岡の方でしょう。それでも損をしているのは夏子なんでしょうか。貞操観念が、当時と現代でこんなに違うものなんでしょうかね。不実な男と結婚しなくてよかったやん、と思ってしまいました。
(2007/08/15)

宮本輝さんの本です。読んだのは多分二作目です。お目当ての本がなかったのでこれを買いました。実はずっと宮本亜門と混同していて、著者近影見て初めて勘違いに気付きました。
離婚した夫婦が手紙をやり取りする、その手紙だけで物語を進める形式です。浮気相手に無理心中され損なった夫と、それが原因で別れた妻が、十年後に偶然旅先で出会います。妻はそれをきっかけに別れた当時聞けなかったことを聞きたい、と手紙を出し、そこからやり取りが続くのです。解説での指摘で初めて気付いたのですが、完全に手紙の内容しか書かれていなかったのに、彼らに何があったのか、そしてどんな想いでいたのかが普通の描き方と遜色なく理解できました。さらっと読んでしまいましたが、すごいことだと思います。客観的な視点が一切入らないのですから。
舞台が芦屋となっていて、(手紙は標準語ですが)話し方が関西弁なのもとっかかりが良かったです。著者は私と同じ神戸出身なのですね。関西弁が上手なのも当たり前か。妻はかなりのお嬢様らしいのですが、「芦屋出身」と言われただけで納得してしまいました。逆に「そっか芦屋のお嬢はこんなんなんかー」と思ったり。
自分で言うのもなんですが、毛色の違うものを選んだなーと思いました。こういうのが正統派っていうんでしょうか。ミステリとかそういうオチがあるものばかり読んでいると、オチがないことに物足りなさを感じてしまいました。面白かったかと聞かれれば、読み易かったと答えます。答えになっていませんね。うーん。本当に読み易かったのです。ただ続きが気になってしょうがないとか、はらはらどきどきする、とかそんなんはありませんでした。言ってみれば、夫の浮気に関して蓋をしてきた過去に初めて向き合った、妻の自分探しみたいな物語でしょうか。これは私がもっと大人になってから読むべきものかもしれません。
(2006/05/07)
[カウンタ: - ]
最終更新:2009年06月07日 17:38