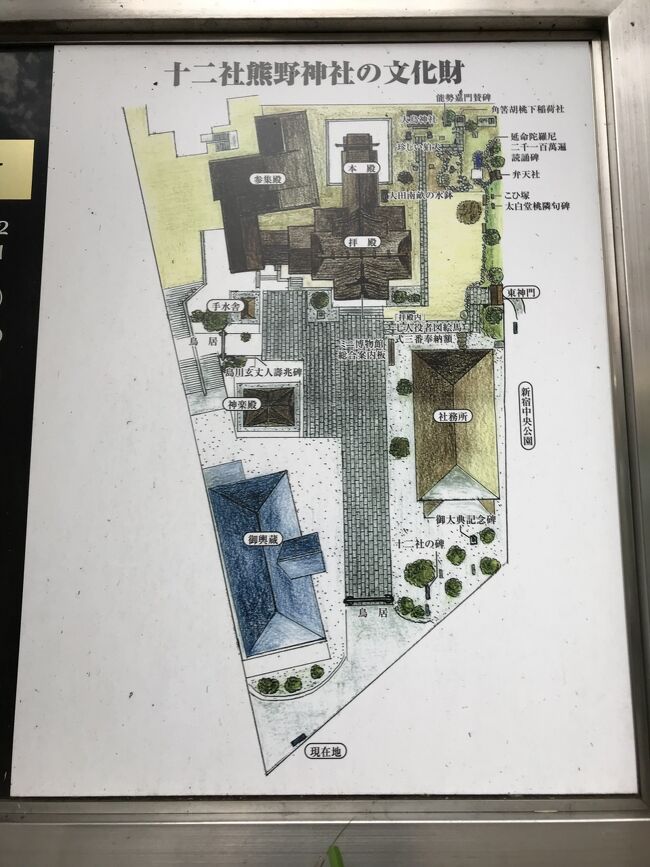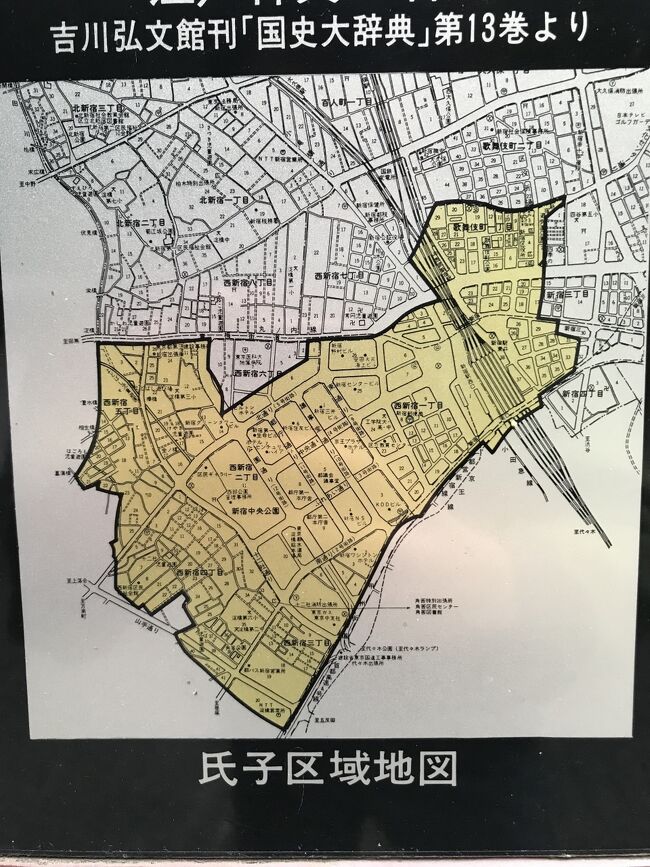熊野神社
くまのじんじゃ

- 応永年間(1394-1428年):中野長者と呼ばれた商人・鈴木九郎によって創建されたと伝えられている。(天文・永禄年間に当地の開拓を行った渡辺興兵衛という人物が祀ったという異説もあり)
- 江戸時代:熊野十二所権現社と呼ばれていた。神社境内には大きな滝があり、また隣接して十二社池と呼ばれていた大小ふたつの池があり、景勝地として知られた。茶屋や料亭などが立ち並びやがて花街となった。
- 明治時代:熊野神社に変更。滝や十二社池は淀橋浄水場の造成や付近の開拓により姿を消し景勝地としての様相は徐々に見られなくなっていった。
関連項目
最終更新:2024年10月09日 23:33